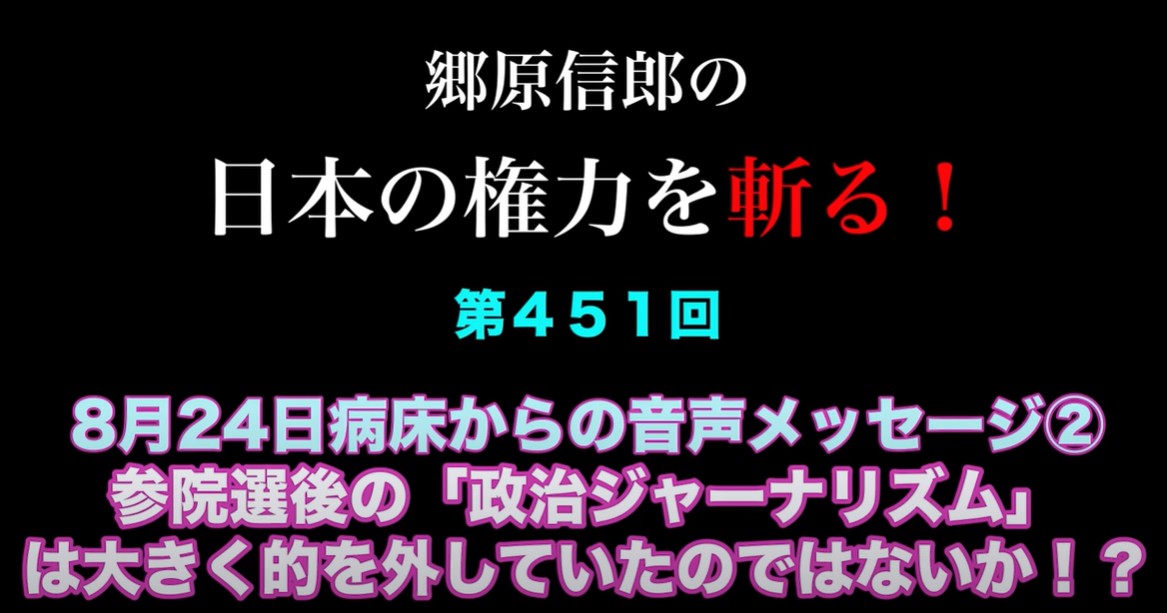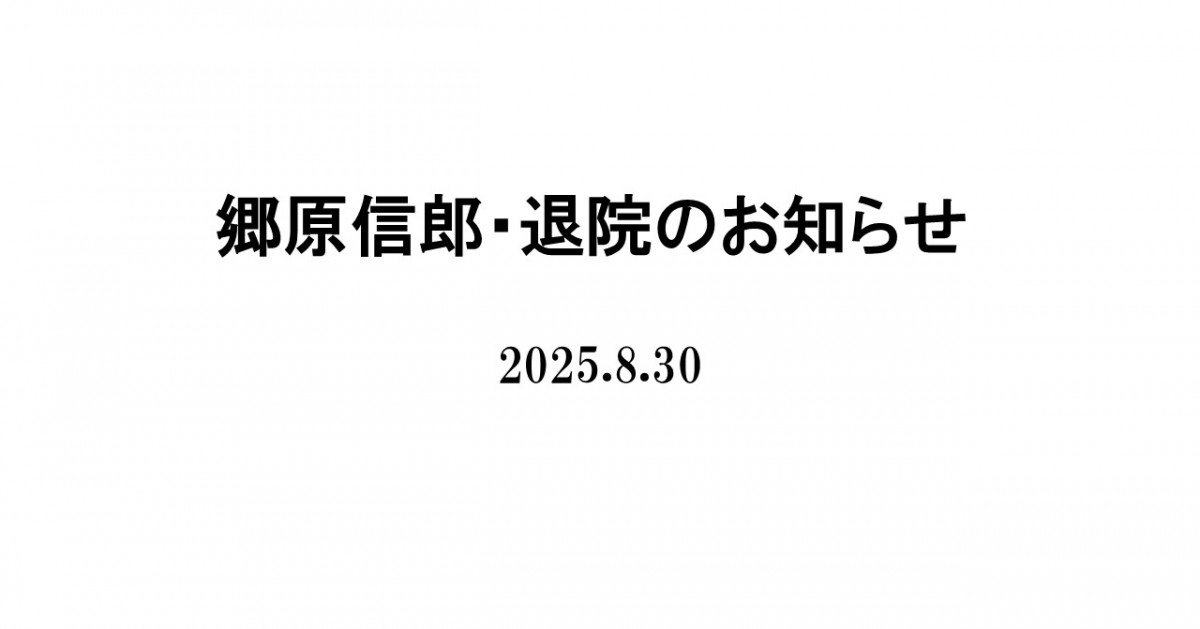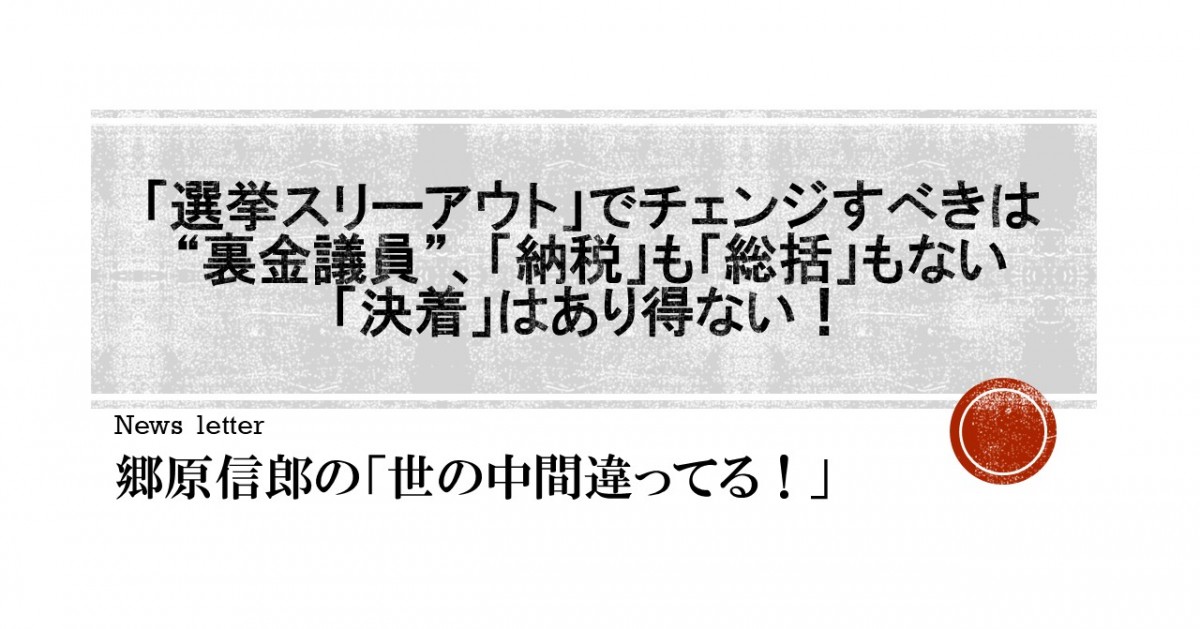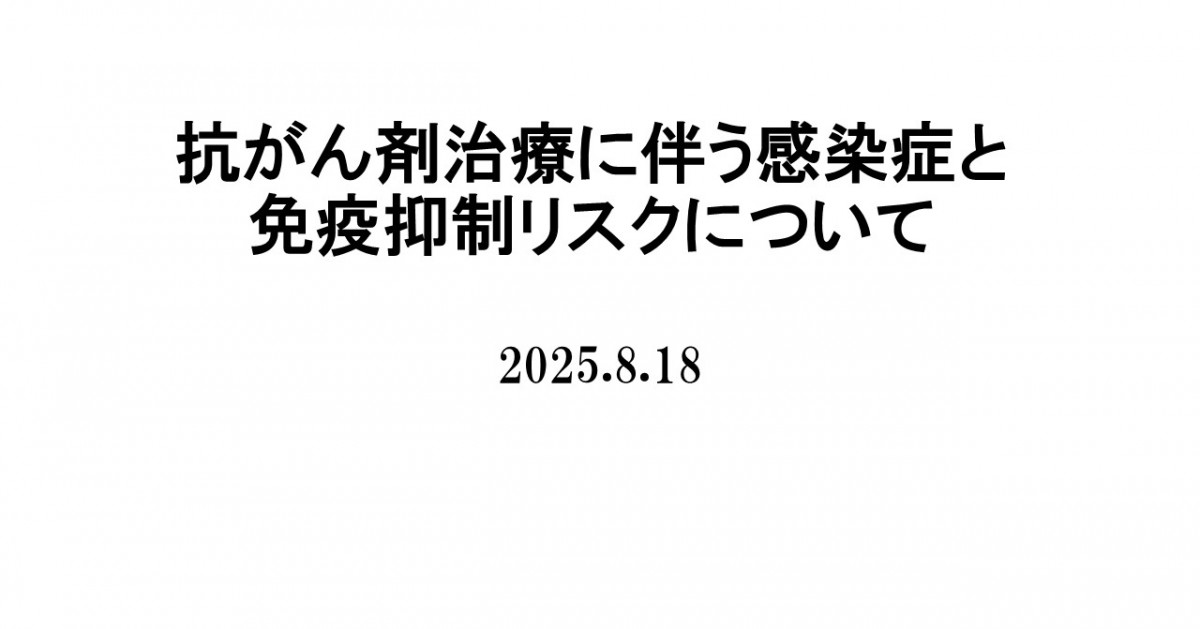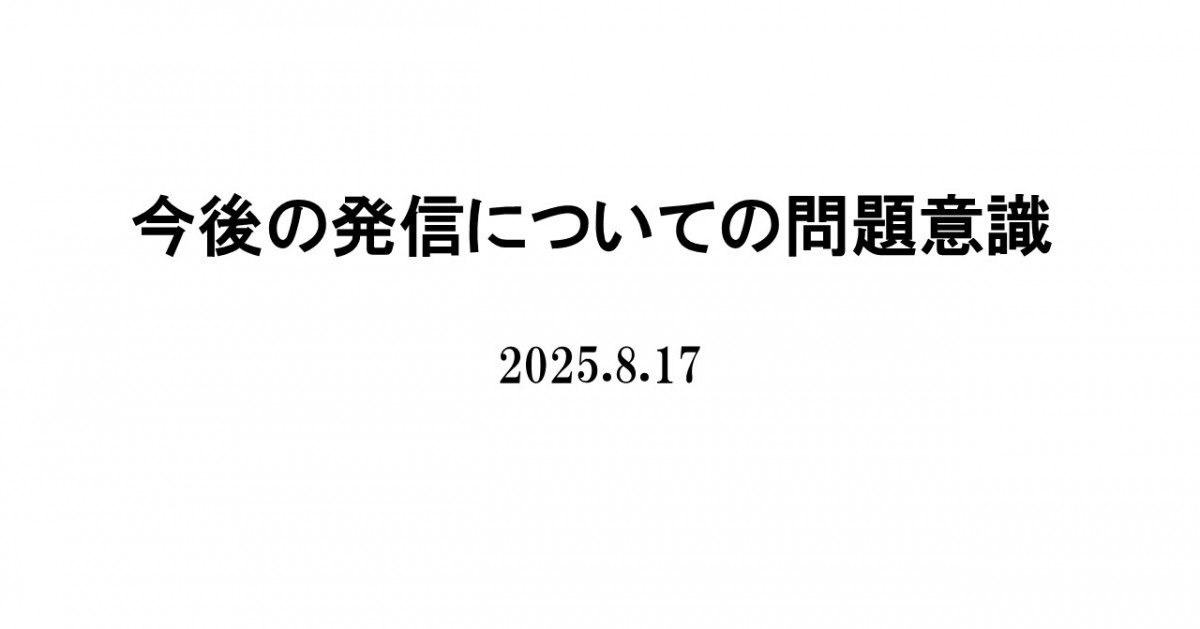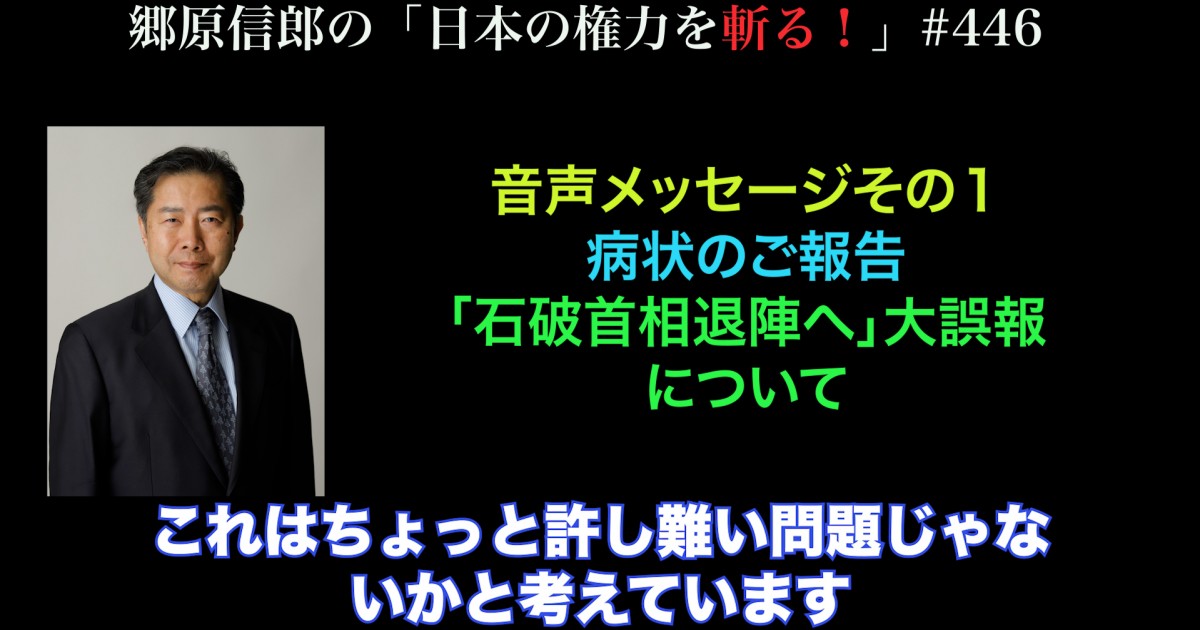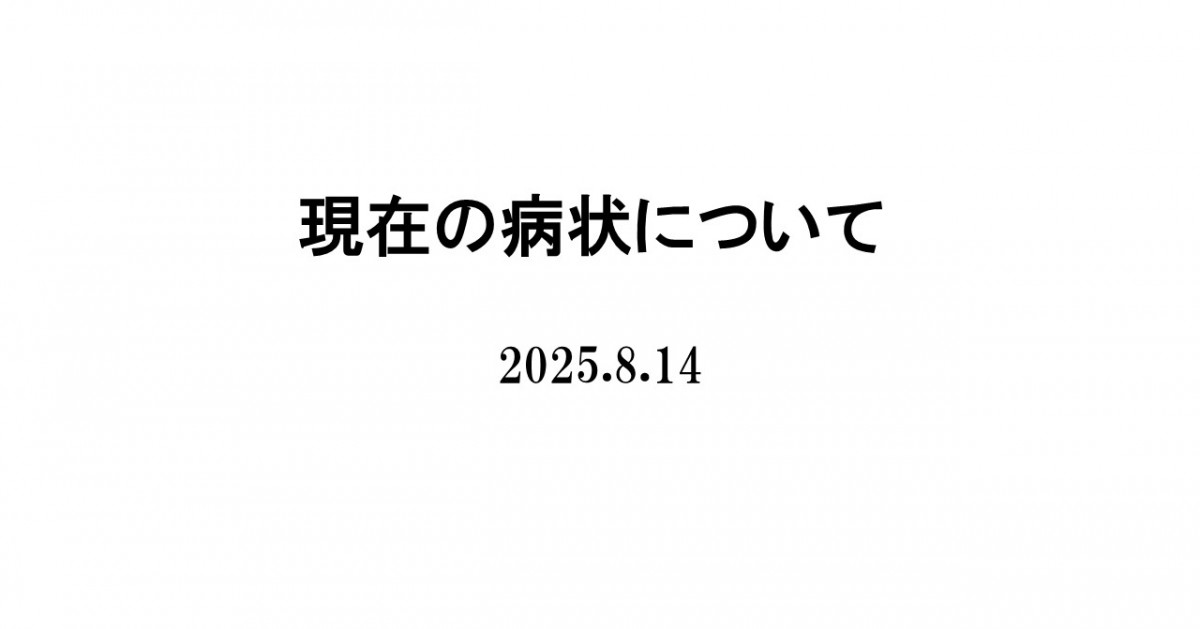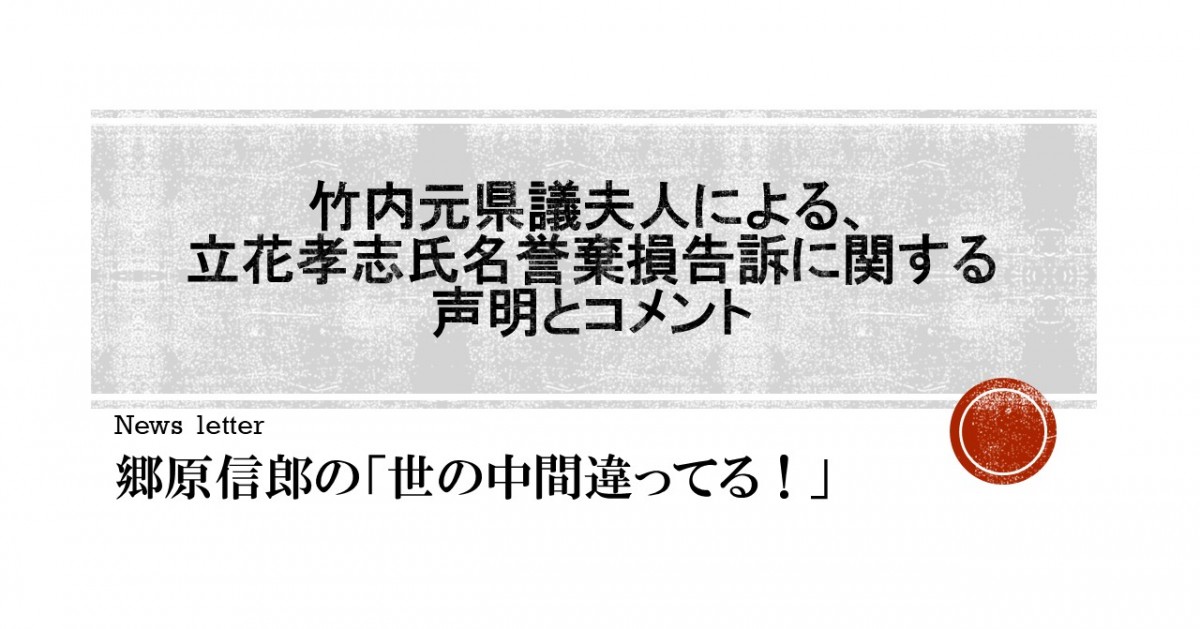小泉進次郎新農相「備蓄米随契安値放出」を“ヒーロー視”する風潮の危うさ
「コメは買ったことがない」発言で辞任に追い込まれた江藤拓氏の後任として農林水産大臣に就任した小泉進次郎氏は、就任会見で備蓄米を随意契約で安値放出する方針を打ち出し、その後、テレビ番組に出演するなどして価格を5キロ当たり2000円まで下げる方針を明言しています。
コメ価格高騰に対する国民の不満に対するパフォーマンスにも見えるこの「備蓄米随契による安値放出」には、農水省の施策としてコンプライアンス上の問題があります。コメ価格の下落で喝采を受けても、中長期的にみると、コメの需給をめぐる弊害、混乱の拡大につながる恐れがあります。
そもそも備蓄米は、本来、天候不順や自然災害、病害虫の被害、戦争や国際情勢の変化などによって、国内の米の生産や供給が一時的に困難になった場合に、国民が必要な食料を確保できるようにするためのものです。それを、コメ価格の変動に対応して国が価格を操作する目的で使うこと自体が、本来の目的に反します。
しかも、備蓄米は、国の財産であり、売買契約契約を締結する場合は、原則として、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならないこととされています(会計法29条の3第1項)。
今回実施されようとしている「随意契約」は、入札などの競争を経ずに特定の業者を国側が選定して契約する方式であり、①契約の性質又は目的が競争を許さない場合、②緊急の必要により競争に付することができない場合、及び③競争に付することが不利と認められる場合において行うことができるとされている契約形態です(同条第4項)。
今回の備蓄米の売却は、これまで入札で行われていたのですから、①の「競争を許さない場合」にも、②の「競争に付することができない場合」にも当たらないことは明らかです。
問題は、③の「競争に付することが不利」と言えるかどうかです。
備蓄米を市場に安く供給することが現在の政府の意向だとすれば、入札で競争させることで価格が高くなることは政府の意図に反することになるとは言えるでしょう。しかし、会計法の規定の「不利」というのは、競争に付することによって高値で売却できることにより得る経済的利益を上回る具体的な不利益が生じることです。国の政策や意図に反することは「不利」には含まれません。
そうすると、備蓄米の随意契約による放出は、会計法上許容されているとは言い難いでしょう。それでも随意契約で放出するというのであれば、政治判断による「超法規的措置」と言うほかありません。過去備蓄米が随意契約で売却されたのは、災害時のみです。問題は、超法規的措置をとってまで随意契約で売却することが実質的に妥当と言えるかどうかです。
随意契約は競争入札と異なり、業者選定や価格設定の透明性の問題が生じかねません。政府が随意契約によって価格操作を行うことが特定の業者に利益をもたらす可能性もあり、公平性を欠く懸念もあります。中小の流通業者や消費者団体が排除されることで、結果的に国民全体への還元が不十分になる懸念もあります。中間の通業者を通さず直接小売業者に供給することで流通段階でのマージンを排除して価格を安くすることが目的なのであれば、入札参加資格を小売業者に限定すればよいのであり、入札を行わずに随意契約で売却することの理由にはなりません。
随意契約による価格設定は、市場の需要と供給による自然な価格形成を阻害します。今回、小泉農水大臣は、備蓄米放出で「需要があれば無制限に放出する」と述べており、供給量を増やすことで価格抑制を強化する考えを示しています。それにより、短期的には価格下落の効果があるかもしれませんが、中長期的には米価の不安定化を招き、生産者・流通業者双方に混乱をもたらすおそれがあります。
また、コメの備蓄制度が維持される限り、国は、今回放出したコメと同量を買い戻さなければなりません。
随意契約で安く放出した場合、それによって、市場価格の下落が継続すれば、将来的な買い戻し価格も抑えられることになりますが、市場価格は小売段階で「市場が決める」ため、コメの市場全体からすると僅かな量に過ぎない備蓄米の安値放出では、消費者価格の大幅な低下につながらない可能性があります。
「買い戻し」について、市場価格や取引実例価格を基準に購入するという備蓄米補充の通常の方法をとった場合、備蓄米の放出後も市場価格が下落する保障はないので、結局のところ、買い戻し価格が放出価格を大幅に上回り、国に財政的な損失が発生することになります。コメ価格の高騰が、庶民の生活を苦しめていることへの対策ということであれば、想定される備蓄米の放出による損失を財源にして、低所得者の直接的な経済的支援を図る方が得策ではないでしょうか。
また、2,000円という価格がもし継続するとすれば、多くのコメ農家にとって生産原価を大きく下回る水準であり、そのような価格水準が長期化すると、それによってコメ農家の経営が成り立たなくなり、離農や減反が進行し、将来的な国内生産力の低下を引き起こすリスクがあります。
このように考えると、備蓄米の随意契約による放出は、あまりに問題が大きいでしょう。
むしろ、これまで通りの公開入札による備蓄米の放出を継続することで透明性と公平性を確保する方が得策ではないでしょうか。
その場合、コメ価格全体がただちに下落することにはなりませんが、コメ価格高騰による影響の低減については、低所得層への食料支援(フードバウチャーや給食制度の充実など)を通じて、必要な層に直接的な恩恵を届ける政策の方が望ましいのではないでしょうか。
そもそも、今回のような「コメ騒動」が起きたことの背景に、長年にわたる減反政策で、コメの生産力が低下していることがあります。コメの自給率の維持のための農業政策の見直しこそが重要です。
かかる意味では、国内需要の喚起(学校給食への地元米使用の拡大、外食産業との連携)や、海外市場への販路拡大を図ることで、構造的な需給バランスの改善を目指すべきです。
備蓄米の放出は、短期的にコメ価格を下落させることには有効な政策手段となり得ますが、その方法には慎重な配慮が求められます。市場原理と公平性を尊重しつつ、農業の持続可能性と国民生活の安定を両立させる政策こそ、今後の食料安全保障にとって重要であり、小泉農水大臣の国民受けを狙ったパフォーマンスとも思える「随意契約」による備蓄米の放出は、今後の国民生活にかえって大きな負の影響を与え、禍根を残すことになりかねなません。
小泉大臣が「備蓄米の随意契約によって安値放出して価格を5キロ2000円に下げる」などとぶち上げたことを、マスコミがこぞって賞賛し、中には、「農水大臣が変わっただけで、これだけ政府の対応が変わるとは」などと驚嘆の声を上げているコメンテーター等もいます。
しかし、会計法の原則を無視した備蓄米の随契放出で市場価格に介入すること自体が、統制経済的な危険な発想であり、そういう手法を「画期的」であるかのように持ち上げて小泉氏をヒーロー視する風潮は、不安定化した政局における「危うさ」を感じます。
実際に、随意契約で放出された備蓄米が、来週から、2000円余りの価格で販売されるようですが、実際に販売されるのは令和4年産の「古古米」や令和3年産の「古古古米」とのことです。品質からすれば、従来どおりの入札で売却したとしても、相当程安くなっていた可能性もあります。
結局、小泉氏がぶち上げた「備蓄米随契放出によってコメを2000円で消費者に提供」というのは、「コメ騒動」に便乗した「空騒ぎ」に終わるのかもしれません。
すでに登録済みの方は こちら