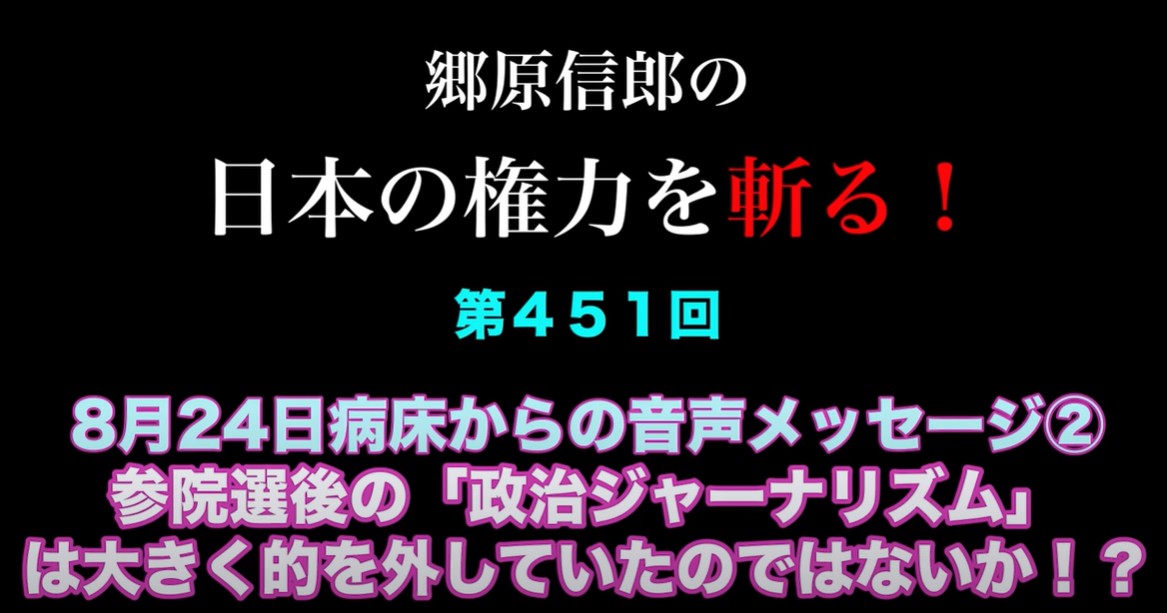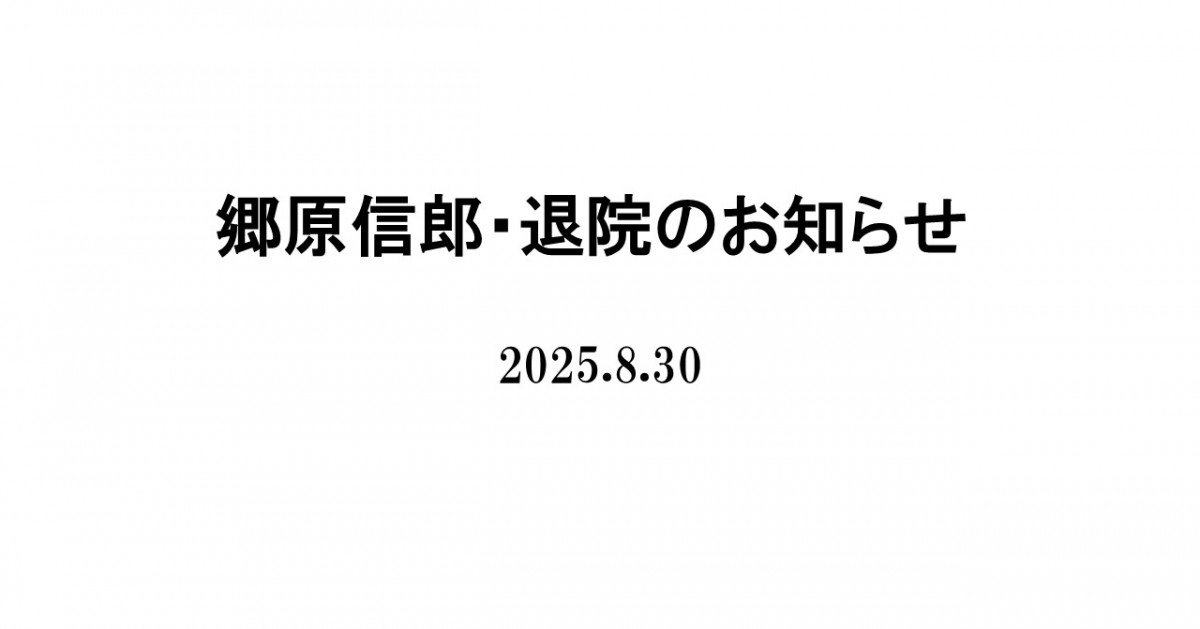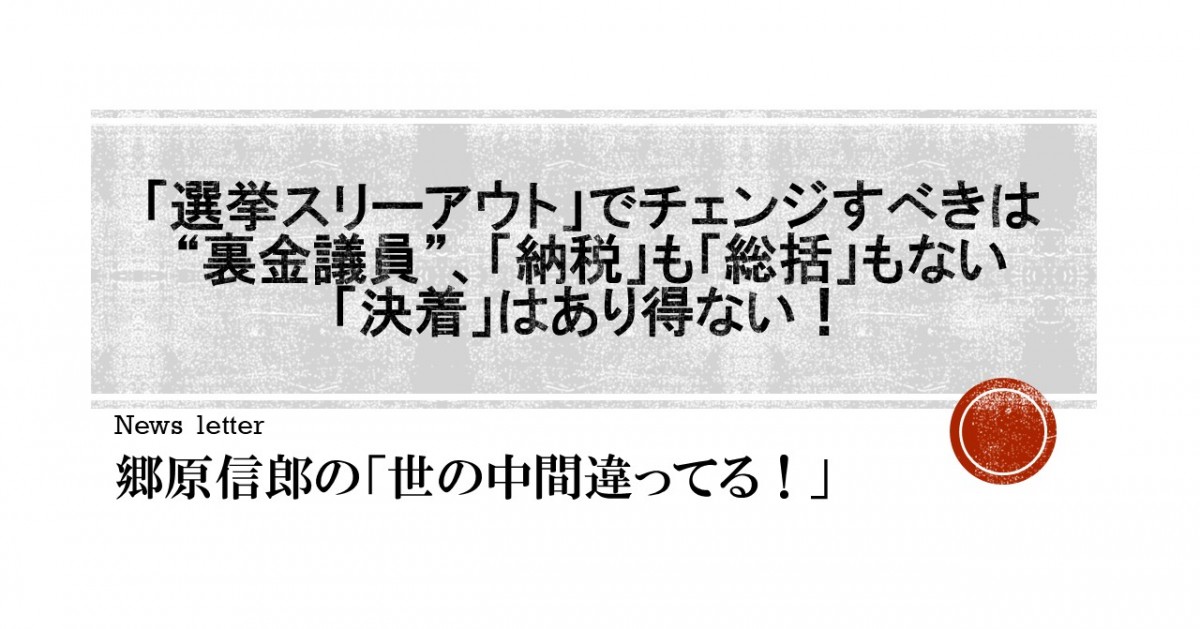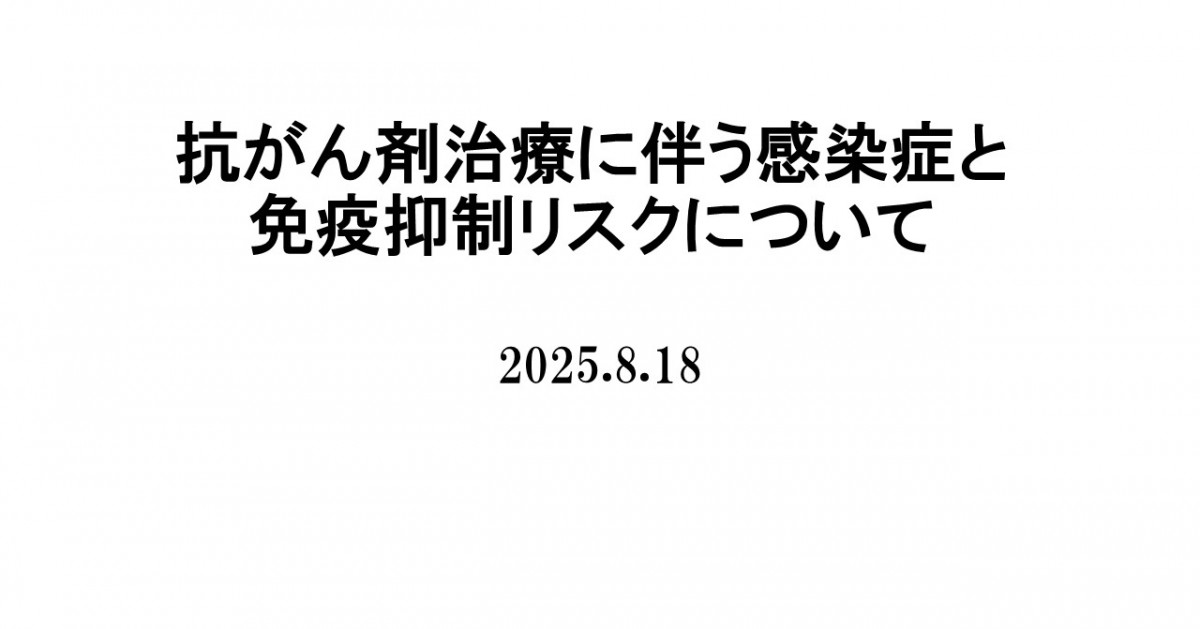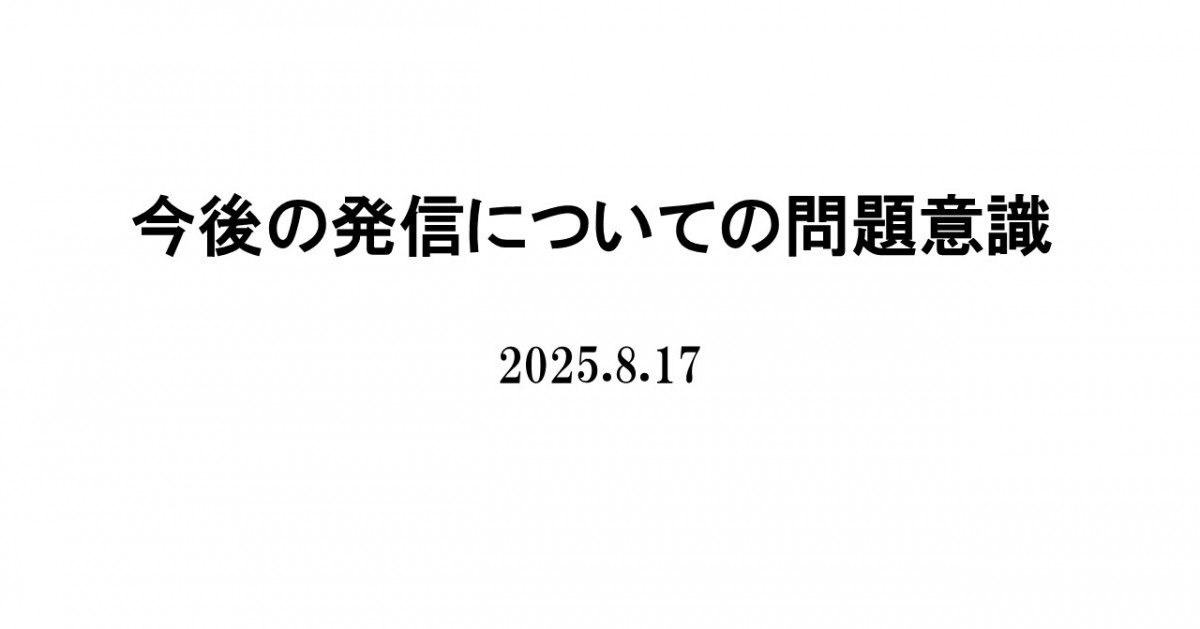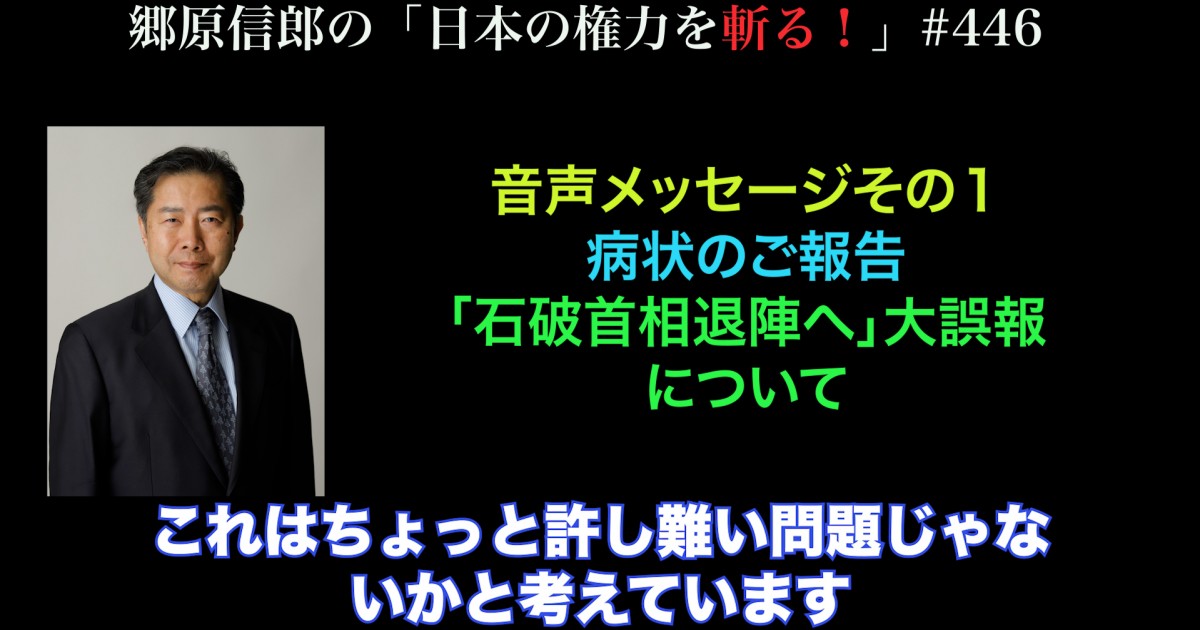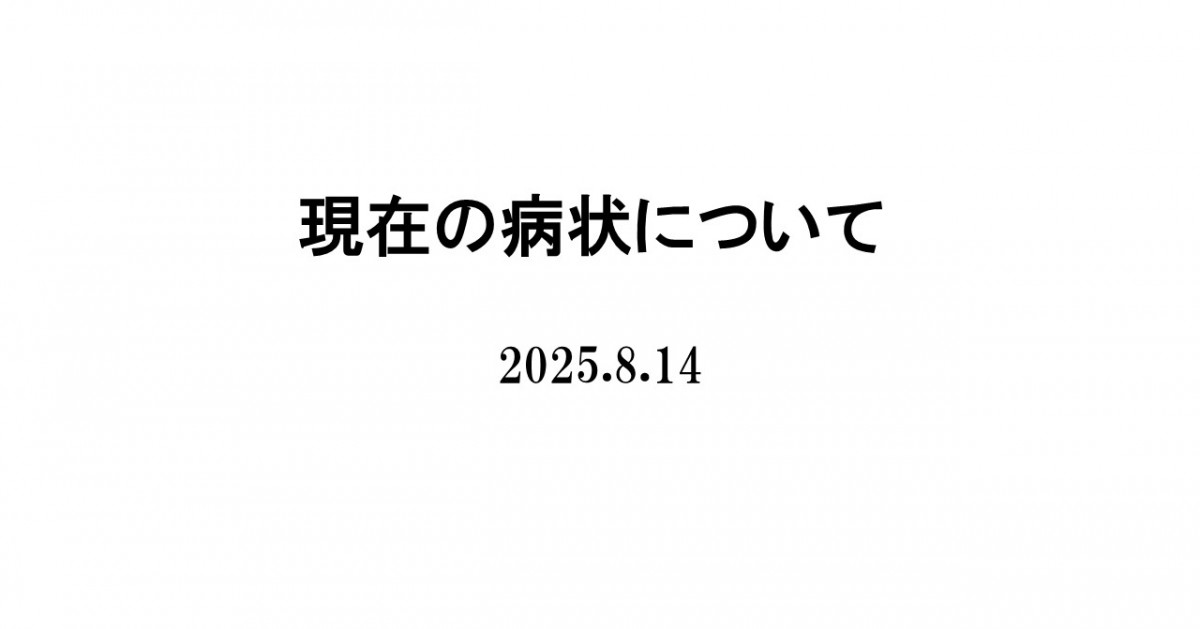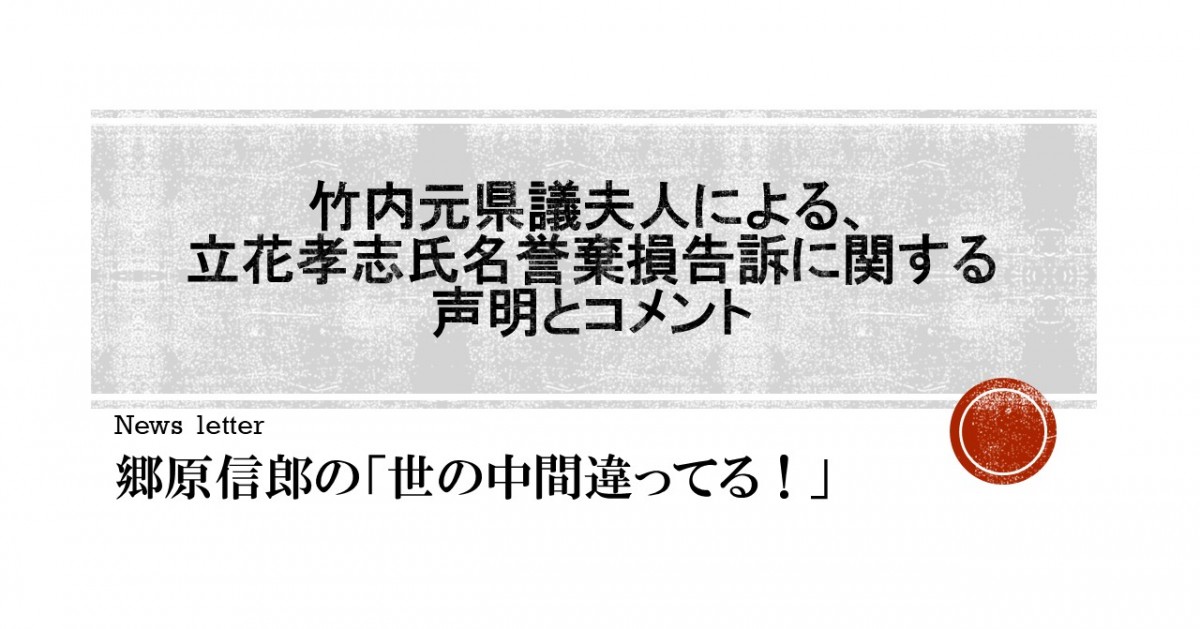森友文書、「政治家関与部分『欠落』」は財務省の大罪、佐川氏国会再喚問が不可欠
森友学園に関する財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の職員、赤木俊夫さんの妻の雅子さんが国に関連文書の開示を求め、財務省は今年4月4日、国有地の売却をめぐる学園側との交渉記録など、2000ページを超える文書を開示しました。
しかし、開示された文書には欠落している番号が複数確認され、そのうち、2014年4月19日から5月11日までの期間は交渉記録などの存在が確認されておらず、この時期の記録とみられる4つの番号が連続して抜け落ちていました。
雅子さんの弁護団から、欠落の経緯について説明を求められた財務省は、5月9日
「8年前に学園側との交渉記録を意図的に廃棄した過程で欠落文書の多くが廃棄された」
「欠落部分は政治家関係者に言及しているものが多くを占めていると推認される」
と説明したとのことでした。
財務省によると、学園側との交渉記録は、2017年に国会質問につながる材料を極力少なくすることを目的に意図的に廃棄され、その過程で欠落文書の多くが廃棄されたとのことでした。
本来、行政行為について国会での質問を受けた場合には、正しく保存された行政文書に基づき正しく説明する責任があります。ところが、財務省は、そのような「国民の代表の国会に対する義務」に反し、国会での質問を回避し、或いはその質問に答える負担を軽減するために、公文書を廃棄していました。行政を担う国家公務員の所為として到底許されることではありません。
今回、「関連文書の欠落」が明らかになったのは、赤木雅子さんが「夫はなぜ死ななければならなかったのか。そこで何が起きていたのか、真相を知りたい」という思いで行ってきた活動によるものです。
苦難の連続だった司法の場での雅子さんの国との戦いの途中から、私自身も、行政文書の開示請求訴訟の控訴審で、検察捜査の経験者としての意見書提出という形で関わりました。
改めて、これまでの経過を振り返った上、今回明らかになったことの意味と、今後行うべきことを整理することとします。
赤木雅子さんの国との戦い
雅子さんは、俊夫さんの死後、財務省側に説明や資料の開示を求めましたが、誠意ある対応がなかったため、2020年3月に、当時の財務省理財局長の佐川宣寿氏と国に対して、夫の死についての損害賠償を求める訴訟を提起し、民事訴訟の場での真相解明を求めました。
国側は当初、請求棄却を求めて争い、「赤木ファイル」等の文書は開示されましたが、改ざんに至る経緯が具体的に明らかになるものではありませんでした。その後、国は、2021年12月15日、一転して国家賠償請求を認め、「認諾」を行ったために訴訟は終了しました。
佐川氏に対する請求についても、一審判決は、佐川氏が改竄の方向性を決定づけたと認定した上で、「国家賠償法の規定に基づき公務員個人は賠償責任を負わない」と判断して請求を棄却しました。高裁の判断も同様であり、最高裁で赤木さんの敗訴が確定しました。
2021年8月、雅子さんは財務省と近畿財務局に対し、「(決裁文書改ざん問題の)調査に関する一切の文書」と「大阪地検特捜部に任意提出された資料」の開示を請求しました。
同省は「特定事件の捜査機関の活動を明らかにすることになる」などとして不開示決定をしたので、同年10月29日、雅子さんは不開示決定の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こしましたが、2023年9月14日、大阪地方裁判所は雅子さんの請求を棄却しました。
検察への任意提出文書の開示請求を阻んだ「国側の主張」
弁護団は、この開示請求訴訟には、さすがに負けることはないだろうと予測していたとのことですが、大阪地裁で出された一審判決はまさかの敗訴でした。
「検察に任意提出した文書が特定されると、将来の同種事件の捜査手法が知られることになる」
という被告の国側の主張を認めたものでした。
弁護団の控訴審に向けての打合せの中で、「検察捜査の実情に詳しい人に協力を求めることはできないか」という話が出た時、雅子さんの頭に「検察批判を繰り返してきた元特捜検事・郷原弁護士」のことが浮かんだということです。
雅子さんは、かねてから支援してくれていた田中真紀子氏に相談、真紀子氏から雅子さんを紹介された私が、控訴審向けの意見書作成を引き受けることになりました。
実は、真紀子氏と私の付き合いも、その直前からでした。その年の6月に公刊した拙著【「単純化」という病 安倍政治が日本に残したもの】(朝日新書)を読んで共感したと言って、私の事務所に電話をかけてきてくれたのがその年の9月です。それを契機に、拙著【歪んだ法に壊される日本】(KADOKAWA)で指摘した政治資金や選挙制度の問題についての勉強会を行うことになりました。「自民党派閥政治資金パーティー裏金問題」の表面化を受け、12月8日に議員会館で共同記者会見を行い、11年ぶりに「真紀子節」が炸裂し、注目を集めました(【田中真紀子氏「国会議員になるのを差し控えて」 説明しない自民批判】)。
任意提出文書の特定による「将来の同種事件捜査への影響」などない
一審判決が認めた国の主張は、
対象文書の特定情報(行政文書の名称等の情報)により、本件各被疑事件の捜査について、財務省又は近畿財務局が、どのような内容や形式の行政文書を、どの程度の範囲(時間的、人的範囲等)で、どの程度の通数にわたり、東京地検又は大阪地検に任意提出したのかが推知されることとなる。これらの情報を分析することにより、本件各被疑事件の捜査における捜査手法や(いかなる内容又は形式の資料をいかなる方法で入手したか)や、捜査対象の範囲(任意提出された行政文書の内容、範囲、通数等)といった、具体的な捜査の内容や捜査機関の関心事項が推知されるおそれがある。
将来、本件各被疑事件と同種の刑事事件のみならず、行政機関が捜査対象となる刑事事件一般の捜査についても、そのような情報や分析を踏まえて、捜査手法や捜査対象の範囲といった具体的な捜査内容や捜査機関の関心事項が推知されるおそれがないとはいえない。
というものでした。それは、検察官時代、様々な検察捜査を経験してきた私にとって、全くあり得ない理屈でした。
個別の事件で、捜査機関が、どのような文書の任意提出を求めるのか、というのは、まさに、その事件の内容、証拠関係、捜査状況に応じて検察官が判断するものであり、あくまで当該事件の個別の問題です。任意提出を求めるのは、その時点でそれを証拠として確保しておくことが必要と判断したということであり、文書等の任意提出を求めることについての検察官の判断は、事件の内容・性格、関係者の供述状況、既に収集済の証拠等によって、また、捜査対象者の協力の程度によって異なります。
私は、某地検特別刑事部長として検察独自捜査の対象としていた行政庁からの文書の任意提出を受けた事例も紹介しつつ、「任意提出を求める場合、どのような文書を含む証拠の提出を求めるのか」などということを一般的に言えるものではないし、検察官の判断で、或いは告訴・告発を受けて行う捜査の場合には、対象文書の特定情報(行政文書の名称等の情報)がわかり、捜査対象とされ任意提出された行政文書の内容、範囲、通数等がわかっても、当該捜査対象事案に関連する文書やファイル等の存在がわかるだけであり、当該時点での捜査の内容や捜査機関の関心事項が推知されることにはつながらないとする意見書を作成し、弁護団に提出しました。
被告の国側がこのような「無理筋の理屈」を主張したのは、任意提出を受けた文書の範囲がわかることが、検察にとって余程不都合だという事情があったのかもしれません。
そういう国側や検察への「皮肉」を込めて、上記意見書の結論に、以下のようなことも書き加えておきました。
本件で任意提出の要否の検察官の判断が、通常、検察官が行う判断とは異なり、不自然に消極的なものであった場合には、「事件の真相解明に向けて、検察官が適切に判断して刑訴法上の権限に基づく証拠収集を行うこと」という検察官の本来の捜査とは異なったものであること、本件の刑事処分の適正さを欠いたことを疑う余地を生じさせることはあり得るかもしれない。しかし、それは、当該個別事件で捜査についての検察官や検察庁の方針を推知する材料になるだけであり、一般的な同種事件、将来の事件の捜査手法や捜査対象の範囲を推知させるものでは全くない。
私が言いたかったのは、国が「任意提出した文書」の名称等の情報の開示を拒むのは、将来の同種事件の捜査への支障のためではなく、今回の森友関連事件の捜査処理が、通常の捜査処理からかけ離れたものだったことがバレないようにするためだったのではないかということでした。
「捜査への影響」を否定し開示請求を認めた控訴審判決
2025年1月30日、控訴審判決が言い渡されました。「将来の同種事件の捜査への影響」について以下のように判示し、一審の判断を覆しました。
財務省等の判断で任意提出された文書がいかなるものかが明らかになったとしても、これによって捜査機関の本件各被疑事件と同種事犯に対する捜査方針や意図が明らかになるとはいえない。さらに、本件各被疑事件と同種事犯の捜査であっても、当該事案や任意提出を求められる個人や組織等によってその作成又は取得する文書の種類、名称、作成時期・頻度、分量及び保管状況等は多種多様であって、本件各被疑事件における任意提出の結果のみの分析から他の同種事犯にも通用する法則性を見出すのは困難と思料されること等に鑑みると、文書特定情報の通知により本件各被疑事件に係る財務省等の任意提出の範囲が明らかになったとしても、それによって他の同種事犯にも通用する法則性のある捜査手法や捜査機関の関心事項等といった捜査機関にとって機密性の高い情報が推知されるものとは考え難く、将来の同種事犯のみならず犯罪一般の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるものとも認められない。
私の意見書を全面的に採用し、一審判決が認めた「将来の同種事件の捜査に支障がある」との国の主張を否定し、開示請求を認める判決でした。
赤木雅子さんにとって、国との裁判での初めての勝利でした。
そして、石破茂首相の決断によると伝えられた国側の「上告断念」によって、「対象文書の特定情報」が開示されることになっただけでなく、財務省は、関連文書を全面開示することになり、その第一弾として開示された2000枚を超える文書の標目から、前記の「文書の欠落」が明らかになったのです。
「無理筋の理屈」による開示逃れと「文書の欠落」
今回明らかになった「文書の欠落」は、国側が、前記のような「無理筋の理屈」まで持ち出して開示を免れようとしていたこととも関係している可能性があります。
財務省側が任意提出した交渉記録の一部が欠落していたことを認識した大阪地検特捜部側は、どう対応したのでしょうか。政治関係者に言及している文書の多くが欠落しているということであれば、まさに国有地売却の重要な経緯に関する「罪証隠滅」そのものです。
公式記録としては廃棄されているとしても、個人のパソコン等に文書の電子データが残っている可能性もあります。検察は、財務省側に徹底してデータの提出を求め、応じなければ強制捜査を検討するのが当然です。しかし、大阪地検特捜部が、そのような捜査を行ったようには思えません。
雅子さんの開示請求に応じて「対象文書の特定情報」が開示され、最終的に、任意提出した文書の内容が明らかにされると、検察の捜査が杜撰だったこと、最初から「不起訴の結論ありき」で捜査をしていたことが露見してしまうので、何とかして開示を免れようとした、それが、前記のような「無理筋の理屈」まで使って開示請求の棄却を求めた理由ではないでしょうか。
そうだとすると、私が意見書に皮肉を込めて書いたことが、「図星」だったことになります。
今回開示された文書の内容と、その一部欠落は、森友学園問題に関する検察の捜査処理に対して重大な疑念を生じさせるものです。
「北川大阪地検検事正」は、森友学園問題にどう対応したのか
それに加え、もう一つ検察の捜査処分に対する疑念を深める要因があります。
そのような重大な疑念が生じている森友学園問題に関する一連の検察の捜査処分が行われた時期が、北川健太郎元大阪地検検事正による部下の女性検事に対する準強制性交事件が起きた時期と重なることです。(北川元検事正はその後2024年に逮捕・起訴されました。)
北川元検事正の在任期間は2018年3月~2019年11月、準強制性交事件の発生は2018年9月です。一方、森友学園問題の関連事件の不起訴処分は2018年5月、2019年3月15日に不起訴になった佐川ら財務省職員10人について大阪第1検察審査会が「不起訴不当」と議決し、大阪地検特捜部が再捜査を行い、同年8月9日、財務省職員10人について改めて不起訴処分としました。
つまり、森友関連事件の不起訴処分の4か月後に部下の女性検事に対する事件を起こし、その半年後に検察審査会の不起訴不当議決があり、その後、再捜査と再度の不起訴処分が行われました。その期間というのは、性犯罪被害者の女性検事との間で、性犯罪被害をめぐってやり取りが行われていた最中だったのです。
女性検事は、仕事上、検事正と関わりを持たざるを得ませんでしたが、北川元検事正からは被害を訴えないか何度も確認されていました。事件から9か月経った頃に、事件についての認識を問いただすと、北川元検事正から、
「あなたの同意があると思っていた」
「被害を表沙汰すれば私は絶対に生きていくことはできない」
「大スキャンダルとして大阪地検は組織として立ちゆかなくなる」
などと言ってきたと記者会見で述べています。
事件から9か月経った頃というのは2019年6月頃、まさに、森友関連事件の再捜査の最中でした。検事正としての事件決裁や捜査指揮がまともに行えたでしょうか。
検察における事件の決裁は、一般の事件であれば、副部長、部長決裁で済むことが多く、次席検事、ましてや検事正まで実質的に関わることは稀です。しかし、この森友関連事件は、財務省側が被疑者であり、また、首相官邸も重大な関心を持っている事件です。もし仮に、検察審査会の不起訴不当議決を真剣に受け止め、起訴も視野に入れつつ積極的に再捜査を行い、起訴の方向で上級庁の了承を得ようとすれば、大阪地検のトップである検事正には、余程の覚悟と胆力が必要だったはずです。自らが犯した性犯罪の問題で「心ここにあらず」の「北川検事正」に、そのようなことができたとは思えません。
北川氏の性犯罪の被害者である女性検事も、自身のブログで、
「北川被告人が事件後に決裁した事件、特に性犯罪事件が適正に決裁されていたかの検証をすべき」
「佐川理財局長」の再度の国会証人喚問が不可欠
今回、財務省の森友学園側との交渉記録の中で、政治家関係者に言及する部分が意図的に廃棄され欠落していることが明らかになったことを受け、今後、どのような対応を行うべきでしょうか。
問題は二つあります。
一つは、国有地の売却に関する交渉記録の公文書を、国会での説明を回避する目的で意図的に廃棄したことについて真相を解明することです。
この問題は、2018年に朝日新聞の報道で明らかになり、厳しい批判を浴びた「決裁文書改ざん問題」以上に、悪質で弁解の余地のない行為です。決裁文書は、原資料に基づき、決裁手続に必要な事項を記載する書面であり、財務省による改ざんについても、本来決裁文書として不要な記載、言わば「余事記載」を削除したことが中心で、文書そのものの目的を阻害するものではなかったと説明されています。
検察が、改ざん行為についての虚偽公文書作成罪の事件を不起訴にした理由について「売買契約の内容などが変更されていない」「虚偽の文書を作成したとまでは言えない」と説明したのも同様の見方によるものです。
しかし、「文書の欠落」で明らかになったのは、国有地売却に関する原資料そのもの廃棄です。その対象は当時、国会で政治家側の関与やその影響が問題とされ、それに関する真実を明らかにするための公用文書です。
このような財務省の対応について、当時、理財局長として、責任者だったのが佐川宣寿氏です。しかも、安倍首相が森友学園問題での追及を受け、
「私や妻が関係していたということになれば、首相も国会議員も辞める」
と答弁した後、佐川氏は、
「森友学園との交渉や面会の記録は速やかに廃棄した」
との虚偽答弁を行っています。佐川氏自身が、廃棄を指示していた可能性もあります。佐川氏は、決裁文書改ざんが明らかになった2018年3月に参議院予算委員会で証人喚問されましたが、「刑事訴追のおそれ」を理由に、決裁文書改ざん等についての実質的な証言はほとんど拒絶しました。
しかし、現時点では、関連する犯罪はすべて公訴時効が完成しており、刑事訴追を受けるおそれはなく、証言拒絶はできません。偽証の制裁の下で真実を証言させることが不可欠です。
もう一つのポイントは、森友学園問題に関連する刑事事件の捜査処分が適切に行われたのか、不適切だったとすれば、いかなる原因によるものなのかを解明することです。
国有地売却に関する背任事件、決裁文書改ざんに関する虚偽公文書作成等の事件では、すべて不起訴処分となり、検察審査会で10人について「不起訴不当」の議決が出ましたが、再捜査の上、再度の不起訴処分が行われました。この時の捜査が果たして適正に行われたのか重大な疑問が生じています。
今回明らかになった「交渉記録の中の政治家関係者に言及する部分の意図的廃棄」は、捜査の対象となっている国有地の売却をめぐる背任罪についての証拠隠滅に加え、公用文書毀棄罪に該当する疑いもあります(検察は、保管期限が「事案終了まで」とされていたことから、公用文書毀棄の対象となる「公用文書」には当たらないことを消極判断の理由としたのかもしれません。しかし、「公用文書」とは、判例上、「その作成者、作成の目的等にかかわりなく、公務所において現に使用し、又は使用に供する日的で保管している文書を総称する」とされています。森友学園疑惑の一連の経過を明らかにするため国会議員から提出を求められていたもので、具体的な使用目的も存在していたのですから、「公用文書」に当たると解するべきでしょう。)。
検察の捜査・処分に関しては、当時の捜査の責任者の山本真千子特捜部長(現札幌高検検事長)と、現在、準強制性交罪で起訴され勾留中の北川健太郎元検事正の証人喚問を行うことが考えられます。
一般的に検察官が国会で喚問されない理由
従来、政界汚職事件等について国会で質問が行われても、法務省当局は、
「個別事件についてはお答えを差し控える。なお、一般論として申し上げれば、すべての刑事事件は法と証拠に基づいて適切に処理されている」
と答弁し、個別事件について、検察庁の関係者の国会での参考人、証人としての喚問を拒絶してきました。
法務省や検察庁がそのような対応を行ってきた根拠は、刑訴法47条の
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
との規定です。この規定を、「公判開廷前」だけでなく「開廷後」にも拡大し、
但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。
との同条但書の規定をほとんど無視し、刑事事件についての国会での答弁をすべて拒絶してきたのです。
そのような条文の文言を超えた対応が行われてきたのは、「刑事事件についての検察当局の資料・情報は、実質的にも秘匿すべし」という考え方が無条件に受け入れられてきたからです。
では、そのように個別の刑事事件に関する情報は秘匿すべきとされるのはなぜでしょうか。その理由として考えられるのは、(1)個別の刑事事件の捜査・公判への影響と、(2)プライバシーの保護です。
しかし、森友学園関連事件については、すべて公訴時効が完成しており、捜査・公判への影響は考えられません。また、問題となっているのは、財務省という官公庁における公文書の取扱に関する公的な事象であり、プライバシーの保護も問題とはなりません。
官僚の世界の無謬にこだわる立場からは、「法に基づいて行われる行政行為に国会議員等が口を出してきても、行政当局は些かも影響を受けない。常に適切な対応が行われる。そこでの国会議員の動きなどに関する資料は、『夾雑物』(きょうざつぶつ:ある物質の中に、不要なものや異物が混入していること)のようなものであり、そのようなものが存在すると、あらぬ疑いを受けたり、国会で野党議員の追及のネタにされたりするだけだから速やかに廃棄すべき」という考え方になるのかもしれません。
しかし、それは、行政行為が、国民の代表である国会の信認を受けた内閣の責任の下に、「国民のために行われている」という原則を蔑ろにするものです。行政行為が公正・公平に行われているのかを国民そして国会が客観的に知る唯一の手掛かりは、行政に対する国会議員、政治家側の働きかけ等を、正確に記録し、公文書として保存することです。とりわけ、「安倍一強」と言われ特定の政治家に権力が集中し、官僚の世界を歪めていた時代であれば、行政行為が政治家から有形無形の影響を受けていた可能性があり、正確な記録保存の必要性は一層大きかったと言えます。
この意味において、森友学園に対する国有地売却に関する政治家の動きについての公文書を、問題表面化後ただちに丸ごと廃棄したという、今回明らかになった財務省の罪はあまりに重く、そのような行為に対して全く刑事罰を適用することができなかった当時の検察の対応にも、重大な疑問があります。
このような公文書の廃棄が行われず、すべて国会に提出され、交渉の経過、政治家の介在の事実が客観的に明らかにされていたら、国会審議の紛糾・混乱が生じることも、それらをおそれた財務省内での決裁文書の改ざんが行われることもありませんでした。
そして、公務員としての使命に忠実だった赤木俊夫さんが、自ら命を絶つこともなかったでしょう。
このようなことは二度と繰り返してはいけません。そのためにも、当時の佐川理財局長の証人喚問は不可欠ですし、当時の山本特捜部長、北川検事正の証人尋問も検討すべきです。
すでに登録済みの方は こちら