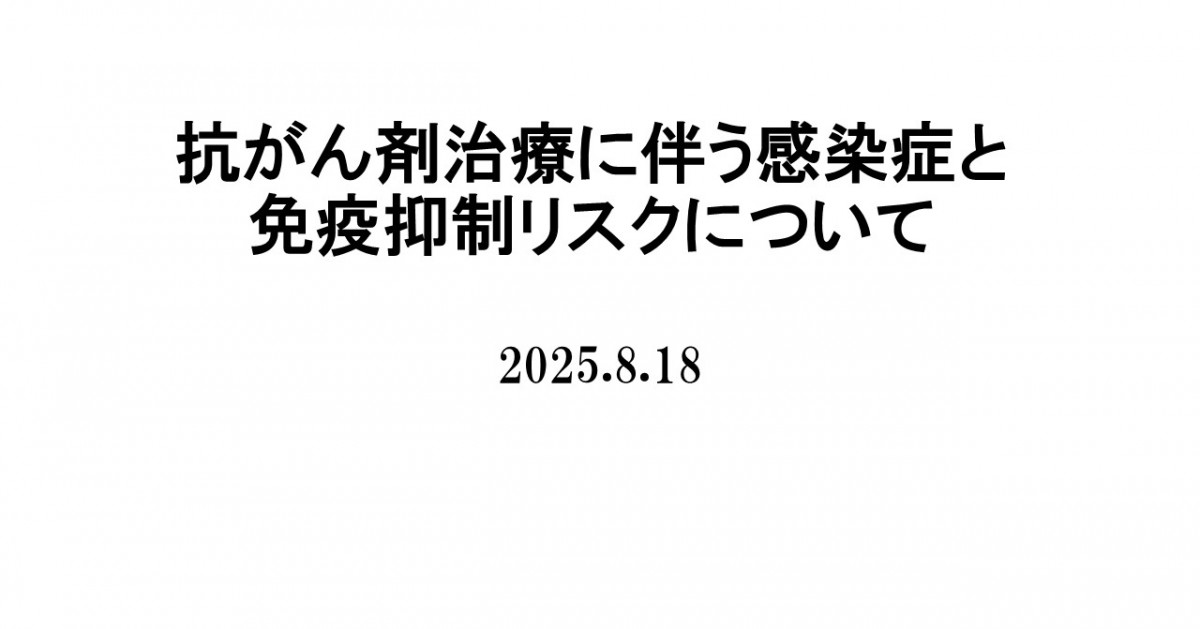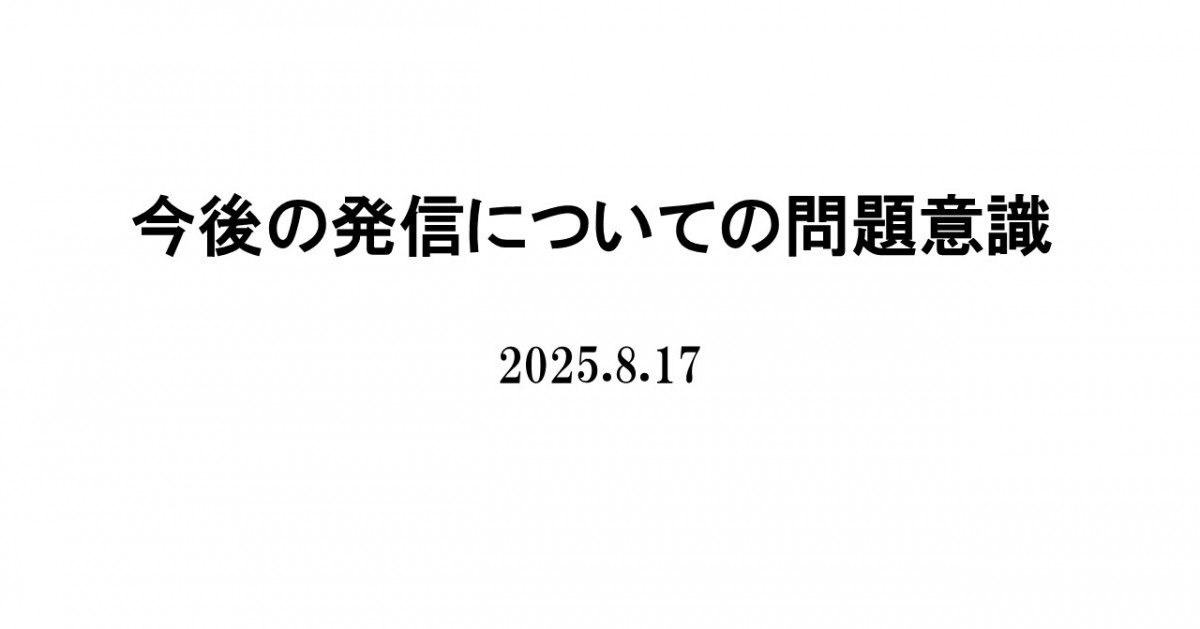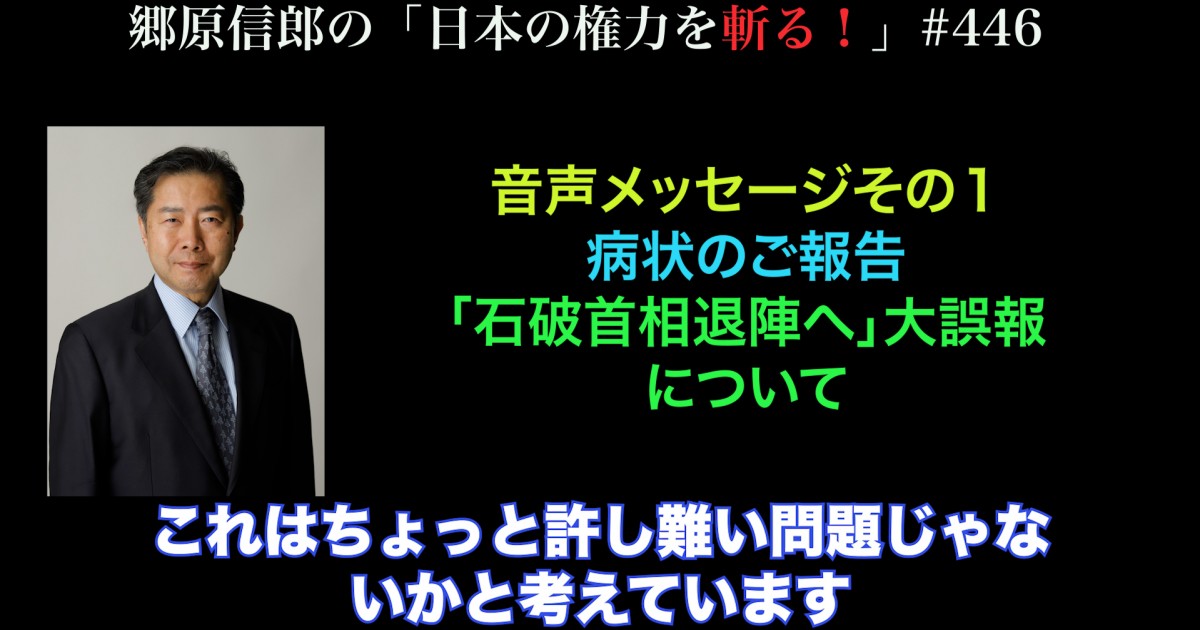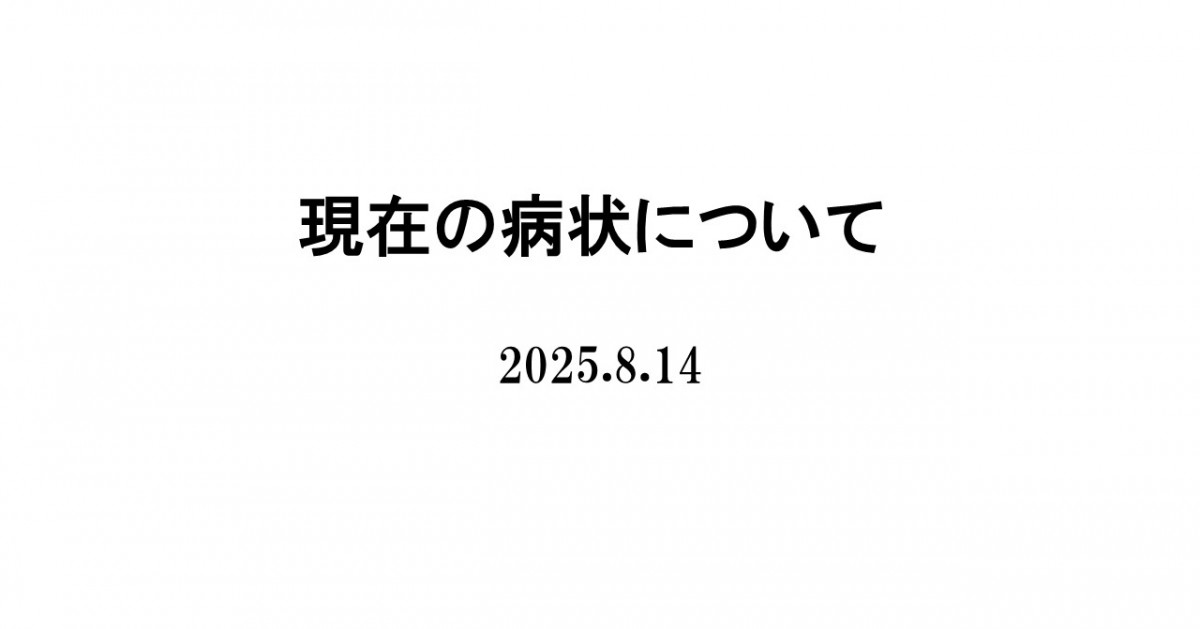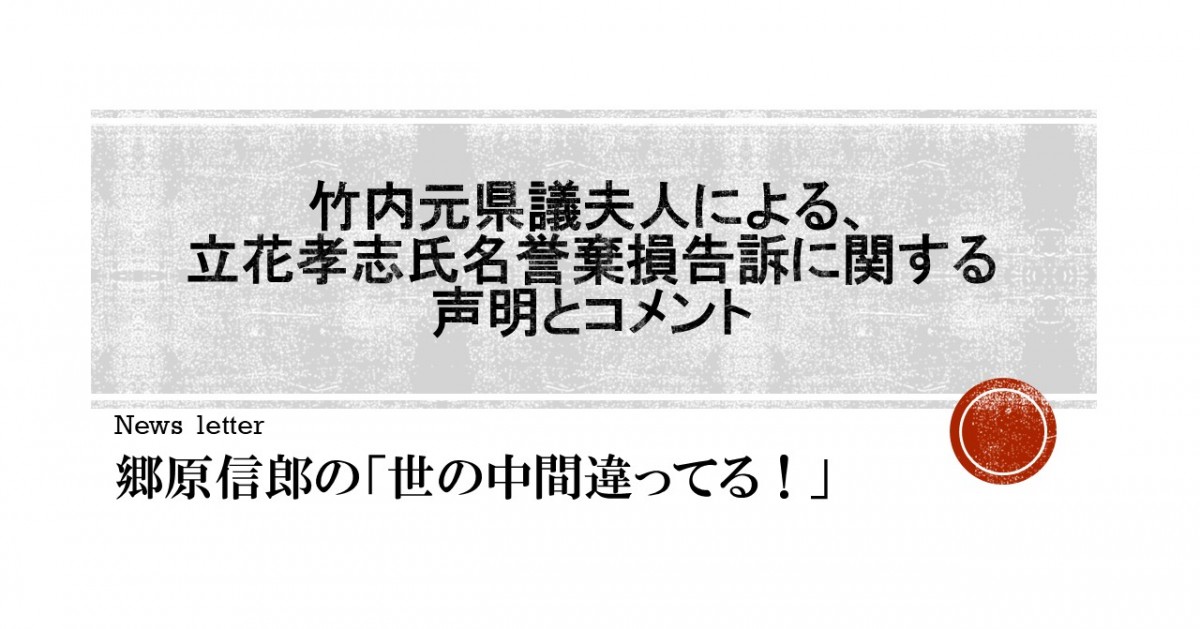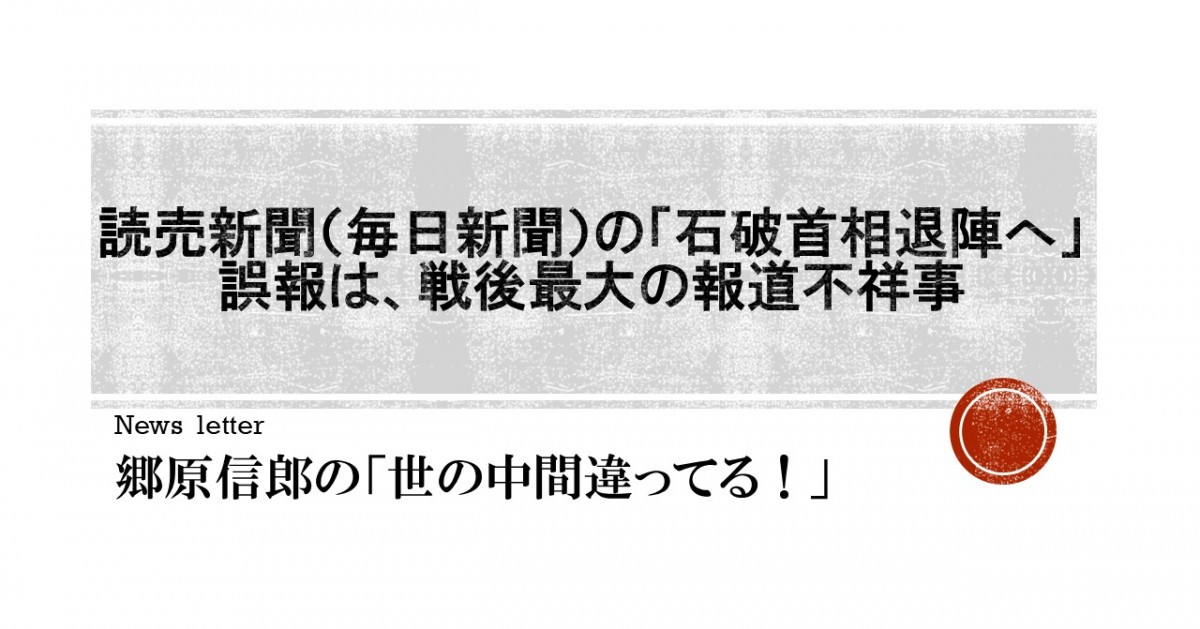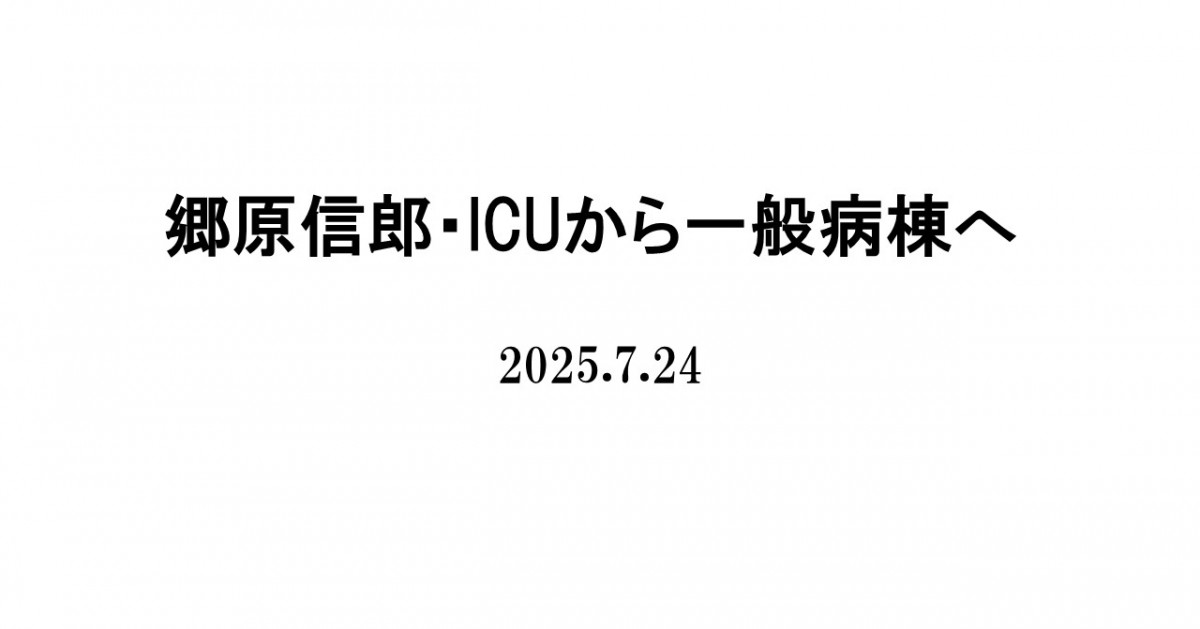「選挙スリーアウト」でチェンジすべきは“裏金議員”、「納税」も「総括」もない「決着」はあり得ない!
直近の病状は、【抗がん剤治療に伴う感染症と免疫抑制リスクについて】で書いたとおり、左手首の動脈瘤が免疫抑制のために未処置なので、右手と音声しか使えない不自由な状況です。
しかし、現在、自民党内で「石破おろし」と言われる石破首相退陣要求の党内抗争について、昨年10月の衆院選、今年6月の都議選、そして、7月の参院選の3つの選挙で、自民党が三連敗した原因と「裏金問題」との関係について、参院選の総括が行われる前の今、どうしても言っておきたいことがあります。
今年4月に公刊した【法が招いた政治不信 裏金・検察不祥事・SNS選挙問題の核心】(KADOKAWA)の中で指摘した「裏金問題の本質」、「自民党の信頼崩壊の原因」を踏まえて、可能な限り書いてみたいと思います。
裏金問題による「自民党の政治権力の崩壊」と「納税問題」
長年にわたって「安定政権」を維持していた自民党の「政治権力の崩壊」が生じたのは、「自民党派閥政治資金パーティー裏金問題」が原因でした。パーティー券売上の一部が、所属議員に、政治資金収支報告書に記載不要の「裏金」として還流し、確認できる5年間でも数億円に上ることが明らかになりました。その裏金問題に対する国民の強烈な不満反発の原因になったのが、「課税に対する不公平感」でした。
国会議員は、政治資金パーティーの売上の中から自由に使っていい「裏金」を受け取り、それについて税金の支払も免れていることに対して、国民は激しく怒りました。国民は、事業者もサラリーマンも、汗水流して働いたお金を報酬・給与として得ます。その際、法人の事業を行って得たお金であれば「法人税」等を、個人の収入として得たお金であれば「所得税」等を支払わなければいけません。その上で、残ったお金を自由に使うことができます。
裏金事件が注目を集め、検察の捜査、刑事処分が決着した時期は、個人事業主などは、払いたくもない税金を納めるために、確定申告に向けて気の滅入るような作業を強いられている時でした。しかも、2023年10月にインボイス制度が導入され、「会計処理の透明化」の動きが中小企業や個人事業主にも及び、多くの国民が負担を強いられていました。
それなのに、政治家の世界では、自由に使えて税金もかからない「裏金」という、「領収書不要の金のやり取り」が行われていたことがわかり、派閥は大規模な政治資金パーティーで巨額の収入を得て、その一部を裏金で所属議員に分配し、彼らは税金も支払わず自由に使っている。そのことに対して国民は怒りを爆発させたのです。
ところが、この「裏金問題」について、殆どの議員が処罰も受けず、問題の中身も、責任の所在も、問題解消のための方策も、全く明らかになっていません。
このような「裏金議員の納税問題」は、国会でも野党から追及を受けました。当時の岸田文雄首相は、国会で「裏金議員は所得税を納税すべきではないか」と追及される度に、
「検察捜査の結果を踏まえて、適切に判断されるべき」
との答弁を繰り返しました。そして、実際に、検察は、「政治資金収支報告書に記載不要の金」として、議員側が受領していた「ノルマ超の売上」の還流金を、「資金管理団体又は議員が代表を務める政党支部の収支報告書に記載すべきだった政治資金」であったことにして、その旨の収支報告書の訂正を行わせ、最初から「政治資金」だったことにしてしまい、議員は、所得税の納税を全く行っていません。
しかし、世の中では、通常、表に出せない「裏金」を受領していたことがバレた時に、税務署がそのような「大甘な対応」をしてくれることはあり得ません。
「適法な政治資金」は、いずれかの団体の政治資金収支報告書に記載することで初めて、税務上の「政治資金」として取扱ってもらえるのです。受け取ったお金を収支報告書に記載しないまま受領して保管したり、領収書もとらずに使っておいて、 何年も経ってから収支報告書を訂正して「政治団体に帰属する政治資金だった」などと言い訳しても 政治資金と認めてもらえることはありえません。一般人であれば、隠していた金がみつかり、「人から預かっていたお金です。私の金ではありません」と言っても、「預かり証」でもなければ、個人所得として課税されるのが当たり前です。
検察の捜査の中で政治資金収支報告書を訂正したとしても、それは政治資金規正法上の問題であって、収支報告書を訂正して「政治資金だったことにした」からといって、遡って所得税を払わなくてよくなる訳ではないのです。
このままでは、国民が、裏金議員の納税の問題に対して納得できるわけがないし、裏金議員に対する反発不満が解消されるはずがないのです。
昨年の衆院選で、自民公明与党が少数与党に転落することになった最大の原因が、「裏金問題」であったことは明らかです。
都議選惨敗の原因も都議会自民党の「裏金問題」
それに加え、今年6月の都議選での惨敗も、都議会自民党の裏金の問題が最大の原因です。
私は、今年4月9日、東京都議会政治倫理条例検討委員会に最初の参考人として招致され、都議会自民党の裏金の問題について意見を述べました。以下は、その要約です。
個人のところに入ってきたお金であれば所得税が発生します。雑所得になるはずです。ですから、検察の指導に従って政治資金収支報告書を訂正して、政治団体に帰属したということにしなければ、原則個人の雑所得になって、何か例外的に経費が認められるということでない限り、全部税金をきっちり納めてもらうということになったはずです。ところが、残念ながら、そういう方向での処理は行われませんでした。そして、この裏金議員といわれた人たちの中で、税金を払った人はほとんどというか、全く聞いたことがありません。
こういったことが国会議員レベルで起きて、そして世の中が、処罰もされない、税金も払わない、こんなことで許せるかという思いが強烈な批判不満につながって、昨年の衆議院選では、選挙の結果にも大きな影響を与えることになり、その直後に、その問題が都議会に飛び火したというのが今回の都議会自民党の政治資金パーティーをめぐる、いわゆる裏金問題ということだと思います。
政治資金パーティー券をノルマを超えて販売した議員のところには、そのノルマを超えた分がキックバックされるとか、あるいはその分がパーティーの主催者の方に納入されないで議員側にとどまっている、いわゆる中抜きという形で議員側に帰属している。この構図も恐らく国会議員の政治資金パーティーとほぼ同じだろうと思います。
この問題について、何を突き詰めていかないといけないかというと、本当はこのお金はどこに入ったのか、どこに帰属すべきお金かということを明らかにすること。何より重要なことは、そこだと思います。
国会議員の派閥政治資金パーティーの問題に関しては、そこが十分に突き詰められることなく、全て政治団体とか政党支部に帰属したもののように扱われました。
国会議員の場合は、議員会館というのがあって、そこにも事務所があります。公設秘書が政策秘書も含めて三人もいる。それ以外にもいろいろ秘書もいて、それなりの事務所の体制も整っているわけですから、その事務所で政治資金として管理しているというような説明も一応可能だと思います。
しかし、総体的には事務所の体制が国会議員ほど整っていない地方議員の場合、個人に、そのままノルマを超えたパーティー券の収入が入ってきている、あるいはとどまっているというケースが多いのではないか。とすると、いわゆる裏金というのが個人に帰属している割合は、国会議員の場合よりも、むしろ都議会議員の政治資金パーティー問題の方が一層問題なんではないかと私は思っております。
そのように考えますと、まず今回の問題、国会議員の事件で、残念ながらきちんとした解決が図られなかった国民の不満が、非常に大きな形で残ってしまった。裏金議員に対して、都議会議員の方々は、納税の問題だけは、しっかり事実関係に基づいて適正な処理を行うことが、まずは重要なんじゃないかという気がいたします。
この参考人陳述で私が特に言いたかったのは、国会議員の裏金問題についても、結局、検察の示唆で資金管理団体や政党支部の政治資金収支報告書の記載の訂正という形で済ませてしまって、裏金が遡って政治資金であったような処理をして所得税の納税すらしていないことで、国民の反発不満が生じているんですが、都議会自民党の場合はもっとひどい。そもそも、その議員活動や事務所の実態などからして、都議会議員の場合、パーティー券の売上を中抜きしたお金は個人に帰属している場合が多い。そうであれば所得税を払うのは当たり前だということです。
それだけに、私は、都議会の参考人としてもその点を強調し、非公式に相談を受けた都議会自民党幹部にも、「信頼回復のためには納税をしっかり行うべき」と指摘しました。しかし、自民党の都議は誰ひとり、所得税の納税をしませんでした。
そこには、今さら都議が裏金の所得税を払ったりしたら、それが国会議員の裏金議員に逆流しかねない、検察の意向に反することになる、自民党本部側の懸念があったのかもしれません。
しかし、いずれにしても、それによって都議会自民党は完全に都民の信頼を失ったと言わざるを得ません。都議選で自民党が歴史的惨敗を喫したのも、まさしく裏金問題が原因です。
参院選の敗因と「納税に対する抵抗感・不満反発」
そして、今年7月の参院選です。
この選挙結果は、消費税廃止、消費税減税という国民の声が圧倒的に大きく、消費税減税に消極的な自民党・公明党・立憲民主党は支持されませんでした。
「給付」か「減税」について、圧倒的に「減税」が勝った。端的に言えば、そういう結果です。
その大きな原因となったのが、「裏金問題」だと思います。そこには、納税の負担が大きいこと、そして、徴税を行う税務当局が国会議員の「裏金」に対してあまりに寛容であることへの国民の不満・不信感があり、それが「納税することへの抵抗感」につながっていると見るべきだと思います。
国民は、給与所得者は所得税を源泉徴収され、買い物のたびに消費税をきっちり払わされる。中小企業も、消費税を厳しく取り立てられ、インボイスで苦しめられる。ところが、自民党の国会議員は、裏金を手にして、それがばれても、政治資金収支報告書を訂正して、所得税も免れる。そのような不公平に対する国民の怒り・不満が、根強く残っている状況では、減税に消極的な自民党・公明党などが、消費税減税を訴える国民民主党・参政党などに惨敗するのも、当然の結果です。
昨年秋の衆院選以来の選挙での自民党の三連敗は、間違いなく、「裏金問題」による“スリーアウト”であり、それによって「チェンジ」となるべきは、「裏金問題」にケジメをつけることができず、所得税の納税すら全くしていない「裏金議員」なのです。
「石破おろし」の中心となる「旧安倍派議員」と高市早苗氏
今、「石破おろし」の中心になっていると言われる旧安倍派国会議員の多くが総裁に担ごうとしているのが、高市早苗氏のようです。
高市早苗氏は、昨年9月の自民党総裁選の出馬会見で、裏金議員への対応について問われ、
「自民党で処分が決まっている。8段階の処分の中には『非公認』もある。非公認より厳しい処分が5名に下されている。非公認を含めて党内で積み重ねてきた議論を総裁が代わったからと言って“ちゃぶ台返し”をしたら『独裁』だ」
と、自分が新総裁に就任した場合、裏金議員への公認等の見直しについて検討する考えはないと述べました。
しかし、自民党の党紀委員会で決定された処分に対して、国民は全く納得していません。それに対して、国民から強い反発・批判が生じているからこそ、岸田内閣の支持率が低迷し、「現職首相の総裁選不出馬」という結果につながったのです。岸田総裁の下の自民党内で行われたことを、すべて「是」として見直さない、という対応は、自民党内では通用しても、国民には全く理解されません。
自民党の党紀委員会の処分では、裏金議員の側は、すべて「政治資金として保管・使用し、議員個人が懐に入れていた金はない」と説明し、自民党の側も、その弁解を丸呑みして、「裏金はすべて政治資金」との前提で、「不記載は、すべて会計責任者が行ったこと」で、議員本人は、「会計責任者に任せきりで不適正な処理としてしまった者の管理責任」だけが問題にされました。
しかし、その「前提」が完全に間違っています。裏金議員に対する自民党の従来の対応が国民から厳しい批判を受けているのは、自民党の多くの議員が、収支報告書で公開もしない「裏金」を得ていたことが発覚したのに、刑事処罰を受けないどころか、納税すらしないで済まされていることに対する、納税者としての強い不満・反発によるものです。
高市氏が、そのような国民の不満・反発を無視し、「ちゃぶ台返し」などという理屈を持ち出してまで、裏金議員の公認を維持しようとしたのは、総裁選で決選投票に残った場合に、「裏金議員からの圧倒的な支持を受けたい」との思惑があったからとしか思えません。
「石破降ろし」の中心になっている旧安倍派の裏金議員たちは、おそらく「昨年9月の自民党総裁選」まで時計の針を戻し、そこで、石破氏ではなく、高市氏が総裁に選ばれていたら、という思いが頭から離れないのでしょう。
もし、高市氏が決戦投票で勝利し、総裁に就任していたとしたら、「ちゃぶ台返しはしない」という旗を掲げて、裏金問題を一切不問にし、衆院選・都議選・参院選を「タカ派」路線で強引に乗り切ろうとしていたことでしょう。
そういう裏金隠し、裏金議員擁護路線の高市総裁で突っ走っていたら、自民党は、参政党に流れる票の一部は防げても、多くの国民は自民党を見放し、参院選での敗北はさらに大きなものになっていたはずです。
「裏金問題」は、長年にわたって自民党組織に深く根差してきた「政治資金の不透明性」という「自民党の本質」そのものだという認識が全く欠落してるのです。
このような 裏金議員を中心 とする「石破おろし」の動きが、総裁選の前倒しに向けての動きにつながっていることに対して、多くの国民が冷ややかな目で見ていて、世論調査で石破首相続投を望む国民が多数に登っているのは、自民党が三連敗した選挙の経過からも、その背景にある裏金問題、とりわけ「裏金議員の納税」に対する批判不満からは「当然の反応」です。
そのことを全く意に介さず、このような状況にあるのに、「裏金議員」が中心となって、「自民党の再生のためには体制の刷新が必要だ」などと言って「石破おろし」を画策し、総裁選の前倒しを議論していることに対しては、呆れ果てたという他ありません。
萩生田議員秘書の略式起訴
ちょうどこのタイミングで、「裏金議員」の代表格のように見られてきた萩生田光一衆院議員の政策秘書が、検察審査会が「起訴を見送り続ければ、いつまでたっても虚偽記載はなくならない」という理由で「起訴相当議決」を行ったことを受け、政治資金規正法違反(政治資金収支報告書虚偽記入)で検察に略式起訴されました。
不記載額は、約1900万円です。
要するに、3回の選挙の敗因となった裏金問題は、世の中にも、国民にも全く納得が得られていないということが、今回の検察審査会の議決にも現れたということなのです。
検察はこれまで、3000万円を基準として、それ以下の金額の不記載については、刑事立件しないか、立件しても起訴猶予としてきました。しかし今回、検察審査会で1900万円の不記載が「起訴相当」とされ、略式起訴したことで、今後、同程度の金額の事案があった場合は起訴せざるを得なくなります。
さらに、今後、検査審査会が、1500万円であっても1000万円であっても起訴相当と議決するかもしれません。今回の検察審査会の起訴相当議決によって、裏金議員の少なくとも秘書などの処罰は 全面的に見直すことになり、処罰の範囲が大きく拡がる可能性があります。
自民党と裏金議員が行うべきこと
つまり、自民党にとって、「裏金問題」は、刑事事件としても、まだ、今後の展開が続くことは必至で、国民の間に生じた「裏金議員が納税を免れていること」への不満・反発も大きく、決着がついているなどとは全く言えない状況なのです。
裏金問題は「政治資金の不透明性」という自民党の構造問題に起因する問題です。それがいったいどういう問題であったのかを総括すること、国民が当然だと思っている「バレてしまった裏金の納税」を行うことが、自民党の再生のためには、まず、必要です。
これまで書いてきたことは、当然のことで、裏金問題について国民の多くが思っていることです。最新の世論調査で 石破内閣の支持率が上昇傾向にあり、国民の多くが 自民党内の 「石破おろし」 に否定的な見方をしているのも、3つの選挙で自民党が敗北した原因が裏金問題に象徴される「政治資金の不透明性」などの「組織の体質」にあり、むしろ、国民はこの状況を乗り越えて自民党の組織の体質を抜本的に改革することを石破首相に期待していると見るべきです。ところが「石破おろし」「総裁選前倒し」に血道を上げている自民党議員の人たちには、国民の反応を敢えて見ないようにしているようです。
私はこれまで与党として政治権力をであった自民党を様々な問題で批判してきました。
しかし、やはり、健全な保守政党としての自民党の存在は、日本の政治に必要だと思います。
政権発足後の1年間は盤固めの期間。党内基盤が薄弱な石破首相にとって、石破カラーを出し、「政治とカネ」問題も含めて思い切った対応を行うとすれば、これからが本番です。
すでに登録済みの方は こちら