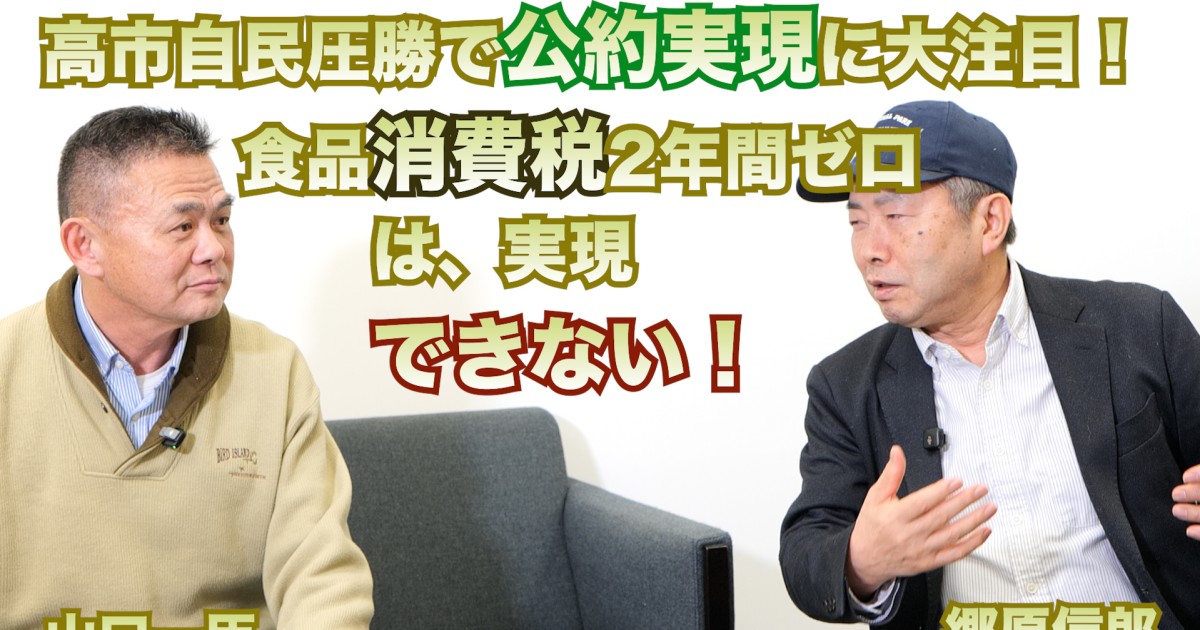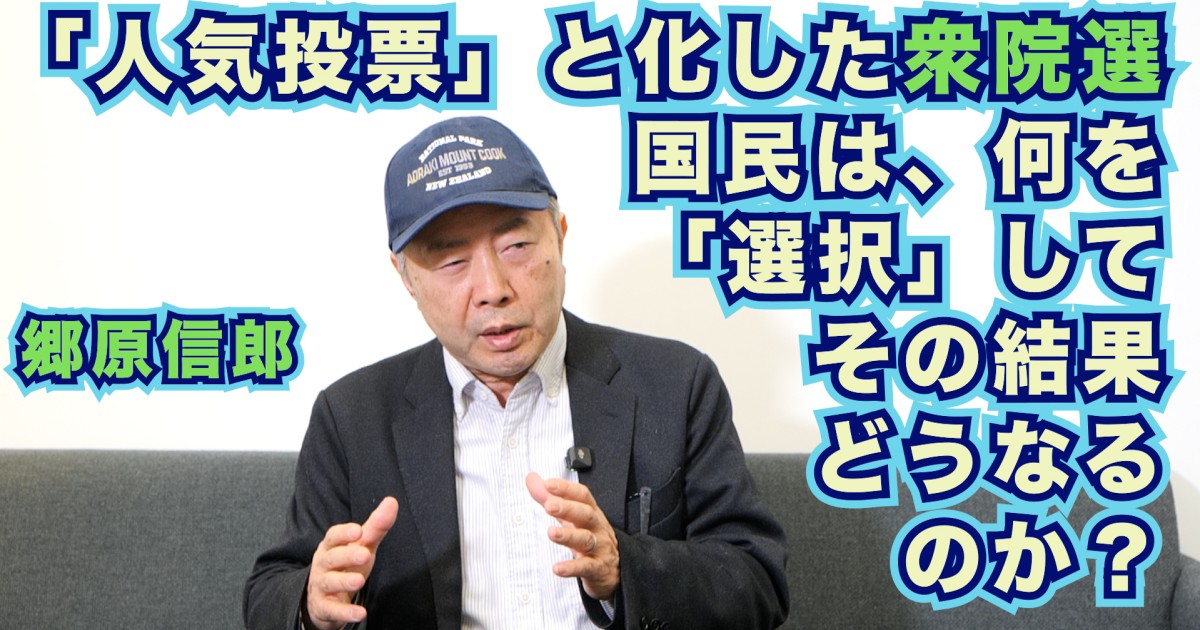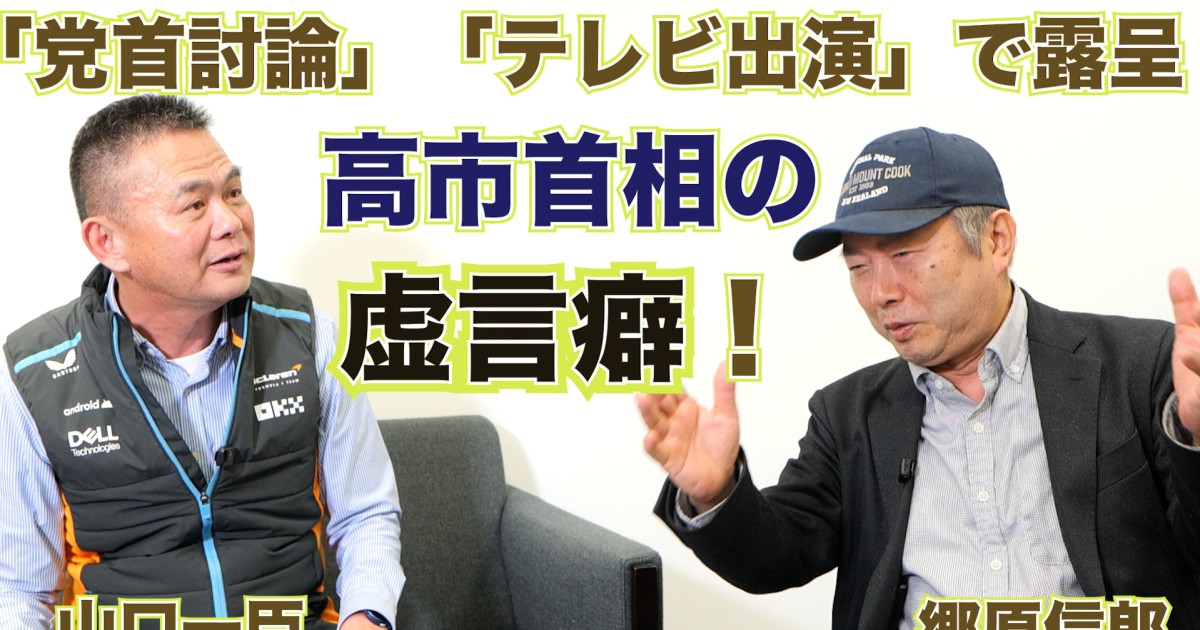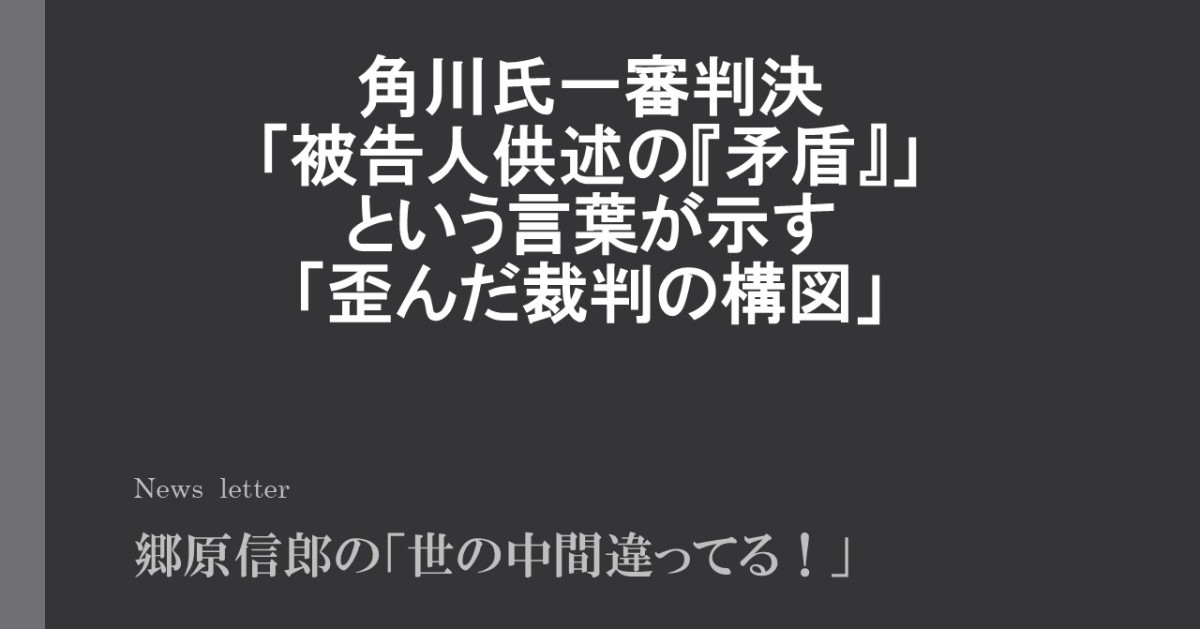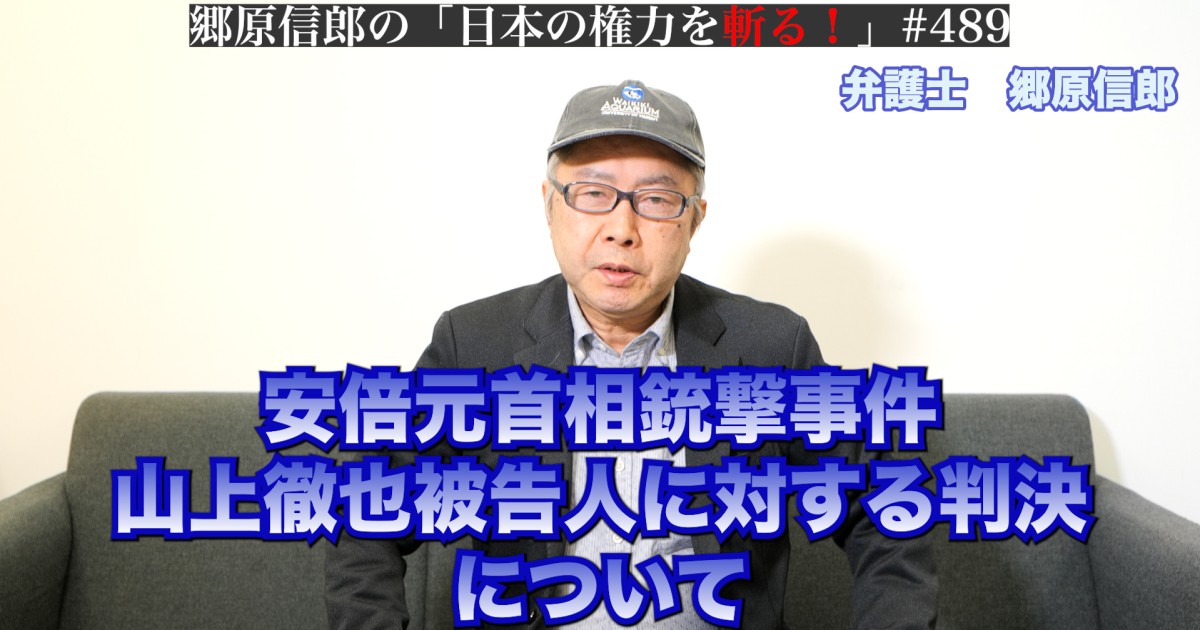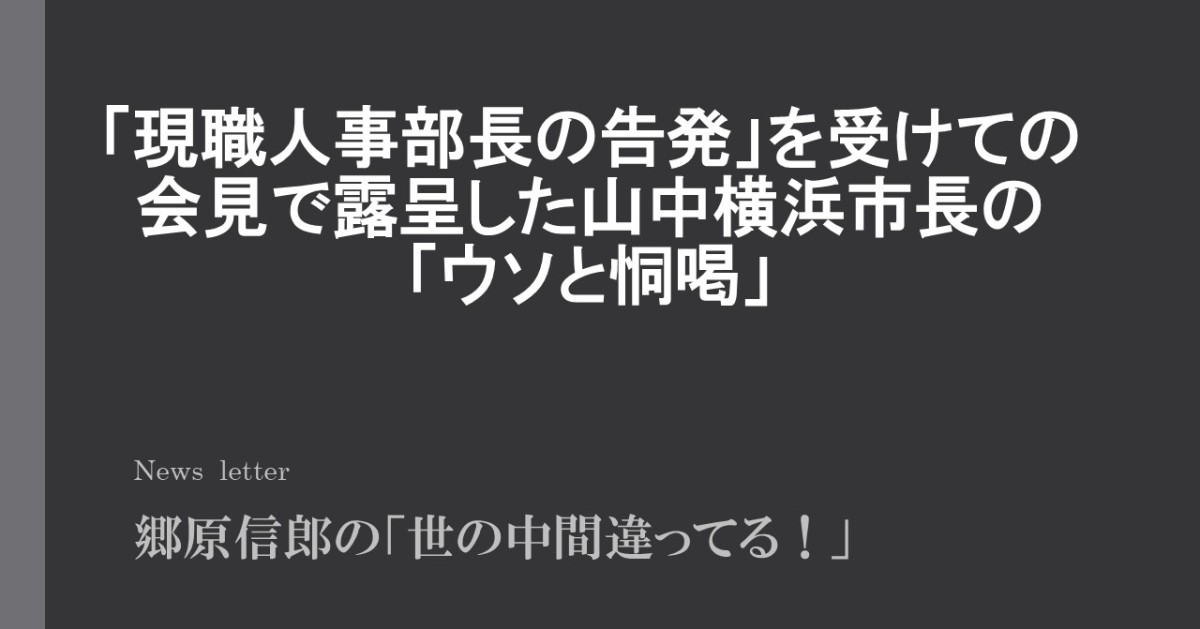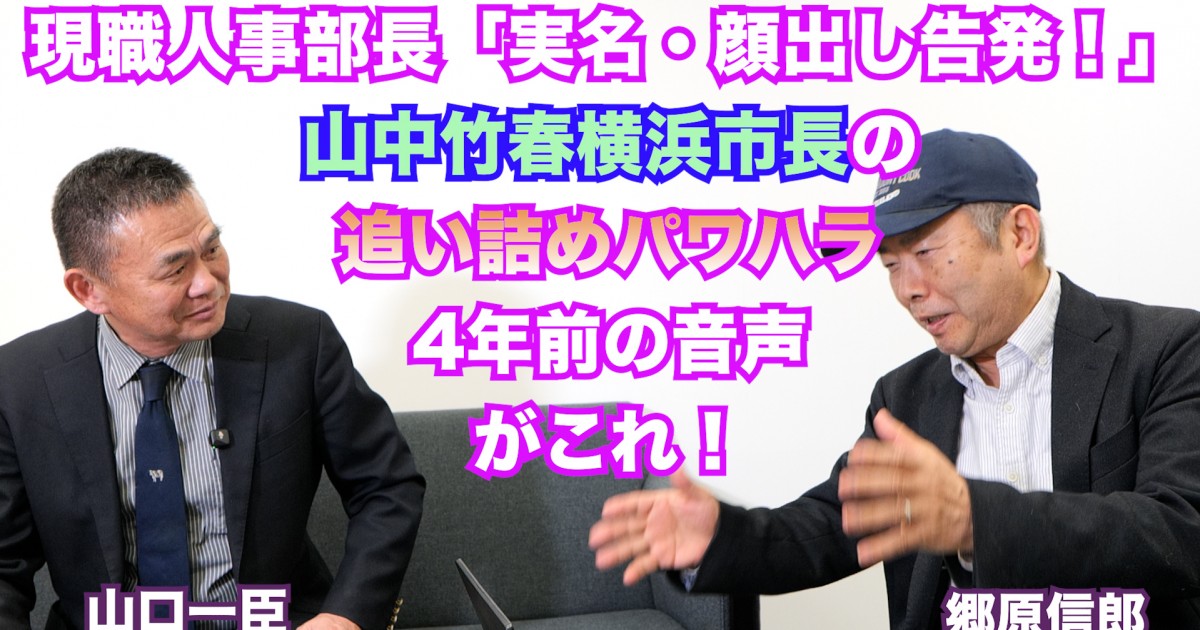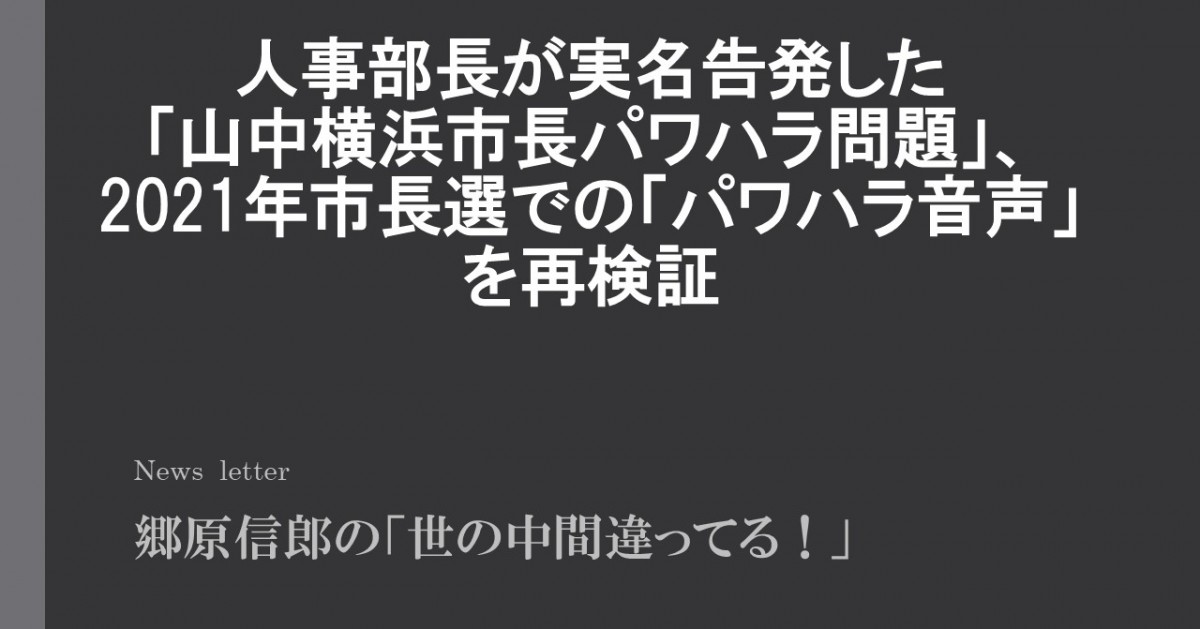抗がん剤治療に伴う感染症と免疫抑制リスクについて
これまでのレターで、私にとっては「権力との戦い」に関わっていくことが、気力、体力を維持する「薬」でもあるので、先の見えない闘病の中で、その時々の病状、体調に応じて、可能な範囲で、私自身のこれまでの戦いの延長として、どうしても世の中に言っておきたいことの発信は行っていきたいと考えているとお伝えしました。
しかし、悪性リンパ腫の抗がん剤治療に加えて、その過程で生じた左手首の感染症による血管の損傷が深刻化し、抗がん剤の副作用としての免疫抑制の下での左手首の手術が必要となり、難しい判断を迫られる状況になっています。
高度な医療を受ける中で、予期せぬ合併症としての感染症への対応を、抗がん剤による免疫抑制の中で行うという事態は、がん患者一般にとってもあり得ることだと思いますし、その予防と対策は、医療関係者にとっても重要な問題だと思います。
私自身の症例を参考に供したいと思います。
今回、悪性リンパ腫の急激な悪化でICUに緊急入院となった後、体に繋がれたいくつかの管の中に、左手首の動脈にカテーテルを挿入し循環動態を24時間把握する措置がとられていました。9日後、ICUから一般病床に移る際にカテーテルを取り外したのですが、その前後で、挿入部位からの黄色ブドウ球菌による感染が発生し、血管を通じて菌が全身に及ぶ恐れがあるということで、抗菌剤の点滴を1日3回受ける治療が始まりました。
幸い全身への感染は抑えられたものの、左手首の感染症はなかなか回復せず、腫れが続き、2週間後に血管エコーを取ったところ、血管の剥離に加えて動脈瘤が生じており、それが破裂すると、左手全体に出血が及び危険な状態になるということで、緊急に動脈を切断し他の部位の静脈を用いて動脈接合する手術が必要と言われています。
一方で、抗がん剤治療の方は、第2クールの治療を開始する時期に入り、感染症との関係で様子を見ていましたが、5日前に第2クールの投与を受けました。その後に血管の状態が変化して手術の必要が生じたため、ちょうど左手の手術の予定が、免疫抑制の最高点になってしまいました。
第1クールでは、白血球が800(一般的には3,100~8,400個/μL)にまで落ち込んだ時期に当たることから、このような状況で動脈を切開する手術が果たして可能なのか、その手術を遅らせた場合の動脈瘤の破裂のリスクの評価との関係で難しい判断になっています。
大変設備の整った大学病院で、万全の医療体制のもと、主治医の血液内科の他、感染症科、皮膚科、心臓血管外科など多くの専門のドクターに関わってもらっているものの、稀有な合併症への対応は専門の狭間となりやすく、適宜適切な対応を行うのはなかなか容易なことではないようです。
病気に罹患したことがわかれば、まずは、その全治をめざして可能な限りの治療を受けることになります。その病気が癌など重篤なものであれば、抗がん剤治療等による副作用も大きく、それが身体に様々なダメージを与え、リスクを生じさせる。そこでの医療、患者としての対応は、そのようなリスク全体を克服できるものでなければならない、ということを、この年まで病気一つしたことがなかった私は、初めて思い知らされました。
ということで、抗がん剤の副作用による手先の痺れの中でも、ある程度自分でキーボード入力をすることもできていたのですが、左手首の動脈瘤の影響で、また右手だけしか使えない状況になってしまいました。
もっとも、今まで全く気付いていなかったのですが、スマホに「Google音声入力」の機能が装備されていることがわかったので、音声で入力したショートメールをパソコンのメールアドレスに送って文章化することができました。
昨日送信したニュースレター【今後の発信についての問題意識】は、今後発信する内容を整理するために、そのような方法で作成したものです。
そこでも書いたように、「政治資金パーティー裏金問題」は、検事時代の捜査の中でも 特に力を入れて取り組んできた問題であり、自民党派閥について問題が表面化した当初から、検察捜査についても様々な観点から問題を指摘し、発信してきました。今年公刊した【法が招いた政治不信】 でも詳しく書きました。
その私が、昨年秋の衆院選以降の選挙における自民党敗北の原因としての裏金問題と、今の自民党の党内抗争についてどのように考えているかということを、是非皆さんにお伝えしたい。
そして、今なお深刻な分断対立が続く兵庫県の斎藤知事を巡る問題、近く検察の処分が行われるとみられる公選法違反の問題について、皆さんに正しく理解して頂けるよう、しっかり書いておきたいと思います。
そのためにも、当面の治療の厳しい状況を、何とか乗り越えていきたいと思います。
すでに登録済みの方は こちら