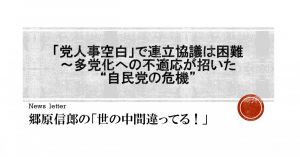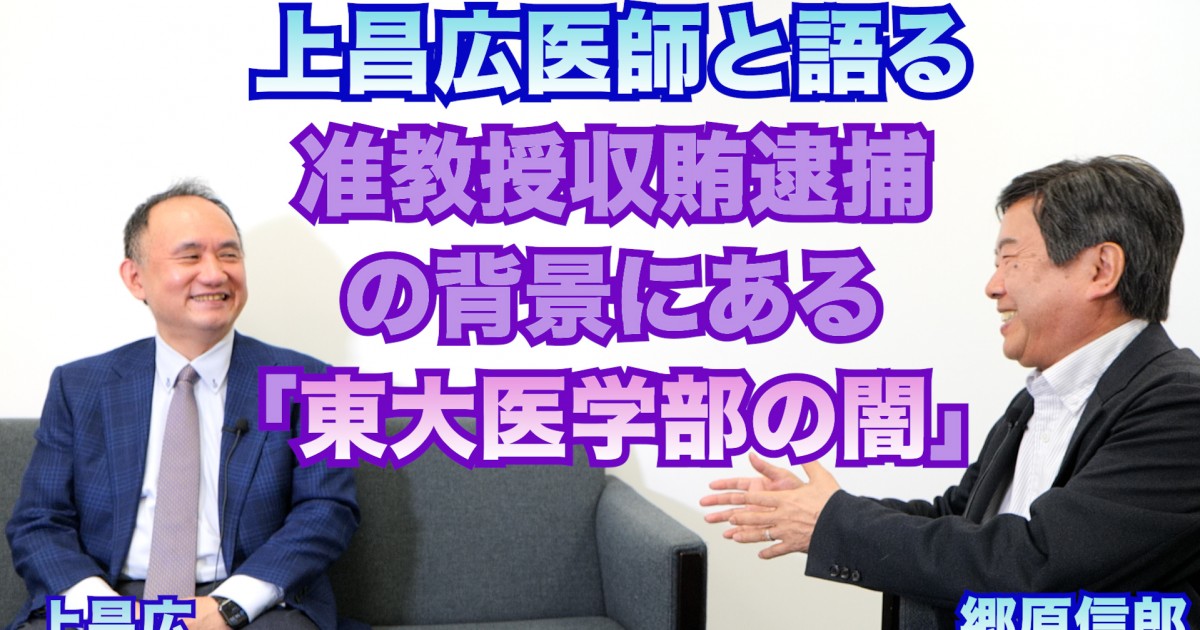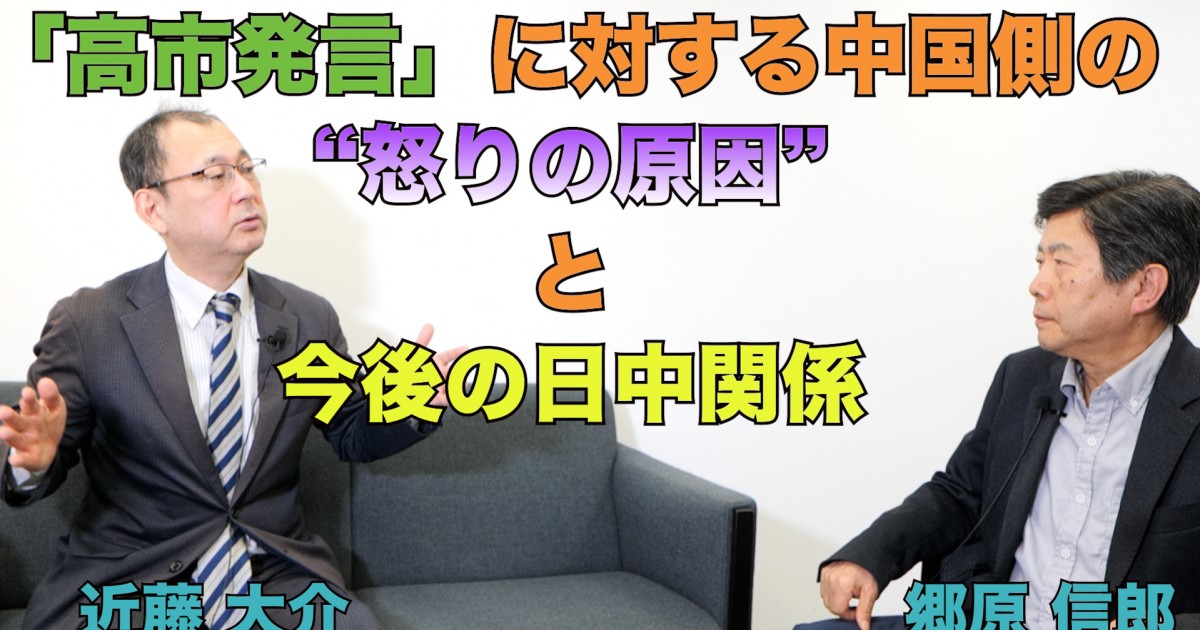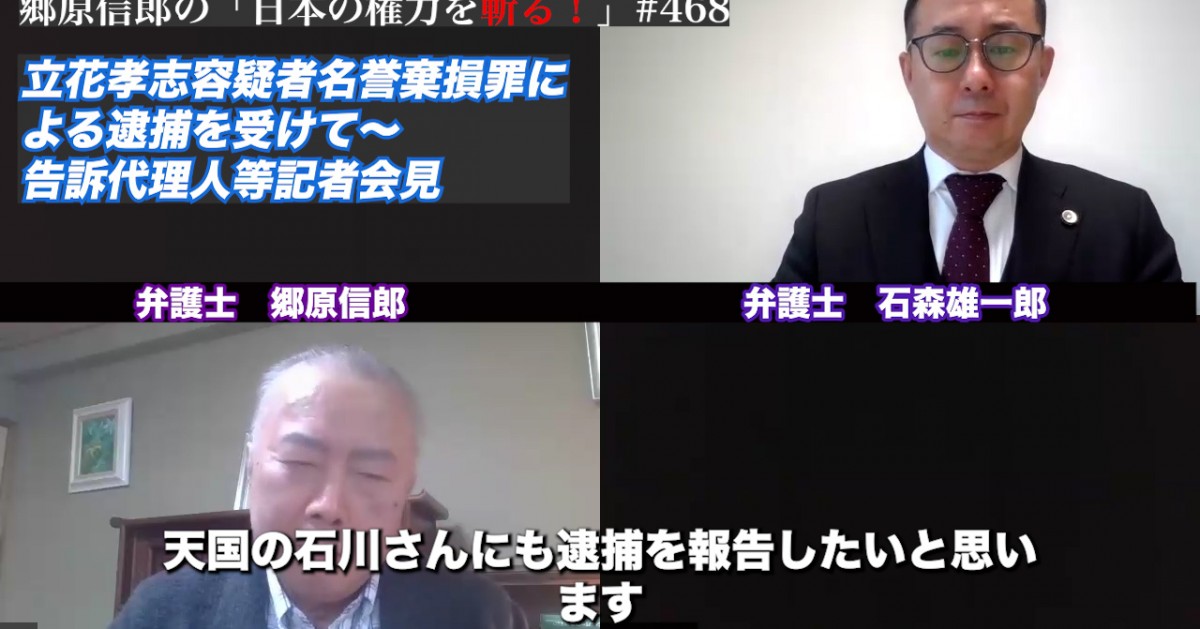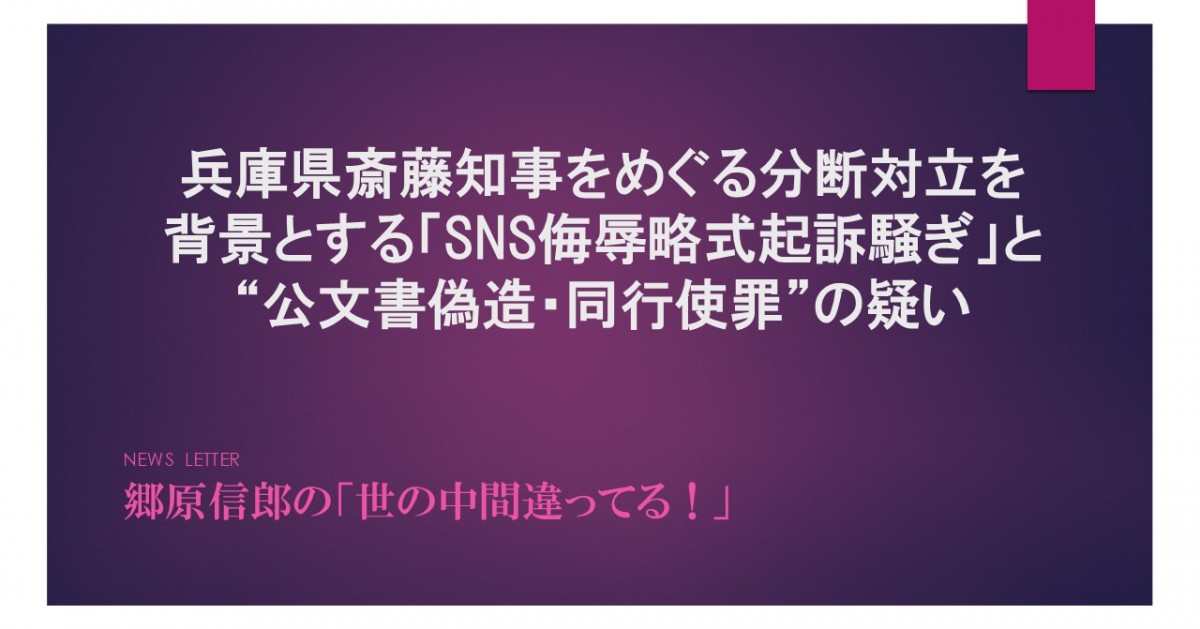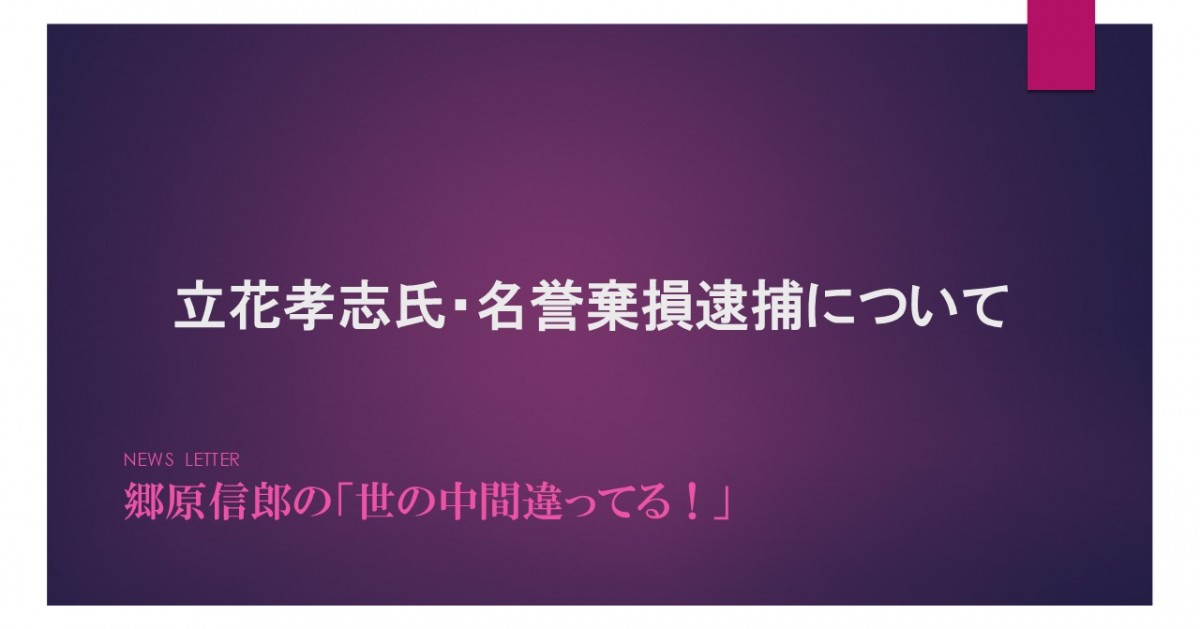維新の“目くらまし”の「議員定数削減」に隠された「民主主義への重大な脅威」に最大の警戒を!
2025年10月10日、自民党との連立協議で、公明党は連立離脱を表明、26年にわたって続いた自公の連立関係が終了することとなり、衆議院の議席数196と、過半数を37議席も下回っている自民党は、政権の枠組みすら見通せない事態となりました。
ところが15日の高市早苗総裁と吉村洋文代表との党首会談で、自民党と日本維新の会(以下、「維新」)が連立に向けて政策協議を行うことが合意され、翌16日から開始されました。16日午前には維新の両院議員総会が開かれ、自民党との協議について藤田文武共同代表に一任されました。16日、17日と連日政策協議が行われた後、
「大幅に前進した。最終的な詰めの段階」
などと説明、藤田氏は、15日の立憲、国民、維新の3党の党首会談で始まっていた総理指名選挙に向けた野党連携の協議からの離脱を表明しました。これにより、臨時国会冒頭の首班指名での高市首相指名は事実上確実になりました。
連立協議開始当初、維新が、「連立合意の絶対条件」だとしていたのが「社会保障改革」と「副首都構想」でした。吉村代表は、それに加えて「議員定数改革を来る臨時国会で行うことの確約がなければ連立はない」と言い出し、その後のテレビ出演でも繰り返すなどして、「議員定数1割削減」も絶対条件に掲げました。
「企業団体献金の受け皿規制」という維新・自民の連立合意の障害
こうして維新と自民との連立に向けて政策協議が始まりましたが、そこで最大の問題となることが予想されたのが企業団体献金の問題でした。結党時から「身を切る改革」のコアとして企業団体献金に対して最も厳しい政策を掲げてきたのが維新です。
高市総裁選任後の連立協議で、公明党は、「企業団体献金の受け皿を政党本部、都道府県連に限定し、政党支部への献金を禁止する規制」の受入れを強く求め、高市氏がそれに応じる姿勢を見せなかったことから、26年間にわたって続いた自民党との連立離脱を通告しました。
その後、公明党、国民民主党に立憲民主党が加わり、維新に対して、この「企業団体献金の受け皿規制」の政治資金規正法改正案を国会提出し成立させる提案が行われました。「企業団体献金の全面廃止」を掲げてきた維新も、「全面廃止」よりハードルが低い「受け皿規制」に反対する理由はなく、藤田共同代表も法案には賛成する姿勢を見せていました。
既に野党間の協力で法案成立の可能性が高まっている「企業団体献金の受け皿規制」を自民党に求めないことは、それまでの維新の企業団体献金への厳しい姿勢からすればありえないことでした。
しかし、高市自民党が公明党との連立協議で受け入れなかった「受け皿規制」を、その直後の維新との連立協議で受け入れるとは考えにくいことでした。この点をうやむやにしたまま自民党と連立合意を行えば、維新の要求より低いレベルの政治資金制度改革をもぶち壊してしまうことになります。他の野党から猛烈な批判を受けるだけでなく、マスコミからも世の中からも厳しい批判を受けることになり、それは、改革政党としての維新への信頼性そのものが崩壊してしまうほどのダメージにつながりかねませんでした。
そのような状況で、突然、維新の吉村代表が「絶対条件」として持ち出してきたのが、「議員定数削減」であり、次の臨時国会のうちに法案を成立させることの確約まで自民党に求めるという「厳しい姿勢」を示しました。
それは、あたかも、維新が自民党に「受け入れが容易ではない要求」を行って「筋を通そうとする姿勢」であるかのように見えました。
「議員定数削減」などを連立合意の絶対条件に掲げることの矛盾と困難性
しかし、「議員定数削減」を持ち出した維新の吉村代表の姿勢には、もともと大きな矛盾がある上、現実的にも、自民党に対してそのような要求を押し通すことは困難でした。
第1に、維新が大阪の地域政党として出発した時点で「身を切る改革」を掲げて議員定数削減を最初に実行し、組織改革や補助金削減などによる財政再建に成功したとしても、それは地方自治体のことであり、それがただちに国政レベルで実行できるわけではありません。
国会の議員定数削減は、その国の民主主義のあり方にもつながる問題であり、特に比例区だけを大幅に削減し、小選挙区と比例代表のバランスを変えることは、現行の選挙制度の性格にも影響する問題です。スタートアップ政党の出現など新規参入に対する障壁にもなるのであり、与野党を含めた国会での議論に加えて国民的な議論も必要となります。
逆に、バランスを維持したまま削減しようとすると、小選挙区の定数削減が地方の議席の切り捨てにつながり、地方の声が国会に届かない状況を招きかねません。
国会議員の定数削減は、地方自治体レベルで過半数を占める政党が地方議会の定数削減を強行するのとはわけが違うのです。
第2に、そのような議員定数の削減を、臨時国会までに成立させることについては、自民党内での反発も強く、党内合意を得ることも困難です。
実際に、吉村氏が議員定数削減を「絶対条件」として掲げた直後から、自民党内からは、選挙制度調査会の会長で、前の臨時総裁選で選挙管理委員長を務めた逢沢一郎氏が、
《与野党で「衆議院選挙制度に関する協議会」で議員定数を含めて、あるべき制度を議論中。この状況のなか、自民・維新でいきなり定数削減は論外です。》
とXに投稿、山下貴司元法務大臣も、
「議員削減は国民の参政権を削るという側面がある」
とした上、「客観的なファクト」として、
「現在の衆議院議員定数465人はこの100年で最も少ないこと」
「国際的に見ても、国会議員一人あたりの人口は、日本は約27万人で、独・仏・英の2倍以上。逆に言えば、日本国民一人が国会議員を生み出す力はOECD平均の半分以下であること」
などを指摘するX投稿を行うなど、維新との連立協議の中で議員定数削減を持ち出すこと自体について、公然と反対の声が上がりました。
維新が政策協議開始の時点から「絶対条件」として掲げていた「社会保障改革」、「副首都構想」といった要求を受け入れることも、自民党にとって容易なことではありませんでした。
「社会保障改革」については、維新は、現役世代の負担軽減を目的とした社会保険料引き下げを強く主張してきました。高齢者の窓口負担増、OTC類似薬の保険適用除外などにより国民医療費を年間4兆円以上削減し、社会保険料1人あたり年間6万円の減額を目指し、手取り収入を増やして消費拡大を図るというものですが、自民党内では反対意見が強く、もう一つ維新が強く要求していた「教育無償化」の方で合意して24年度予算案への賛成を取り付けたという経緯があります。
「副首都構想」の方は、副首都の基盤となる「危機管理都市」や経済特区を整備する構想と、大阪市解体による特別区設置の「大阪都構想」という維新の結党以来の看板政策の実現を目的とするものです。これに対して自民党大阪府連は住民投票で反対を表明し、2015年・2020年の住民投票で維新とは激しく対立し、その結果、都構想は否決されました。「副首都構想」は、大阪自民党にとって到底受け入れられるものではありません。
自民党内での議論の体制の未整備
維新が「絶対条件」として掲げていた「社会保障改革」、「副首都構想」、「議員定数削減」は、自民党にとって、いずれも容易には応じられない事項であり、党内で十分な議論が必要なはずでした。
自民党としても政策の根幹に関わる重要事項について維新との間で合意を行うのであれば、自民党の党則に定められた手続に従い十分な検討を経て党としての決定を行うのが通常のやり方です。
ところが、自民党内での検討の体制、意思決定手続等については、10月15日の拙稿【「党人事空白」で連立協議は困難~多党化への不適応が招いた“自民党の危機”】でも述べたように、10月4日に高市新総裁が選任され、自民党の体制が一新された後は、幹事長、総務会長、政調会長などの役員人事が決定されているだけで、それ以外の党内人事は未了でした。
しかも、政務調査会については、政調会長に小林鷹之氏が選任され、その後、会長代行・代理等が選任されているだけで、部会長も部会メンバーも空席でした。本来であれば、「社会保障改革」については厚生労働部会、「副首都構想」については国土交通部会で、従来の議論を踏まえて検討が行われるべきであるのに、部会長、副部会長は全く選任されていませんでした。
昨年10月の衆院選で、裏金問題への国民の批判などから惨敗し、国民の支持を失っていた自民党の内部で、参院選後に「石破おろし」と言われる権力闘争が起こり、その末の臨時総裁選で予想に反して小泉進次郎氏を破って当選したのが高市氏でしたが、執行部人事については、極端に麻生派に偏っていること、「裏金議員」萩生田光一氏の幹事長代行起用などに対して、世論の反発が強まっていました。維新との連立合意を拙速に進め、それまでの党内での議論を無視した合意を行えば、党内で潜在化していた高市執行部への批判が一気に顕在化する可能性もありました。
自民党が党内手続を省略して、維新との連立合意にむけて具体的に義務を負う形の合意を行うことには、「議員定数削減」については、維新が地域政党として行った「改革の出発点」は国政レベルとは根本的に異なること、「社会保障改革」「副首都構想」も含め、自民党内での合意を得ることが困難であること、という二つの面から無理があったのです。
連立合意書の内容では「絶対条件」になっていない
上記のような経緯を経て、自民・維新の両党は、20日の夕刻に連立合意に至ったことを発表し、連立合意書も公表されました。
その内容からはっきり言えることは、政策協議の際に維新の側が「絶対条件」なとど強調した「社会保障改革」「副首都構想」について、今回の連立合意書には、自民党側として、それまでの党の方針や政策に反する具体的な合意はほとんどなく、何かを具体的に義務づけられるものはほぼないことです。
そういう意味で、「自民党内で合意の困難性」という面での問題は少ない内容だったと言えます。
維新が「絶対条件」として掲げていた要求のうち、「社会保障改革」については、
具体的な制度設計を令和七年度中に実現しつつ、社会保障全体の改革を推進することで、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指す
というかなり曖昧な表現にとどまっています。
「副首都構想」については、
首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能分散及び多極分散型経済圏を形成する観点から、令和七年臨時国会中に、両党による協議体を設置し、首都及び副首都の責務及び機能を整理した上で、早急に検討を行い、令和八年通常国会で法案を成立させる
とされています。この法案が、実質的に大阪を副首都とすることにつながるものかどうかが問題ですが、この点については、「両党による協議体」に委ねられることになるので、この連立合意書だけでは方向性は不明です。
最後の「一二、政治改革」の項目に、維新にとって、自民党との連立合意の最大の障害になると考えられた「企業団体献金」の問題への対応と、それを目立たなくするための「目くらまし」のために出してきたとしか思えない「議員定数削減」について記載されています。
「企業団体献金」については、「自由民主党は禁止より公開」、日本維新の会は「完全廃止」と従来の主張は異なっていたが、「制度改革が必要であるとの課題意識は共有し」ているが「最終結論」が出ていないとし、「企業団体からの献金、政治団体からの献金、受け手の規制、金額上限規制、機関誌等による政党の事業収益及び公開の在り方」などを同列に並べて検討対象として、「協議体」「第三者委員会」などでの検討を行って、
高市総裁の任期中に結論を得る
とされています。企業団体献金に依存してきた自民党の論理を丸呑みし、「検討の体裁」だけ整えて結論を先送りするものです。
これは、「企業団体献金の受け皿規制」についても自民党に要求せず、他の野党が法案を提出しても反対するという意味です。
「議員定数削減」については、連立合意書の「政治改革」の項目に、
1割を目標に衆院議員定数を削減するため、25年臨時国会において議員立法案を提出し、成立を目指す。
と書かれています。
「25年臨時国会において議員立法案を提出」という点は、維新が自民党側に今年中に国会での法案提出をする義務を負わせるものです。しかし、その法案の内容は「1割を目標に」と書かれているだけで、比例と小選挙区の関係についても触れられていません。そして法案の「成立」については「目指す」というだけなので、結局、吉村氏が強調する「成立」まで約束したわけではありません。自民党内で議員定数削減の法案について意見集約することも容易ではありませんが、成立の見込みがたっていない法案を一応提出するだけであれば、それほど大きな抵抗もないでしょう。
連立合意書上は、「議員定数改革を来る臨時国会で行うことの確約」などとは程遠いものであり、結局のところ、吉村代表が唐突に持ち出した「議員定数削減」が、企業団体献金の議論から逃げるための「目くらまし」だったことは否定する余地がありません。
「物価高対策」にもめぼしいものはない
国民が強く求めている「物価高対策」についても、連立合意書の12項目の最初に「経済財政関連施策」があり、 7月の参院選の際も大きな争点となった物価高対策が記載されています。このうち、
ガソリン税の暫定税率廃止法案を令和七年臨時国会中に成立させる。
だけが即効性のある対策ですが、これは既に8月に与野党間の合意ができており、政治空白がなければ11月1日に実施される予定だったものです。
それ以外は、
電気ガス料金補助をはじめとする物価対策
インフレ対応型の経済政策に移行するために必要な総合的対策
所得税の基礎控除等をインフレの進展に応じて見直す制度設計
など抽象的な内容ばかりで、参院選で維新が掲げた公約についても、
給付付き税額控除の導入につき、早急に制度設計を進めその実現を図る
飲食料品については二年間に限り消費税の対象としないことも視野に法制化につき検討を行う
などのあいまいな表現にとどまり、自民党に具体的な義務を負わせるものではありません。
その一方で、参院選で石破自民党が掲げた「給付金」については
行わない
と明言しています。
維新は、自民党との連立に向けての政策協議の目的として「この機会に改革に向けての政策実現を前に進める」ということを強調してきましたが、結局のところ、物価対策等、国民生活に直結するテーマについては、今回の連立合意書の内容は、自民党側に具体的な約束をさせる内容にはなっていません。
「タカ派保守的な主張」が随所で具体化
一方、連立合意文書の、
-
「三、皇室・憲法改正・家族制度等」
-
「四、外交安全保障」
-
「五、インテリジェンス政策」
等の項目には、高市氏の支持の中心となった自民党の保守派の主張、或いは、それ以上にタカ派保守的な主張が具体的に書き込まれています。
敵基地攻撃能力保有、防衛費の国内総生産(GDP)比2%への引き上げなどを決めた安保関連3文書の改定の前倒しを明記しているほか、外国人問題では、受け入れ規制や在留者向け制度の悪用への対応といった規制強化策、選択的夫婦別姓制度に関しては、旧姓の通称使用の法制化法案を2026年の通常国会に提出し成立を目指すとして、制度導入に反対することなどを具体的に盛り込んでいます。改憲についても、「可及的速やかに、衆参両院の憲法審査会に条文起草委員会を常設する」と盛り込んでいます。
このような維新の保守タカ派的な性格は、日頃の「改革政党」としてのイメージとは異なります。しかし、維新は、自民党の地方政治家を中心に結成された党で、もともと、このようなタカ派保守的思想が党の中核に受け継がれており、同様にタカ派的な思想傾向を持つ高市氏から「国家観をともにする党」と評価された「本性」が、連立合意の中で具体的に表れたと見ることもできます。
維新が連立合意に至った背景としての3要素
維新は、連立合意の最大の障害となる「政治とカネ」問題から目を反らすために、見え透いた「目くらまし」としての「議員定数削減」まで持ち出し、高市政権樹立に突っ走る自民党との「連立合意」による強い結びつきを求めました。
そのような動きの背景として「改革政党志向」「地域政党志向」「右翼政党志向」の3つの要素が考えられます。
まず、「改革政党志向」は、これまで維新が支持者や国民に訴え続けてきたものであり、今回の連立合意に向けて「絶対条件」を掲げたのも、「改革政党」としてのアピールを継続するためのものでしたが、少なくとも連立合意書の内容からは、ほとんど評価できるものはありませんでした。
しかし、自民党との連立に向けての協議開始の時点で突然登場した吉村代表は、頻繁にテレビ出演し、維新の「改革政党」としての「一丁目一番地」であることを強調し、連立合意書公表後も、「議員定数削減が出発点だ」とし、「それが実現すれば改革が一気に進む」などの発言を続けています。
実際に維新が大阪府議会・市議会で行ってきた議員定数削減によって、一人区を増やし、それによって対立政党(自民党など野党)にとって圧倒的に不利な状況を作るというやり方は、国政レベルでも強引に実行すれば、それによる与党独裁体制によって与党側の政策を次々と実行することも不可能ではありません。
連立合意書の中で、唯一自民党に一応の具体的義務付けを行った形になっているのが「議員定数削減法案の通常国会での提出」ですが、比例区定数の大幅削減で小選挙区の割合を高め、衆議院での与党独裁体制を構築することを目的とするのであれば、高市氏や支持者の議員達にとっても、大きな意味を持つものとなります。そのような法案を国会に提出し、自民・維新に加えて参政党などの賛成を得て法案を成立させ、解散総選挙に打って出れば、公明党、共産党などの少数政党を駆逐し、自民・維新の与党で圧倒的多数の議席を狙うことも不可能ではありません。
つまり議員定数削減を、比例区だけを大幅に削減する形で実現すれば、維新の「改革政党志向」のみならず、タカ派保守政党による国会の独裁体制で「右翼政党志向」を実現することも可能になりかねないのです。
それは日本の民主主義にとって、重大な脅威となります。
日本保守党の島田洋一衆院議員が10月19日に「自民党の高市早苗総裁からの電話の内容」についてのXを投稿していますが、それなりの意味が込められているようにも思えます。
「日本保守党と方向性が一致する政策も多いので、闘うなら大いに支持する旨を答えた」
とした上で、「日本維新の会」による定数削減案については、
「新興小政党を潰すことになる、維新の『衆院比例区に限った定数削減』案に、率直に異議を呈したところ、中身は控えるが、高市氏から丁寧な説明があった」
と述べています。その「丁寧な説明」というのが、上記のような「議員定数削減によってタカ派政党の国会での圧倒的多数をめざす」という趣旨なのかもしれません。
もう一つの背景として考えられる「地域政党志向」は、今回維新が企業団体献金問題への対応など説明困難な問題が多数あるにもかかわらず、拙速に連立に向けて協議をはじめた時点でも指摘されていた、大阪の地域政党から出発し、全国政党に展開しようとして、それが大きな曲がり角に来ているという、維新の「党勢」の問題です。
このところ国政選挙で、関西以外では退潮傾向が著しく、党内対立も顕在化して離党者が相次いでいるという維新の党内事情から、自民党側に「貸し」を作れるだけの議席数がある間に連立合意を行い、前回選挙で全勝した大阪の小選挙区での自民党との選挙協力によって大阪府自民党を事実上壊滅させることで関西圏の地域政党としての基盤を確保し、国政政党としては自民党に吸収される形でフェードアウトしていく方向です。
そうだとすれば、維新の現状を考えた場合の苦肉の策であり、少なくとも大阪の維新にとっては、大阪都構想の実現の可能性が高まるなどの実益があり、維新の支持者にとっても理解納得が可能な話ではあります。
維新代表・大阪府知事吉村氏の「議論のすり替え、ごまかし」
維新の自民党との「連立合意」が、「地域政党志向」という、こじんまりした方向に向かうのであれば、大阪の局所的な問題にとどまります。しかし、改革の出発点だとする「議員定数削減」を強引に進めることで、「改革政党志向」のみならず「右翼政党志向」も狙おうとするのであれば、今後、その動向には、最大限の注意と警戒が必要です。
そして、維新という政党が、「地域政党」の実体に隠れて、国政政党としての実体が見えにくく、しかも説明責任を問いにくいという特殊性に留意する必要があります。
党首は大阪府知事であり、国会議員ではありません。国会対応などについて具体的な事項は共同代表の藤田氏が説明し、党の方針や根本的事項は吉村代表が説明するのでしょうが、その場は国会ではなく、限られた記者会見の場やテレビ出演ということになります。
その典型が、今回の連立協議が始まってからの吉村代表の「立ち回り」であり、それが今後も繰り返されることになる可能性が高いのです。
連立合意が公表される前日の19日の夜のフジテレビの番組「Mr.サンデー」では、その直前に出演していた国民民主党の玉木氏からの「企業団体献金の受け皿規制法案」への賛成要請に対して、
「企業団体献金は、維新だけは全く受けないが、自民党以外の他党も、労働組合や赤旗機関紙収入などの収入を得ている。」
と言って、論点をすり替えて質問に正面から答えず、はぐらかしました。
問題なのは、自民党の企業団体献金が、個人の財布としての政党支部に入り、その使途が不透明であることであり、企業団体献金自体の存否とは別の問題です。
しかも、もともと「受け皿規制」を提案している国民民主・公明の両党は、企業団体献金全面禁止を主張しているわけではないので、吉村氏の話は、両党への反論にはなっていません。維新が、自民党の裏金問題発覚までは、「政治資金パーティー」を積極的に行い、企業から多額のパーティー券収入を得ていたことは棚に上げています。
また、安野貴博氏からの
「議員定数を比例のみ50減らすことは大政党に有利、中小政党、スタートアップ政党に不利に働き、政治の新陳代謝が働かなくなるのではないか」
との意見に対して、
「自分達も35の少数政党だ。今の比例では復活当選しているゾンビ議員が問題。実際に、過去に定数削減の約束が守られなかったのは、大政党の議員が反対するから」
などと反論していました。
しかし、維新は大阪の19を含め小選挙区選出議員が23名と大半を占めています。比例復活が問題なら重複立候補を禁止すればいいのであり、定数削減の問題ではありません。また、2012年の民主党の議員定数削減要求は、当時の政権末期の特殊事情によるもので一般化すべきではありません。そもそも、「既得権益を守ろうとする反対」と「選挙制度の議論の在り方論からの反対」を混同させようとする言い方は「詭弁」そのものです。
また、杉村太蔵氏の、「大阪府知事と与党党首」という「二足のわらじ」に対する疑問をぶつけられて、
「私は万博があったので三足のわらじを履いてましたから」
などと、的外れな返しでごまかし、立場の違いからくる利益相反関係などの問題について正面から答えようとしません。
連立合意書が公表された直後の21日の昼のTBSの番組「ひるおび」に出演した吉村氏は、メインキャスターからの質問に、
「議員定数削減が改革の一丁目一番地」
との持論を滔々と述べ、ごく限られた時間で政治ジャーナリストからの質問を受け、田崎史郎氏から、
「通常国会で法案が提出できなかったり、成立しなかったりしたら連立から離脱するのか」
と問われても、
「絶対成立する」
などと言ってはぐらかし、田崎氏も苦笑していました。
このような話のすり替え、ごまかしを、対面で自然に行って相手を巧妙に誤解させるのが、経済犯罪としての「詐欺師」の手口です。吉村氏の場合は、あまりに見え透いており、対面ではとても通用しませんが、テレビ出演では、一方的に自説を述べ、質問されても、すり替え・ごまかしでやり過ごし、時間の関係でそれに対する再反論がほとんどできないので、その場でバレることがありません。こういうことが、これまでも大阪での記者会見やメディア出演で繰り返されてきたのでしょう。
このようなことが国政に関する問題で行われれば、大阪の有権者に対する「維新による洗脳」の手口が、全国レベルに広がる可能性があります。それが、維新と高市自民党の支持拡大につながるようなことになれば、日本の政治情勢は大きく変わることになります。
今回の連立合意書の方向性からすると、そこに民主主義の重大な危機が待ち構えていると言わざるを得ません。
すでに登録済みの方は こちら