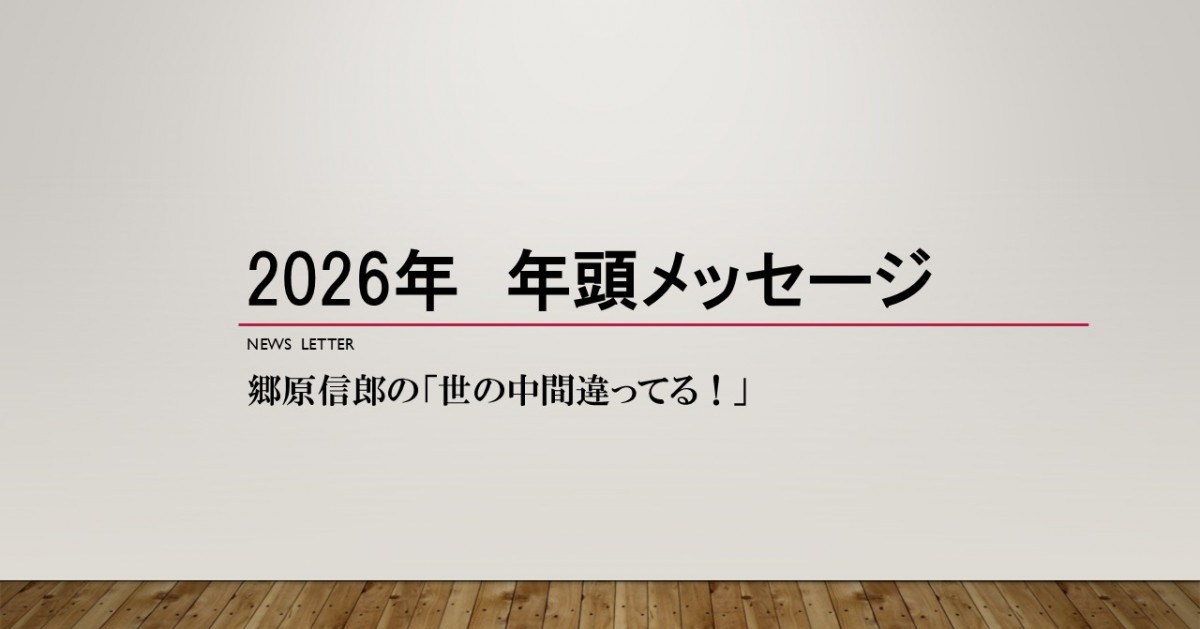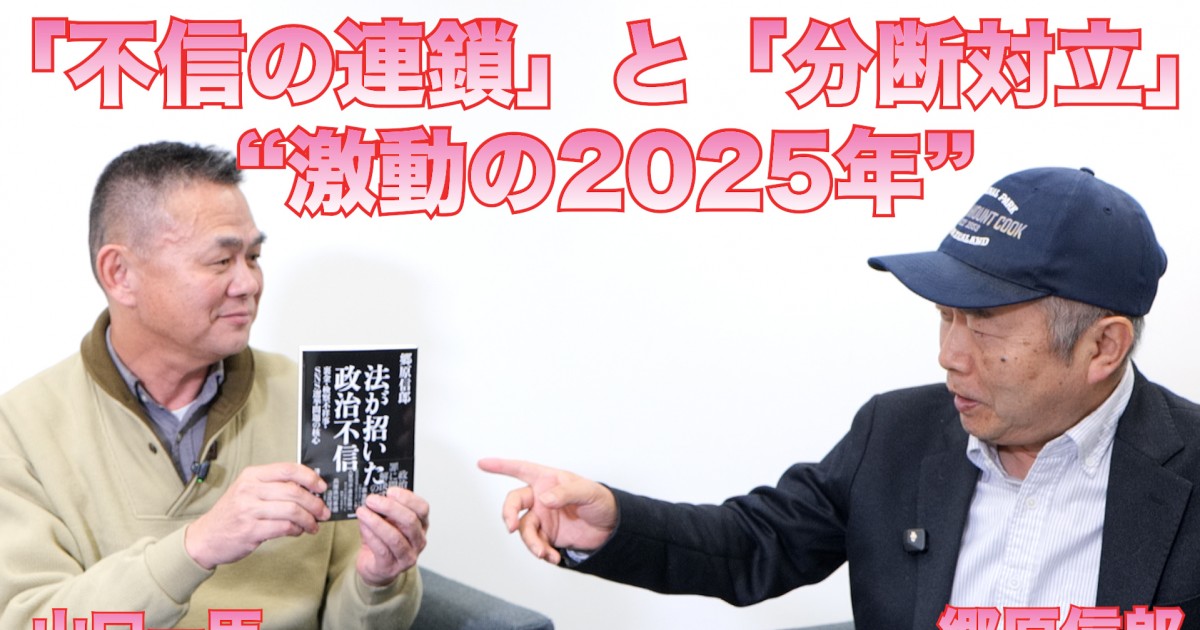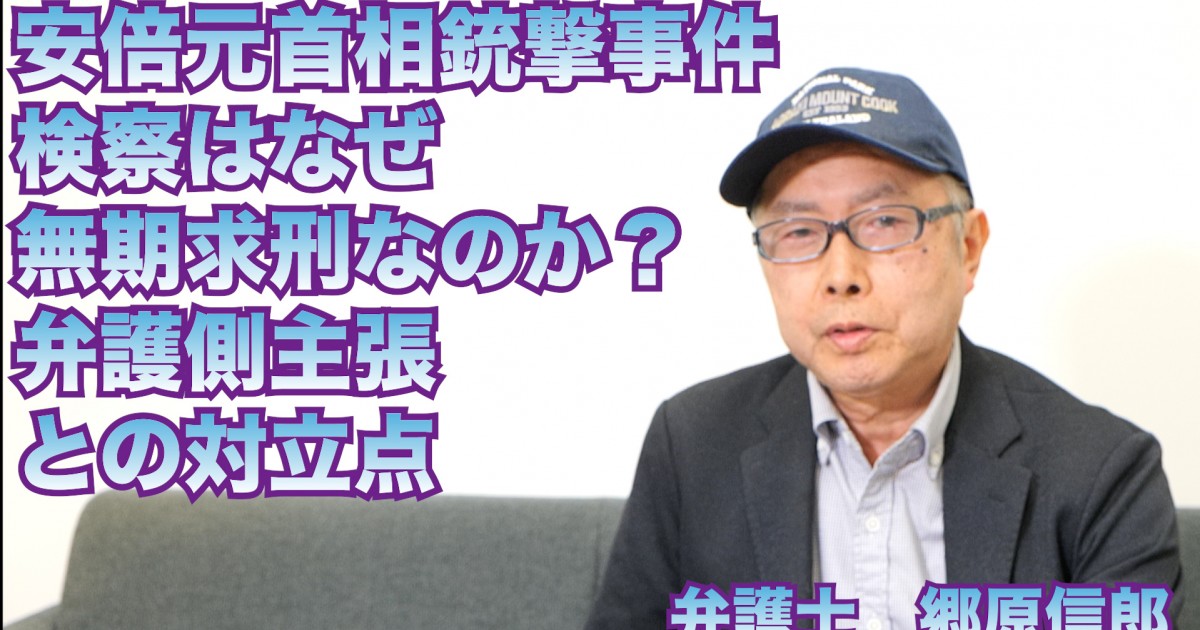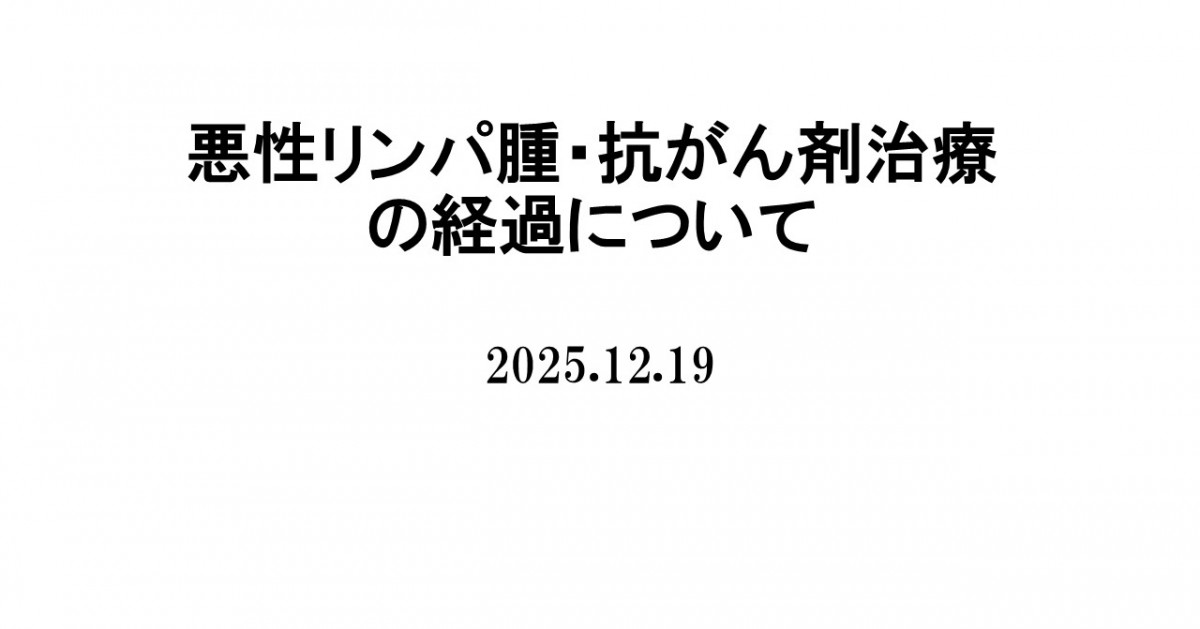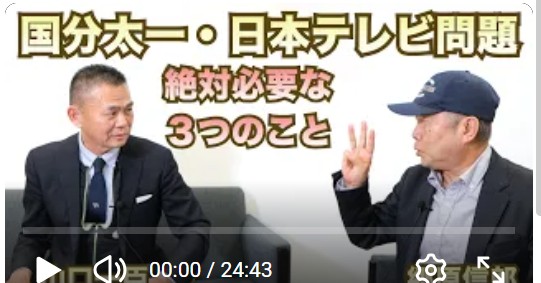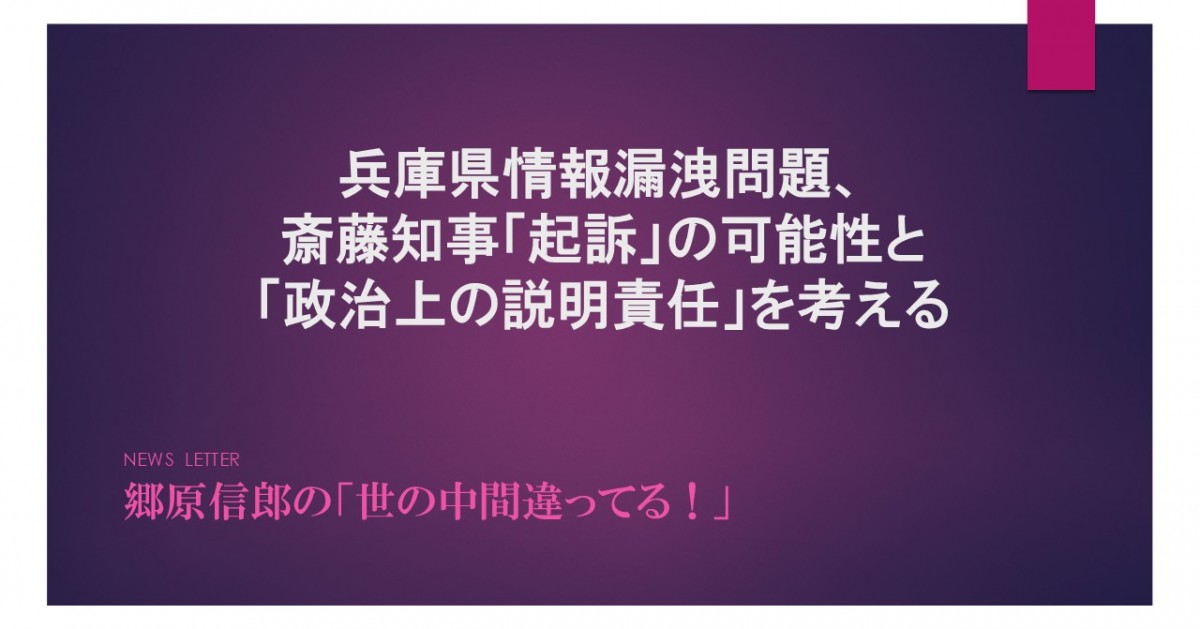斎藤元彦氏公選法違反事件、代理人説明の不合理性と71万5000円支払いの買収罪該当性
【斎藤元彦氏公選法違反事件、折田氏note記事の内容と裏付け証拠を徹底分析する】で詳細に解説したように、折田氏のnote記事は、極めて信用性が高く、その内容によれば、折田氏やmerchu社が、兵庫県知事選挙で、斎藤氏のためのSNS広報戦略を主体的裁量的に実行していたことは明らかです。
このようなnote記事が2024年11月20日に公開され、その後、公選法違反の疑いが各所で指摘されたことから、11月27日の斎藤氏による兵庫県知事定例会見において、本件note記事に関する質問がなされました。
しかし斎藤氏は、
「公職選挙法には抵触しないと認識している。弁護士に説明させる」
と述べ、同会見終了後に、被告発人斎藤の代理人の奥見司弁護士による会見がおこなわれました。
その後も、警察の捜査等について報じられた際に、公選法違反について質問があっても、
「代理人弁護士に任せています。公職選挙法に抵触するようなことをしていないという認識でいます」
と繰り返し述べ、具体的な回答を拒絶しています。
一方、県議会では、2024年12月11日の総務常任委員会で、山本敏信委員が
本年11月末に、ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰があった。これは、全議員がメールで報告をいただき、一覧表ももらっている。今回は15社が表彰された。その資料の一覧の中に、現在、知事選挙で問題になっているPR会社のmerchuも含まれている。知事は、弁護士を通して公職選挙法違反ではないということを明言されており、知事は何も発言していないことも不思議な状況である。このmerchuの代表者が表彰式には出られていない。公職選挙法の問題が生じた後に表彰を持って行かれたのか、merchuの方が辞退されたのか、状況を伺う
と質問しましたが、その場では具体的な回答は行われず、その後の県議会の質問で、斎藤知事の公選法違反の問題への言及はあっても、斎藤知事に対して公選法違反自体についての質問は行われていません。
世の中では大きな関心を集め、警察の強制捜査等も行われている事件について、斎藤知事も買収側の当事者として告発されているのですから、通常は、斎藤知事に対して県議会でもその疑惑について質問が行われ、それに対して斉藤知事が何がしかの答弁を行うか、捜査中であることを理由に答弁を差し控えるか、ということになるのが通常だと思いますが、兵庫県議会では、知事に対する質問すら行われていません。
それだけに、この斎藤知事とmerchu社、折田氏との公選法違反の問題については、斎藤氏の代理人奥見弁護士の説明がすべてと言うことになるわけです。
本稿では奥見弁護士の説明に合理性があるのか、信用性があるいのかという点について徹底検証します。
斎藤知事の説明責任と政治責任
まず、前提として重要なことは、斎藤氏は兵庫県知事として強大な権力を持つ地方自治体の首長であり、その権力の座に選ばれた知事選挙において、自らの公選法違反の疑いが生じているわけですから、斎藤氏には県民に対して説明責任があるということです。それは、merchu社への71万5000円の支払いが公選法の買収罪に当たるかどうかという刑事責任の問題だけにはとどまりません。政治的にも重大な説明責任があるということです。
同社はSNS運用や広報戦略を専門とし、兵庫県を含む、自治体における行政関連業務を得意とし、兵庫県との関係性は強いものがありました。
例えば選挙前、merchu社は斎藤県政下の兵庫県から「ひょうご・こうべ女性活躍推進企業」や「ひょうご仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)推進企業」として表彰を受けていました。また、正社員わずか数名の小規模企業ながら、県の公報誌などで折田氏の活躍が度々紹介され、県HPトップページで「優良企業」としてPRされていました(2024年11月下旬に削除)。
さらには、折田氏個人も、「兵庫県地域創生戦略会議」の委員、「兵庫県eスポーツ推進検討会」の構成員、「次世代空モビリティひょうご会議」の有識者(構成員)に任命されており、県の政策立案に関与していました。
そのうえ、広島県、高知県、広島市、藤沢市、神戸市など、複数自治体のSNS運用やイベントプロモーションでmerchu社が業務を受注しており、兵庫県とは直接の契約関係はないものの、県が運営する地域情報アプリ『ひょうごe-県民アプリ』のリニューアルについて、再委託という形で関与しています。
このように県知事の職務上、公務で一定の関係性があり、また、業務上(特に将来的に)関係がないとはいえないmerchu社に、斎藤氏が知事選挙での選挙関連業務を発注すること、自ら社長の折田氏を訪ねた上、選挙の応援を受けること、それは、仮に無償のボランティアであったとすれば、なおさら重大な問題があると言えます。その点に関して、斎藤氏には、刑事責任とは別個に、知事としての説明責任、政治責任があります。
斉藤知事から、このような重大な説明責任をすべて丸投げされたのが奥見弁護士ということになるわけですから、その説明の合理性、信用性が厳しく問われることになるのは当然です。
斎藤氏代理人弁護士による「請求書」公表と事実経過の説明
会見で奥見弁護士は、斎藤氏側からmerchu社に支払ったのは、以下の5項目であることを明らかにし、請求書を公表しました。
●公約のスライド制作 30万円
●チラシのデザイン制作 15万円
●メインビジュアルの企画・制作 10万円
●ポスターデザイン制作 5万円
●選挙公報デザイン制作 5万円
会見で奥見弁護士は以下のような事実経過の説明を行っています。
(1)斎藤氏は、本年9月末頃、支援者から、社長夫妻(折田氏夫妻)に会ってみるよう勧められた。その支援者から、「ボランティアで協力してくれる方を探している中で、社長夫妻が賛同して手を挙げてくださった」との説明を受けている。なお、社長が以前から兵庫県の委員を務めている関係で、以前から斎藤氏と社長との間に面識はあった。
(2)斎藤氏が、PR会社(merchu社)を訪れたのは、2024年9月29日で、滞在時間は17時30分から約1時間。訪問前に、斎藤氏からPR会社に事前準備について依頼したことはない。この席で社長から、斎藤氏が選挙に出るとした場合に協力しうることの説明を受けている。説明の中には、後に、実際に依頼することになったポスターデザインの制作、チラシデザインの制作、などのほか、SNSの利用についての話もあった。29日の話し合いは、斎藤氏がPR会社を訪問し、説明を聞いただけで終了している。
(3)翌日以降、PR会社から、いくつかのプランと、その見積もりが出されたと聞き及んでいる。現時点で私の手元にはないが、見積書には、今回実際注文するに至ったポスターデザイン制作などのほかに、YouTube用動画撮影などの項目があったとのこと。しかし、noteに記載されているような、広報全般をPR会社に依頼するとか、SNS戦略の策定などの項目はなく、いずれも制作物の提案であった。
(4)PR会社からの提案に対して斎藤氏サイドが依頼したのが、請求書記載の5項目。なぜこの5項目に絞ったかについては、「斎藤氏は、県民の皆様に伝えたかったことを発表する方法としての公約スライドの制作、選挙に最低限必要と考えられた選挙ポスター、チラシ、選挙公報の依頼に絞って依頼することにした」とのこと。当時は、政治活動、選挙運動を行う資金の目途も立っていない状況であったこともその理由であったことも聞いている。
(5)社長がnoteで記載されているようなSNS戦略を依頼したということや、広報全般を任せた、ということは事実ではない。
(6)個別に依頼したので、契約書は作成していない。注文は10月3日から10月9日ころにかけて、個別で依頼している。個別というのは、「チラシデザインの制作をお願いします」「わかりました」というような関係。
(7)PR会社側からの請求は、発行日が10月31日のものであり、1通のみ。内容を確認後、本件支払をしたのが11月4日。
(8)社長ご夫妻は、斎藤氏がPR会社を訪れた日以降、斎藤氏の考えに賛同し、斎藤氏の応援活動をしている。社長の活動としてこれまで確認できているのは、・公式応援アカウントの取得・公式応援アカウントの記載事項のチェック・街頭演説会場などにおける動画の撮影、アップロードなど。
これらは、社長、社長の夫、斎藤氏の同級生、そのほか選挙スタッフといえるメンバーと話し合って行われている。社長はSNSのことに詳しい方なので、他のスタッフからの質問に答えたり、社長から助言などがあったことも確認している。
(9)これらはいずれもPR会社としての活動ではなく、選挙のボランティアの一員としてなされたものであり、かつ、社長が主体的裁量的に行ったというものでもない。社長個人とは何の契約もない、報酬支払の事実も、その約束もない。
つまり、斎藤氏側の説明は、斎藤氏が「merchuオフィス」を訪問し、その際に、ポスターデザイン、チラシデザインの制作、SNSの利用について「説明」を受けたが、SNS広報戦略策定についての「提案」は受けていない、その後、同社から送付された見積書の中の上記デザイン制作業務だけを依頼し、広報戦略、SNS戦略などは同社には依頼していない、さらにその後のSNS運用などは、折田氏が個人としてボランティアで行ったものであり、しかも斎藤氏側の陣営が主体的に行ったもので、折田氏が主体的に行ったものではない、というものです。
note記事の内容についての言及
そして、折田氏が投稿したnote記事について、奥見弁護士は、
「投稿には事実でない部分が記載されており、盛っていると認識している」
と述べ、具体的には、以下の点が事実と異なるとしています。
-
◎請求書の5項目以外のものはPR会社が行った事実はない。社長個人が行った。
-
◎プロフィール撮影は社長個人が行った。
-
◎アカウントの立ち上げも行われているが、あくまで個人。セキュリティや公式アカウントとしての信頼感の担保も個人で行ったもの。契約内容には入っていない。
-
◎ハッシュタグは10月に数人で決めた。
-
◎SNS運用は社長もかかわっていたと思うが、選挙スタッフと一緒あるいはスタッフのみのこともあった。
-
◎広報全般を任せた事実はない。
選挙運動費用収支報告書の記載
斎藤氏側は、上記のような主張にもとづき、12月2日に、兵庫県選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書において、関連する記載を行っています。
具体的には、2024年11月4日に斎藤側からmerchu社に支払われた71万5000円のうち、「メインビジュアル企画制作 11万円」「チラシデザイン制作16万5000円」「ボスターデザイン制作5万5000円」「選挙広報デザイン 5万5000円」については、「支出の部」に、「選挙運動」の「区分」で、「さいとう元彦後援会」宛ての支払として記載されています。
一方、「公約スライド制作 30万円(税別)」については、同収支報告書に記載されていません。
この点につき、奥見弁護士はメディアの取材に対し
「公約のスライド制作は政治活動にあたり、選挙運動には含まれないため除いた。問題はないと考えている」
と説明しています。
奥見弁護士の説明は不合理、信用性なし
奥見弁護士の説明は、公選法違反ではないとする斎藤氏の見解にできるだけ沿う主張を一方的に述べ、それに反するnote記事の内容を、事実と異なると主張するだけで、その根拠は何も示していません。証拠として提示しているのは、事後的な請求書のみで、契約書や見積書など、契約時の当事者の意思表示の内容を客観的に示す証拠は何も提示されていません。
【前記ブログ】で述べたように、折田氏のnote記事については、周囲の言動など、note記事と整合し、奥見弁護士の説明に反する客観的な証拠が見られることと比較しても、斎藤氏側の主張の信用性は低いと言わざるを得ません。
斎藤氏側は、斎藤氏が9月29日に「merchuオフィス」を訪問し、その際に、ポスターデザイン、チラシデザインの制作、SNSの利用について「説明」を受けたが、SNS広報戦略についての「提案」は受けておらず、その後、同社から送付された見積書の中の5項目のデザイン制作業務だけを依頼し、広報戦略、SNS戦略などは同社には依頼していないと主張しています。
しかし、以下の点を考えればその説明の信用性はほとんどないと言えます。
9月29日の「merchuオフィス」での打ち合わせでは、安野氏の都知事選の選挙総括noteも使いながら、「広報戦略のご提案」の提案を斎藤氏本人に向けて行っていたことが、客観的なnote記事掲載写真からも明らかです。したがって、当日の話題の中心が個々のポスター、チラシなどの制作の話ではなく、確固たる「SNS運用方針」と、その方針が「SNS運用フェーズ」に従い投開票日まで貫かれること、などの広報戦略の説明にあったことも明らかで、個々の制作の話は、そうした戦略の下で一新され、統一されたコピー・メインビジュアル等をいかに制作物に落とし込むか、という、広報戦略に附随する話に過ぎず、制作だけ切り離せる話ではないことになります。
そうであれば、9月29日の打ち合わせを受けて、後日、個々のデザイン制作だけを個別に依頼したとの斎藤氏側の説明は、不自然、不合理です。また、斎藤氏側は、斎藤氏側の説明に符号する、個別の見積書すら示すことができていません。
しかも、前に述べたように、K氏と神戸市議とのLINEのやりとりなどから、10月5日に、斎藤陣営で「選対会議」が開催され、merchu社に対し「SNS監修」を依頼することが決定したことは明らかです。
5項目のデザイン制作業務だけを依頼し、広報戦略、SNS戦略などは同社には依頼していないとの斎藤氏側の主張は、客観的にみておよそ根拠のない主張であり、認められないものと考えます。
「SNS運用はボランティア」との主張の不合理性
斎藤氏側は、9月29日の打ち合わせにおいてSNSの利用についての話し、すなわち「SNS運用についての提案」があったことは認めていますが、それは、merchu社に依頼した業務には含まれず、実際に折田氏が行ったSNSアカウントの立ち上げ、ハッシュタグの決定、記載事項のチェック、動画のアップロードなどのSNS運用は「個人としてのボランティア」だったと説明しています。しかも、折田氏が主体的・裁量的に行っていたものではなく、斎藤氏や斎藤陣営が主体的に運用していたとも主張していますが、以下の(a)~(d)で述べる理由により、そのような斉藤氏側の主張の不合理性は明らかです。
(a)「公式応援アカウント」の設置と「本人アカウント」との連携という発想
「応援アカウント」の設置や運用は、明らかに一連の広報戦略の下で、折田氏の発想で設置され、折田氏の考え方にもとづき運用されており、merchu社に依頼した業務には含まれないとか、斎藤氏や斎藤陣営が主体的に運用していたなどという主張に根拠はありません。
例えば、そのことは、公式の「応援アカウント」の設置、運用に如実に現れています。
通常、選挙における「応援アカウント」は勝手連的なものであり、候補者側が主体的に管理するものではない、と考えられます。実際、斎藤氏側も、2021年の前回選挙では、「応援アカウント」こそ存在するものの、公式を打ち出しているわけでもなく、「本人アカウント」との連携も行われていないように見えます。
しかし今回は、「公式」の「応援アカウント」が設置されており、その投稿内容も、「本人アカウント」との連携、連動を強く意識したものとなっています。このようなアカウントの設置や、本人アカウントとの連動などのアイデアが折田氏のものであることは、令和6年に受注した「高知県SNS公式アカウント分析等委託業務」の企画提案書で同様の「アカウント相互連携」「相乗効果」を謳っていることからも明らかであり、note記事記載の通り、折田氏の提案した「戦略」だと考えられます。
(b)「公式応援アカウント」と「本人アカウント」との相乗効果ということの意味
「応援アカウント」を候補者側が公式に設置する、ということは、「応援アカウント」が単に斎藤氏の動向・予定を告知する目的だけで設置されていたのではないことを意味します。それだけが目的なら、公式本人アカウントから淡々と情報発信すればよいためです。
より重要なのは、「本人アカウント」と「応援アカウント」を通じて発信した情報がどのように拡散し、受容されたかを分析し、次の広報戦略のアップデートに活用することです。それが「相乗効果」の意味であり、merchu社および折田氏の広報戦略なのです。
実際折田氏は、設置した「応援アカウント」の管理権限のみならず、「本人アカウント」の管理権限も有していたことが、前記の通り、折田氏note記事に掲載されている画像から推認されます。管理権限者としてXのAnalytics情報(投稿やアカウントのパフォーマンスを分析するための情報)を参照し、投稿活動を分析・可視化して、広報戦略を日々見直し、次の投稿内容の精査を行っていたものと思われ、それは業務として広報戦略を行っているプロの仕事であり、実際にnote記事記載の通りに十分な成果を上げているのであって、そのようなことを斎藤氏や斎藤陣営が成功裡に行えるとは思えません。
(c)統一的なハッシュタグによる運用
また、「ハッシュタグ」は選挙前から「#さいとう元知事がんばれ」に統一され、投開票日までその通りに運用され、当選とともに「#さいとう元彦知事がんばれ」に変化するというストーリー性まで持たせています。
「ハッシュタグ」は、note記事記載の通り、応援の流れに方向性を提供し、アルゴリズムを有利にし、また、投稿の追跡、分析も容易にするため、一本化することが非常に重要です。また、斎藤氏の「斎」の字は様々な字体がありますが、表記のゆれは投票の有効無効にも直結する極めて重大な問題です。
この「ハッシュタグ」に関しての折田氏のnote記事の記載は、その考え方、設計方法など、熟考した様が極めて具体的に書かれ、しかも当初の記事には、斎藤氏に提案した際の斎藤氏のリアクションまで書かれていて、その内容からは、折田氏が「#さいとう元知事がんばれ」との「ハッシュタグ」を考え、これへの統一を提案したものと考えるのが自然です。
しかも実際、2021年の前回選挙を含め、それまではバラバラであった「ハッシュタグ」が、10月5日に、斎藤陣営で「選対会議」が開催され、merchu社に対し「SNS監修」を依頼することが決定した直後から、「#さいとう元知事がんばれ」に変わっています。
例えば斎藤陣営の森けんと氏は、10月4日までは「#斉藤元彦がんばれ」と投稿していますが、10月5日には、
「本日も選対会議です #さいとう元知事がんばれ 皆様、このタグを覚えてて下さい」
と投稿しているのです。
こうしたことから、広報戦略上重要である「ハッシュタグ」について、折田氏が自ら考え、提案したといえ、統一的な「ハッシュタグ」による運用について、斎藤氏や斎藤陣営が主体であり、主導したとは到底いえないものと思われます。
(d)その他の運用
その他、「応援アカウント」のフォローを「本人アカウント」のみとし、偽アカウントを排除する仕組みは、素人では思いが至らない点ですが、note記事記載の通り、投開票日まで「本人アカウント」のみのフォローとなっています。
また、「応援アカウント」や「本人アカウント」に次々と投稿される、視認性の高いデザイン、綺麗なビジュアルによる演説会等の告知画像などは、必要に応じて即時に作成する必要のあるものですが、活字のバランスや配置、配色等々、全体のスタイルが統一されているものとなっており、プロの関与が強く推認される制作物です。
こうしたことからも、note記事記載の通り、折田氏が「ブランドイメージの統一」、「政策を分かりやすいビジュアルや表現で県民に届けること」や、「各SNSに適したレイアウトや内容に最適化して届けること」などの戦略の下で、折田氏が「監修者として」「責任を持って」SNS運用していたと考えるより他ありません。
結局、これらの点を総合的に考えれば、SNS運用をmerchu社および折田氏が一貫した広報戦略の下で投開票日まで行っていたことは明らかであり、折田氏がSNS運用は折田氏が主体的・裁量的に行っていないとの斎藤氏側の主張には、合理的根拠がないといえます。
斎藤氏側の主張を前提としても、公選法違反を否定できないこと
「5項目のデザイン制作業務だけを依頼した」との斎藤氏側の主張には根拠がなく、事実とは考えにくいのですが、仮に、5項目のデザイン制作業務だけを依頼したとしても、斎藤氏側の主張には不合理な点があります。
前記の通り、対価の支払いが原則として許されない「選挙運動」かどうかは、主として個々の行為が「主体的・裁量的」かどうかによって決まるのであり、それが選挙運動の「内部的準備行為」に過ぎないものかどうかや、「告示前」の行為かどうかとは無関係です。ところが、斎藤氏側は、告示前の選挙の準備である制作業務だけを切り離し、それに対して対価を支払っているのだから違法ではない、と考えているように思われます。
実際に、それぞれの制作業務の具体的な内容を見ていくと、「機械的労務」とはいえず、「主体的・裁量的」な部分があり、「選挙運動」と評価されるため、そうした制作業務に対する報酬の支払いは違法と考えられます。
「公約スライド制作」
まずは「公約スライド制作」を「政治活動」としている点です。
斎藤氏は、10月23日に、知事選への出馬表明を行い、その際に、その記者会見で公約スライドを配布し、その後、自らの公式ホームページに、選挙期間中も掲載しています。この「知事選候補としての政策」のスライド化を折田に依頼し、note記事によれば、その内容については、斎藤氏側がワードファイルで提供したとされています。
これに対し奥見弁護士は、
「スライドは告示前の記者会見で使ったため、選挙運動ではなく、政治活動の費用として後援会が支払った」
「公約の中身ではなく、あくまでデザインの委託費だ」
と述べ、
「公選法に違反する支払いはない」
と説明したとされています。
しかし、斎藤氏は、9月19日に不信任決議案が可決されて失職した前知事であり、スライド制作を折田氏に依頼したとされる10月上旬の時点では、無所属で立候補する意思を表明していたものの、選挙では圧倒的に不利とされ、当時、当選の可能性は極めて低いと考えられていました。
公約スライドは、斎藤の公式ホームページに掲載され、斎藤が知事選挙で当選して再度知事の職に就いた後も、斎藤の政治活動にも継続して使われていることは事実ですが、少なくとも、上記10月上旬の時点では、知事選に当選しなければ、斎藤氏が公約スライドを政治活動に使用する余地はほとんどありませんでした。だからこそ、選挙運動に使用するために、少しでも効果的な公約のスライド化を、PR会社社長の折田氏というプロに頼み、30万円という費用を支出したものと考えられるのです。
このような依頼時の状況からして、斎藤氏が、ただ政治活動のためにスライドを作成しようと思ったのではなく、知事選挙で当選する目的をもって、「政策スライド作成の依頼」を行ったものと考えられます。
「スライドデザイン」の構成における有権者への訴求力の追求
スライド制作の依頼を受けた折田氏は、note記事において、
「ワードファイルの内容を読み解き、どのような方でも見やすいデザインを意識したスライドに仕上げるため、記者会見の直前まで手直しをし、何とか間に合わせた」
と述べています。そして、そのような目的に沿うよう、公約スライド全体が構造化されており、細部に至るまで様々な工夫が加えられています。
例えば1枚目(表紙)では、「兵庫の躍動を止めない!」という最重要メッセージを提示し、すべての公約内容を一文でまとめています。公約内容というよりは、政治宣伝文となっていて、最低限これだけが伝わればもう十分だという内容が簡潔に記されています。
一般的に、公約スライドを手に取って詳細に目を通す者は少ないため、この表紙が一番重要であり、これだけで万単位の人々に宣伝文が到達するものでなければなりません。表紙も、末尾の写真入りスライドも、テレビ番組の制作会社が絵を使いやすいように作られています。
また、スライド3枚目(2頁目)は、「実績」の記述です。少なくともmerchu社としてはSNS戦略上、ネット上で拡散している「98.8%」という数字の訴求力は魅力であり、強調したいところです。そして単に98.8%というだけでなく、「既得権益」「しがらみ」を頭に置いています。98.8%という数字(赤字、特大サイズの文字)。それに円グラフ(さいとうブルー)で一目見て把握できるようにする工夫しており、前半は「98.8%」、それに「127億円を超え」という2か所だけ(文字サイズも特大)、しかも、今回の赤は暗めの臙脂色。目がチカチカしない。それでいて一番重要な数字は目に飛び込んでくるようになっています。
以降のスライドにも、
-
選挙戦を通じて一貫して用いられた「さいとうブルー」によるスライドの着色
-
特に若年層に届きやすい未来志向の政策の掲示
-
文字だらけにならないようイラストを交えたわかりやすいスライド構成
-
「既得権益」「しがらみ」「兵庫の躍動を止めない!」などの重要なキーワードの反復
-
写真を使い、極力文字を省き、「兵庫の躍動を止めない!」の文字を浮かび上がらせるとともに、それぞれの文字サイズを大きくし、文字位置をずらすことで文字通り「踊る」ような印象を与えるデザイン
等々、様々な創意工夫が見受けられます。
「ワードファイル」からこのようなスライドを制作する作業は、到底「機械的労務」とは言い難く、折田氏の主体的・裁量的な作業であったことは明らかです。
「公約達成率98.8%」が選挙運動で強調されるに至った経緯
上記のスライド全体の構成のうち、重要な事項のひとつが「公約達成率98.8%」です。
斎藤氏は、2024年8月1日に知事就任から3年を迎えるに際し、前回知事選挙での173項目の公約のうち171項目を達成か着手しており、着手・達成率は「98.8%」だと誇っていたのですが、実は、そもそも公約数自体が173ではなく、137しかなかったことを(何かの過程で137を173に取り違えたと思われる)、日本ファクトチェックセンター(JFC)や子守康範元毎日放送アナウンサーのYouTubeチャンネル等で指摘され、その点を効果的に攻撃されると命取りになってしまいかねないと考えたのか、公式ホームページから、前回公約を削除しています。
このような状況下で、斎藤氏が「公約達成率98.8%」を自ら主体的に選挙のアピール材料に使おうとしたとは思われず、実際に、10月20日に行われた「公開討論会」でも、斎藤は、「公約達成率98.8%」を自分からは持ち出していません。
一方で、ネット上では98.8%という数字が独り歩きし、驚異的に拡散していました(2024年9月21日、Xの「ツイッター速報」で「【悲報】兵庫県斎藤知事の公約実現率、脅威の98.8%」という言説が拡散し、9月25日の時点で、996万回以上の閲覧回数と6100件以上のリポストを獲得しています。)。
そして、10月20日に行われた「公開討論会」の3日後に完成した公約スライドでは、98.8%を公約の筆頭に掲げ前面に打ち出しているのです。
このような斎藤氏の態度の変遷は、SNS上での98.8%という数字の影響力に鑑み、SNS戦略を専門とする折田氏の発案で、この数字を強調しようとしたものである可能性が高く、少なくとも、斎藤氏が主体的に判断したものとは考えにくいものです。
以上のことから、スライド制作は「公約の中身ではなく、あくまでデザインの委託費」との説明に合理性はなく、実態としては、その「デザインの委託」というのは、斎藤氏が提供した公約内容のワードファイルを基に、公約スライドを作成することを折田氏に全面的に委ねたものであり、折田氏は、その構成、文字の大きさ、色使いなどにより有権者への訴求力を高めるために、様々な創意工夫を行い、また、98.8%という数字を目立たせるなどして公約スライドを完成させたのであり、同スライド制作に斎藤を当選させるための活動としての主体性・裁量性があったといえ、「選挙運動」であったといえます。
「メインビジュアルの企画・制作」
メインビジュアルとは、「ファーストビュー(最初に表示される画面領域)に含まれる大きな画像」です。
一般的には、こうした画像の撮影、制作については、候補者本人のこだわりや意向もあり、候補者の指示、もしくは候補者主導の下で協議して作成している分には「機械的労務」といえます。
しかしながら、本件では、note記事によれば、折田氏側が「コピー・メインビジュアルの一新」を提案し、実際、9月29日の折田氏側の提案資料通りのコピー・メインビジュアルの一新が行われ、斎藤氏は現在まで、その一新されたコピー、メインビジュアルを使い続けていることになります。
また、メインビジュアルを採用した理由について、折田氏は
「斎藤さんの持つ、真の強さと柔らかさをカラーで演出」
「グラフィックエレメントは須磨の海・斎藤さんご自身の人生をイメージした波線を採用」
「右斜め上に向かわせることで斎藤さんの率いる改革が進み、兵庫が躍動していく様子を表している」
などと述べており、折田氏側が考え抜いて提案しているメインビジュアルであることは明らかです。
さらに、こうしてできあがったメインビジュアルについて、折田氏は「デザインガイドブック」を作成して、全ての制作物を、それに準拠する形で制作し、選挙カーや看板を制作する業者にも配布し、折田氏により統一を図ったとの趣旨の記述もあります。
note記事を前提とすれば、折田氏の「メインビジュアルの企画・制作」業務は、「主体的・裁量的」であることは明らかであり、「選挙運動」となるため、報酬の支払いは認められないことになります。
「チラシデザイン制作」「ポスターデザイン制作」
選挙運動費用収支報告書では、「チラシデザイン制作」に16万5000円、「ポスターデザイン制作」に5万5000円の支出が計上され(支出先は「さいとう元彦後援会」)、「チラシ作成費」「ポスター作成費」については、いずれも、公費負担で「セイコープロセス株式会社」に、98万5500円、150万2550円が支払われています。
しかし、セイコープロセス株式会社同社のHPには、「チラシのデザインについて」と題して、以下の記載があります(https://www.seikoprocess.co.jp/printing/flyer/)。
《掲載したい内容がリストアップできたら、何を一番知らせたいか、の順番を決めてください。その上で、イメージしているものに近い資料や色柄、雰囲気などお伝えいただければ、弊社デザイナーが効果的なデザインに仕上げさせていただきます。》
つまり、同社にはデザイナーがいて、「弊社デザイナーが効果的なデザインに仕上げる」というのですから、斎藤氏側はポスター・選挙ビラの「デザイン」を同社に委ねることもできたはずなのです。しかも、その費用を一括して選管に請求し公費負担とすることも可能だったはずです。上記のとおりメインビジュアルが既に出来上がっており、実際に、ポスターと選挙ビラは、そのメインビジュアル画像を全面的に使用しているのであり、セイコープロセスにメインビジュアル画像を送って、あとは、同社に任せることが可能だったということになります。
note記事に書かれているように、
「紙媒体も既存の型にははめず、斎藤さんのことを分かりやすく様々な年代の県民の皆さまに届けるためにはどうしたら良いのか、仕様やサイズの異なるそれぞれの媒体でのベストをデザインチームと日夜追求した」
のであれば、セイコープロセス社に「機械的労務としてのデザイン」を含めて公費で頼むことが可能であったのに、敢えてそれを行わず、印刷だけを発注し、「ポスター」「選挙ビラ」のデザインを、別途merche社に依頼し、有権者に届ける効果的なデザインを追求したということになります。
この場合は、これらのデザインを「当選を得させる目的」をもって主体的・裁量的に行った可能性が極めて高いことになります。
斎藤氏自身の「説明」「供述」は
これまで述べきたとおり、斎藤氏の代理人奥見弁護士の説明は、公選法違反ではないとする斎藤氏の見解にできるだけ沿う主張を一方的に述べ、それに反するnote記事の内容を、事実と異なると主張するだけで、全く不合理極まりないものです。
このような代理人説明だけで、定例記者会見で質問されても、「代理人に任せている」と言って一切の説明を拒絶している斎藤氏が、被告発人として警察、検察の取調べを受けた際に、どのような供述をしているかが重要となります。
この点について、誠に不可解なのが、今年6月28日放映のTBS報道特集【問われるSNSを使った選挙運動 公職選挙法違反の分かれ目は? 斎藤氏側の説明に矛盾も…】でのTBSの取材に応じた奥見弁護士が、「知事からは全く事情を聴いていない」ことを認めていることです。
前記のとおり、昨年9月29日に、斎藤氏らがメルチュ社を訪問した際の「SNS戦略のご提案」と読める画面がスクリーンに出されているだけでなく、安野氏の都知事選の選挙総括noteも使いながら、「広報戦略のご提案」の提案が斎藤氏本人に向けて行っていたことが、客観的なnote記事掲載写真からも明らかなのですから、奥見弁護士が斎藤氏に代わって説明するのであれば、この点を含め、斎藤氏に詳しく事情を聴いた上で記者会見での説明を行うのが当然のはずです。
それらの点について斎藤氏自身は警察や検察でどのような供述を行ったのか、その点が、兵庫県知事斎藤元彦氏をめぐる公選法違反の問題の最大の焦点ということになります。
おわりに
これまで、【斎藤元彦氏公選法違反事件、「追加告発」を含め、改めて解説する】において、これまでの経緯と全体総括を行った上、【斎藤元彦氏公選法違反事件、折田氏note記事の内容と裏付け証拠を徹底分析する】で、本件の発端となった折田氏のnote記事について分析、そして、本稿で、斎藤氏側の説明・弁解を徹底分析しました。
私が7月から体調を崩し、入院中だったにもかかわらず、現時点で、今回の公選法違反の告発事件についてこのような詳細な分析記事を完成させることができたのは、冒頭の記事でも紹介したように、私の事務所の法務コンプライアンス調査室長の佐藤督が、本件に関する資料情報の取りまとめ、判例文献の収集を行い、記事の原案作成も含めて、入院中の私の活動を全面的にサポートしてくれたことによるものです。
こうして私の発信に貢献してくれている佐藤のほか、2か月にわたって代表弁護士が不在の事務所を支えてきてくれた事務所所属の弁護士である私の妻と事務所スタッフ全員に、ここで改めて謝意を述べたいと思います。
すでに登録済みの方は こちら