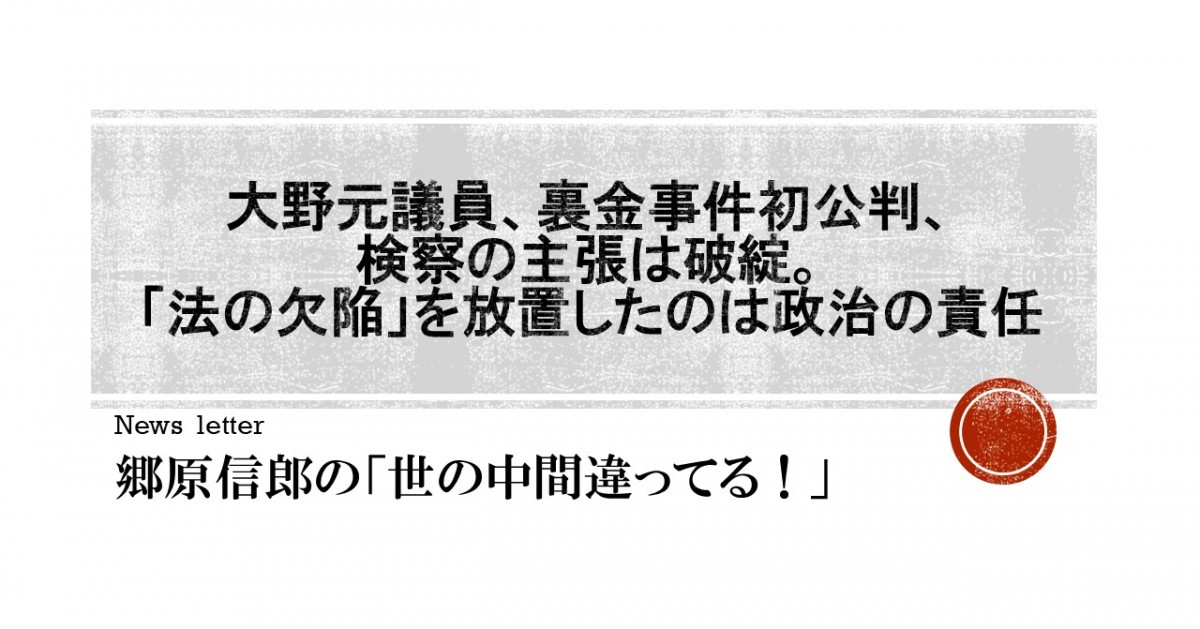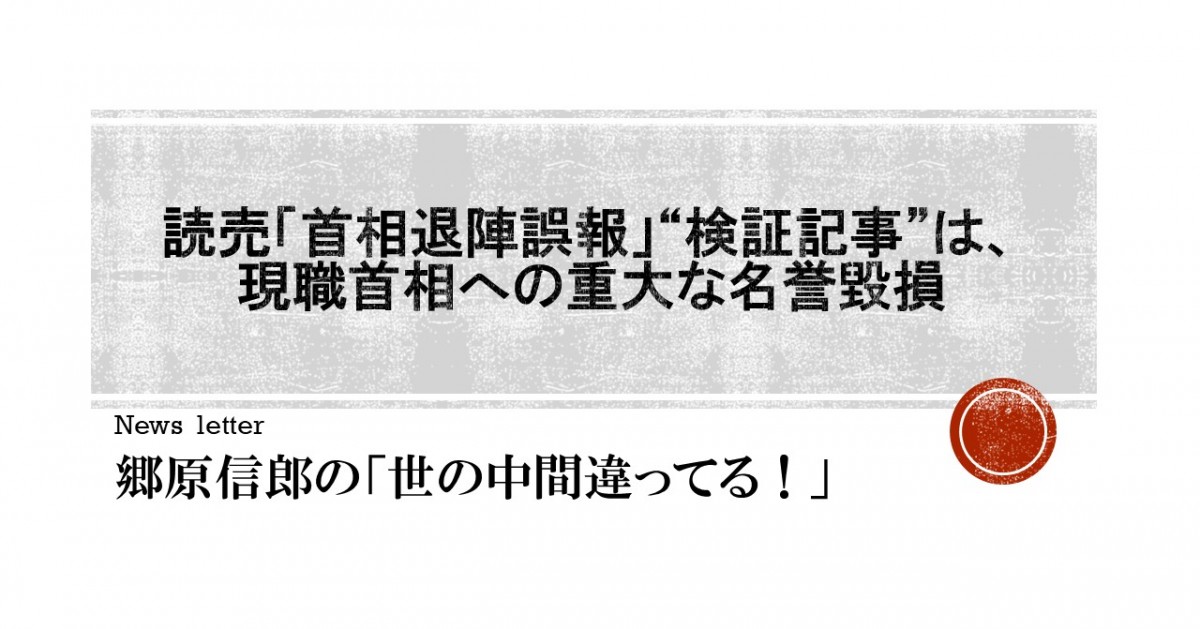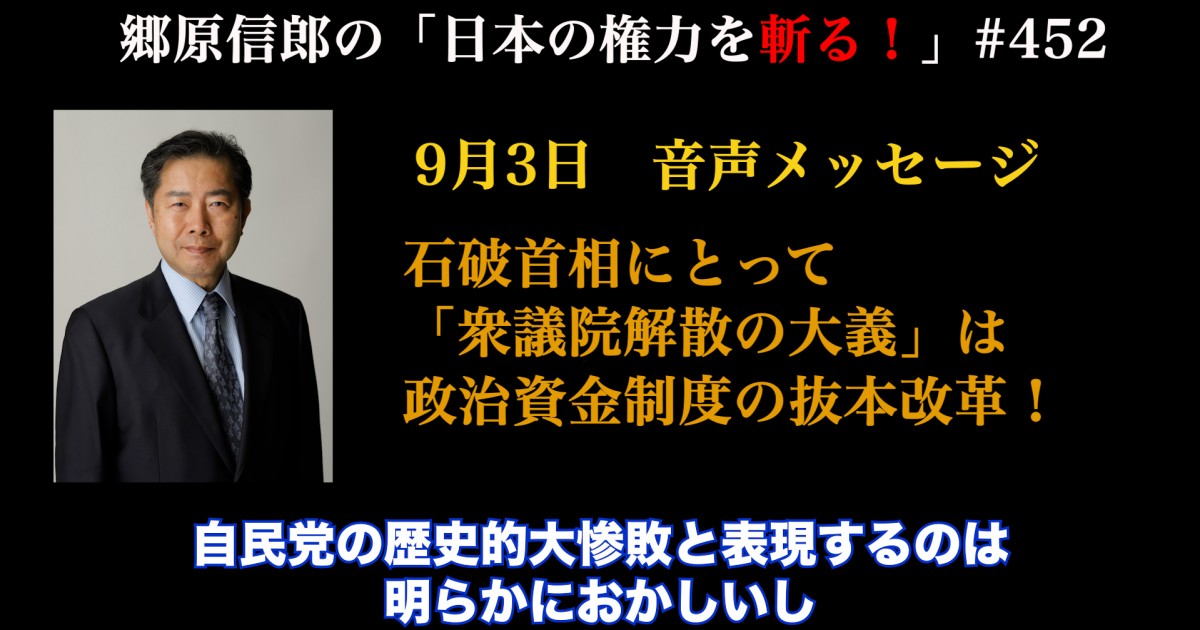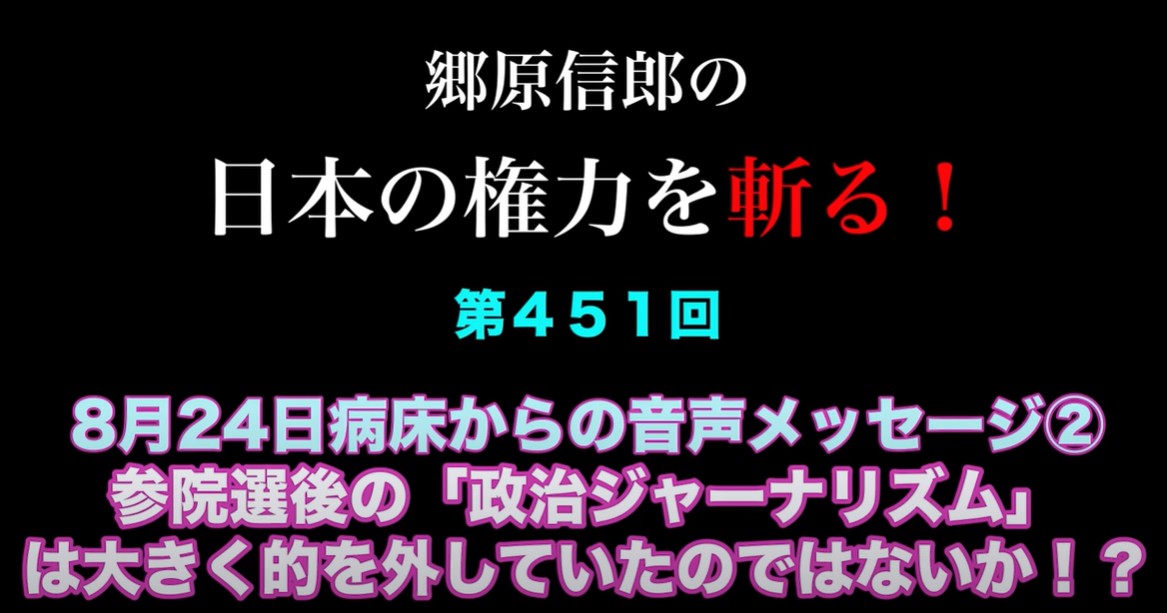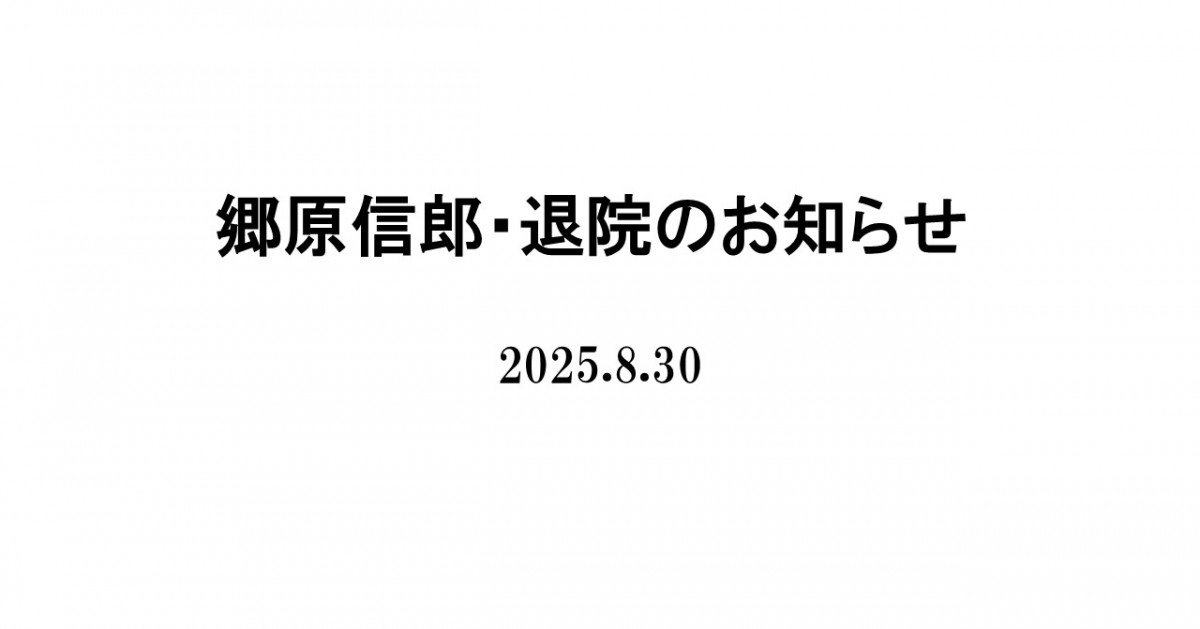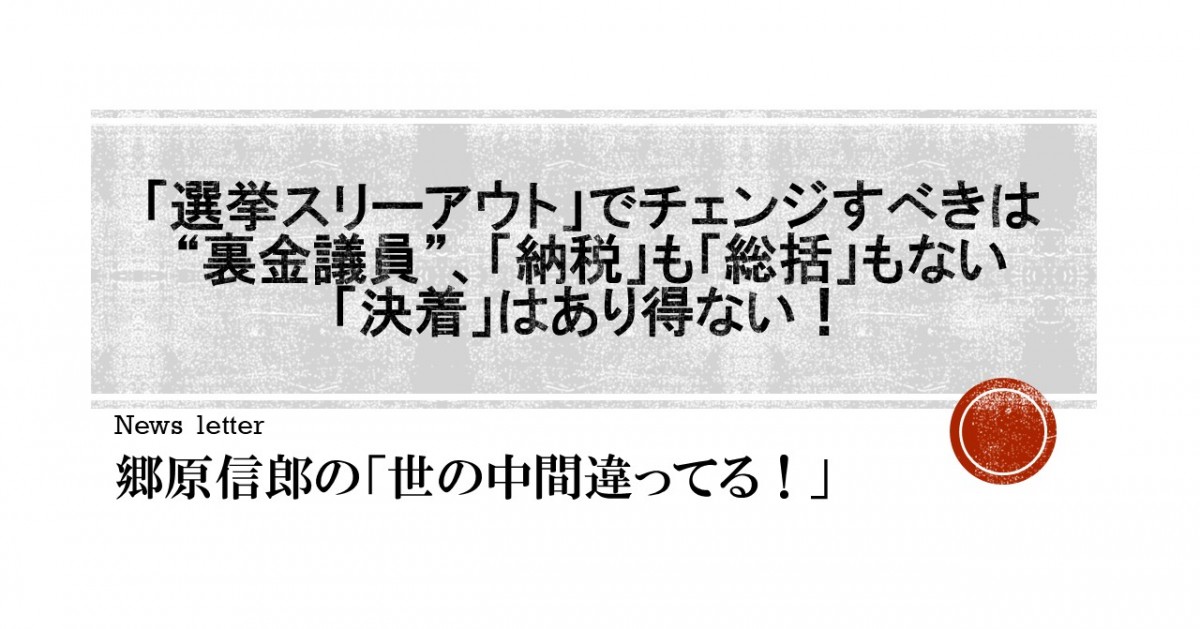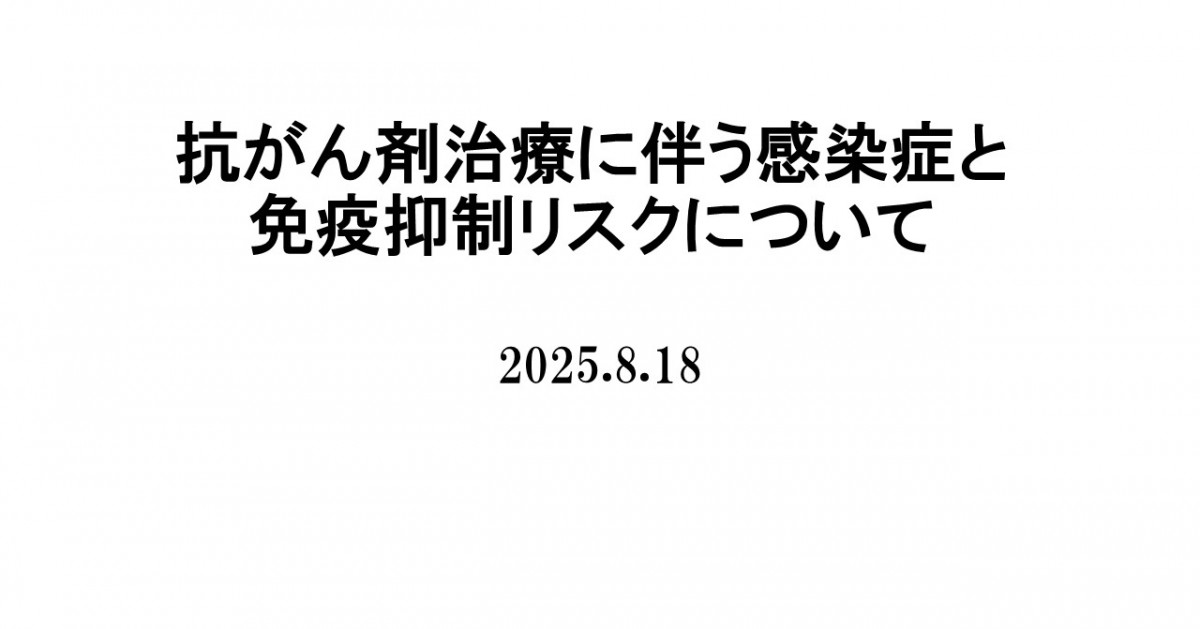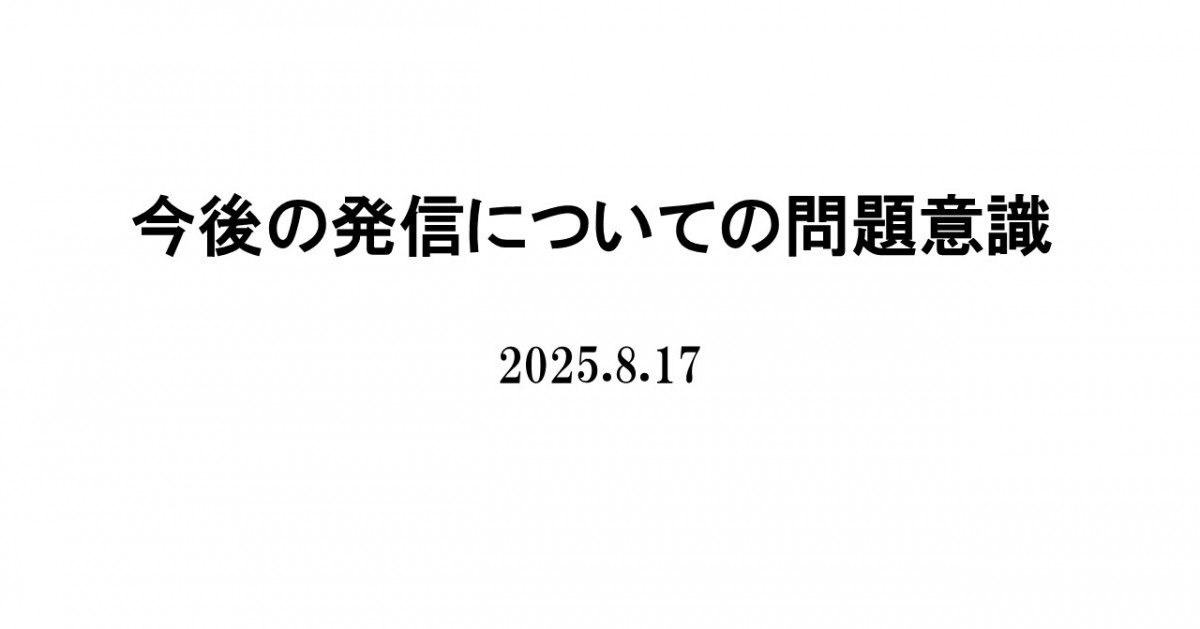「石破降ろし」に正当性なし。読売「現職首相ウソつき」批判“検証記事”は総裁選前倒しに重大な影響
参院選後の「石破降ろし」最終的に実現
9月8日に行われる自民党総裁選の前倒しの意思確認の手続きが進み、賛成意見が過半数を超える可能性が高まる中、石破首相は辞任する意向を固め、7日午後6時から首相官邸で記者会見を行い、総理大臣辞任の意向を表明しました。
自動車関税を25%から15%に引き下げる大統領令署名が実現し、アメリカの関税措置をめぐる対応に区切りがついたことを理由として挙げましたが、前日の官邸での会見で、それは進退の判断に影響しないことを明言していたので、会見の最後で述べた
「自民党の臨時の総裁選挙を実施するかどうか意思確認を行えば、党内に決定的な分断を生みかねず、まだまだやり遂げければならないことがあるが苦渋の決断をした。このような形での辞任について国民の皆さんにお詫びをしたい」
というのが石破首相の真意であることは明らかです。
自民党議員、都道府県連の賛成多数による総裁選前倒しという自民党で初の手段が現実化したことで、7月の参議院選挙後から自民党内やマスコミで続いた「石破おろし」が、最終的に成功し、石破氏は、自民党総裁・総理大臣の職から引きずり降ろされることになりました。
一貫して続投の意思を表明してきた石破首相が、最終的に首相の地位を失うことになった原因の一つに、読売新聞による、戦後の政治史・報道史に重大な汚点を残す最悪の「暴挙」がありました。
読売新聞などが「石破首相退陣へ」の大誤報を行った直後の7月27日の【読売新聞(毎日新聞)の「石破首相退陣へ」誤報は、戦後最大の報道不祥事~自民党石破総裁は厳正な抗議を!】で述べたように、この報道は、「石破首相の意向」という内心を述べた記事なので、その本人が明確に否定した以上、客観的事実と異なっていたことは明白で、その根拠は失われました。
その報道を訂正し、謝罪することになるのが当然だったのに、号外と翌日の朝刊であえて大々的に報じました。しかも、その後も読売新聞は、「石破首相退陣へ」報道をそのまま維持し、それとの整合性を保てるよう、自民党内の石破おろしの動きの強まりを報じ、一方で、石破首相サイドも事実上続投は困難と判断し退陣表明の時期を探っているかのように報じ続け、まさに、「石破おろし」を露骨にめざす報道を続けてきました。
そして、読売新聞は、9月3日の両院議員総会後に総裁選前倒しの意思確認手続が開始された直後、「石破首相退陣誤報」の「検証記事」と称して、「偽装」「捏造」に近いやり方で「石破首相退陣報道」の誤報を正当化し、《石破首相が公式には「続投の意思は全く揺れたことはない。退陣の意向について発言したことも一度もない」と一貫して述べていること》が「虚偽説明」だとして批判し、現職首相を「ウソつき」呼ばわりし、総裁選前倒しの意思確認を控えていた自民党議員や各県連にも影響を与えようとしました(【読売「首相退陣誤報」“検証記事”による「虚偽説明」批判は、現職首相への重大な名誉毀損】)。
「退陣誤報」文春記事にも謝罪要求、法的措置を示唆
読売新聞の「検証記事」に対して、江川紹子氏等がXで批判しているように、社会部系の有識者、ジャーナリストの殆どは、「検証記事とは言えない単なる言い訳」と批判的です。
一方で、政治学者の中北浩爾中央大学教授などは、この「検証記事」を報じる朝日新聞記事のコメントで
《石破総理は自民党総裁選のなかで「勇気と真心をもって真実を語る」と繰り返し述べました。読売新聞の検証記事が事実であれば、嘘を言っているということになります。》
などと、読売の偽装検証記事に完全に乗せられてしまっています。
参議院選後、石破内閣の支持率は回復し、世論調査の結果も、減税を強く求める参政党、国民民主党等の支持者は別として、それ以外の国民からは「石破氏は辞任する必要はない」との声が大きくなっています。それにもかかわらず、自民党内では石破おろしの動きは収まらず、総裁選前倒しをめぐって各都道府県連も多くが前倒し賛成に傾くという、「国民の世論と党内世論の乖離」が生じました。
今回、「石破おろし」の最終手段となった総裁選前倒しの意思確認は、賛成の国会議員に記名した書面を提出させ、それを公表するというやり方でした。この場合、賛成の判断を表明する判断において重要だったのは、賛成が過半数を上回り総裁選前倒しが実現されるかどうかの見通しだったはずです。もし過半数に届かず石破総裁体制が継続した場合には、党のトップに反旗を翻したことによる人事や選挙での非公認などの不利益も懸念されるはずです。一方、賛成が過半数を上回り前倒し総裁選が実施されて石破総裁は交代する、ということになれば不利益を受ける懸念はなくなります。
そういう意味で、日本最大の発行部数を誇る読売新聞が「石破おろし」に加担する一大キャンペーンを行い、総裁選前倒しの意思確認が始まった9月3日の直後に、石破退陣報道の「検証記事」と称して、石破首相の「虚偽説明」「ウソつき」批判を紙面で大々的に行ったことは、総裁選前倒しへの賛成の意思表明を行うかどうか悩んでいた国会議員にとって、さぞかし心強かったことでしょう。
もともと、国民世論と自民党の党内世論との乖離が生じる状況に至っていたことに加えて、「退陣誤報」報道を結果的に正しいものにしようとして「石破おろし」に加担する読売新聞の「反石破報道」が、最終的に石破首相を退陣に追い込むことに大きく寄与したことは紛れもない事実です。
石破政権の成果・世論と乖離する自民党内世論
このような読売新聞による首相退陣に関する一連の「石破おろし」キャンペーンと、その中で行われた誤報検証記事に藉口した「虚偽説明」による石破首相批判は、重大な名誉毀行為であり法的責任は免れません。
もっとも、7月の参議院選挙後から、読売新聞に限らず他のマスコミも含めて圧倒的だった「自公過半数割れで民意が石破政権を否定したのですから、石破首相は退陣するのが当然」というような論調が、仮にその考え方が絶対的に正しく、それを受け入れない石破首相の続投は「狂気の沙汰」だと言えるのであれば、それを阻止するための読売の動きもそれなりに正当化する余地があることになります。
そこで、今回の参議院選挙の結果を受けた「石破首相退陣当然視論」の根拠と、それが果たして合理的なものであるか、という点をまず考えてみることとしたいと思います。
「石破首相退陣当然視論」の根拠は、二つに整理できます。
一つは、「参議院選の敗北の結果で民意が示されたのだから首相退陣は当然だ」という考え方、もう一つは「組織のトップとして敗北の責任を取ってケジメをつけるのが当然だ」という考え方です。
前者は、民主主義制度における「選挙での民意の受け止め方」の問題、後者は政党という組織のガバナンスの問題だといえるでしょう。
参院選で「石破政権を否定する民意」が示されたのか
では、今回の参議院選挙の結果は、本当に「民意が石破政権を否定した」と受け止めるべきなのでしょうか。
日本は、衆議院議員内閣制をとっており、衆議院議員の多数から支持されて総理大臣が指名され組閣を行います。その総理大臣が所属する党が選挙で敗北し、衆議院で他党の議員が多数を占めることになれば、新たな議員が首班指名され、総理大臣は地位を失います。
しかし、総理大臣が、所属する政党の総裁・代表の座を失うとは限りません。政権を失った政党が、その後誰をトップにしていくのかは、政党内部で議論して決めることです。
衆議院選挙でも、敗北が直ちに党のトップの交代につながるとは限りません。参議院選挙の場合は、そもそも制度的には政権選択のための選挙ではなく、二院制の下で衆議院とは異なった役割を果たす参議院議員として誰がふさわしいか、どの政党の候補者がふさわしいかを選択するための選挙です。与党過半数が必達目標とされていたとしても、それが達成できなかったという結果だけから、首相は直ちに退任すべき、ということにはなりません。
もっとも、参院選と言えども、極端な形の敗北で、それが、その政党の支持が決定的に失われたことを示すものであれば話は別でしょう。その場合は、何らかの抜本的対策を講じない限り、その次の選挙でも同様の民意が示されることが確実だからです。
では、今回の参院選での敗北が、「石破総裁が辞任するのが当然」というべき結果であったのでしょうか。
今回の選挙後の報道は「自民党の歴史的惨敗」で埋め尽くされました。「歴史的」というのは、過去にない程の「大惨敗」という意味でしょう。
しかし、歴史的には、宇野宗佑首相が1989年の参院選で69議席から36議席に「33議席減」、第一次安倍政権での2007年の参院選では、自民党は62議席から37議席に「25議席減」という過去の「大惨敗事例」があり、 52議席から39議席への「13議席減」という今回の参院選の結果は、決して「歴史的惨敗」とは言えません。
2007年参院選では、それまで衆参で安定多数を占めていた自公両党が、参議院で過半数を大きく割ったことで、当時、民主党と「二大政党対立」の状況だったことから、国会のねじれによって、法案の不成立、同意人事の拒否などの大きな政治的影響が生じました。
しかし、このような参院選大敗北で自民党に壊滅的な影響を及ぼした時ですら、当時の安倍晋三首相は引責辞任を拒否し、1か月半後に政権運営に行き詰まり、体調不良を理由に首相を辞任しました。そしてその2年後の衆院選で自民党は大惨敗し、民主党に政権を明け渡しました。
今回は、参院選の前からすでに、衆議院では少数与党となっており、参議院でも過半数を下回ったことで政権運営の難度は変わるものの、国会での野党との調整、連携が必要であることに変わりはありません。
自民党総裁として掲げた「与党で過半数」の必達目標が3議席達せられなかったのは事実です。しかし、従来は組織票で安定的に議席を確保してきた公明党が「6議席減」という想定外の結果だったことが大きく影響しており、しかも、「3議席の未達」であれば、保守系無所属などを含めれば、なんとか過半数を確保できる可能性もあります。
今回の参院選は、既存政党が参政党などの新興勢力に敗北したということであり、その背景に消費税減税等の積極財政を求める世論があります。財政規律を重視する既存政党の敗北は、立憲民主党・公明党等も同様であり、自民党だけが敗北したのではありません。このような参院選の結果を、「歴史的惨敗で、石破政権を否定する民意が示された」というのは、あまりに短絡的であり、選挙結果を客観的にとらえたものではありません。
「結果責任」重視の自民党組織のガバナンス
しかし、自民党内での「石破首相退陣当然視論」は、「参院選で民意が示された」というだけでなく、「組織のトップとして敗北の責任を取ってけじめをつけるべき」という意見の方が中心です。それは、組織のガバナンスの問題だと言えます。
その点に関して聞かれたのが、
「企業経営者でも3回連続赤字を出したら辞任するのが当然」
「結果に対してはトップが責任を負うべき」
という「結果責任」を重視する声でした。
「結果責任」とは、結果に対して負うべき責任で、それに対して、目標達成のために組織をまとめたり問題に対応したりするのが「遂行責任」です。
上場企業であれば、経営者は、株主に対して利益を実現する責任を負います。会社に損失を与え続ければ、その株主に対する責任をとって辞任というのも当然の対応です。
しかし政党の場合、トップが負う責任はそのように単純なものではありません。選挙で国民の支持を得るとともに、その支持を活用して党の政策を実現する。そして、政権を担う政党であれば、国政を安定的に運営して行く責任を負う。このような複雑な責任を負う政党、とりわけ政権与党のトップの責任を、単純な「結果責任」で考えることはできないはずです。むしろ「遂行責任」を中心に考えることの方が政党にとっては合理的なはずです。
昨年9月の総裁選で石破氏が自民党総裁に就任、直後の衆院選は、当時の政治資金パーティー裏金問題への批判からは当然の結果とも言える自民党敗北でした。その結果、少数与党となったものの、石破首相は、弱い党内基盤の下で何とか党内体制を維持し、野党との協力も得ながら予算・法案を成立させ、コメ大幅増産の方向への農政改革を打ち出し、参院選直後にはEUなどにも先がけてトランプ関税を25%から15%に引き下げる合意に成功しました。石破政権は、今後、本格的に石破カラーを出して政権を運営していくべき時でした。遂行責任を果たすという面ではこれからが本番だったといえます。
ではなぜ、自民党内ではこの「結果責任」中心の単純な考え方がまかり通るのでしょうか。そこには組織の根幹に、勝ちと負けを峻別し、負ければ潔く腹を切って責任を取る、というような旧来日本型組織の単純な考え方があるのでしょう。上位者には、結果を出すまでのプロセスについて「言い訳」せず、表面的な潔さだけが評価される、そのような背景の下で、日本の政党の中心であった自民党で、「結果責任」中心の考え方が当然視されてきたということではないでしょうか。
しかし、それは、55年体制の下で政権基盤が安定し、その政党のトップである自民党総裁選が「最大の政治上の決戦」だった状況には通用しても、現在のように国民の要請も民意も複雑多様化し、それに応じて多党化時代を迎えた情勢の下では全く通用しません。そもそもここで石破おろしを実現して自民党総裁が交代したとしても、その存在は直ちに首班指名を受けるわけでもないし、野党との関係でどのような協力ができるのかも不明です。
そのような状況において、自民党がいったん正式手続の総裁選で3年という任期を石破首相に委ねたのであれば、まず党内基盤、政権基盤を安定させるための期間に1年を費やし、そこから石破政権として本格的に「遂行責任」を果たす段階に入るというのが合理的な考え方であり、国民もそれを期待していたはずです。
実際に連立内閣が常態化しているヨーロッパ各国では、国政選挙後の連立の枠組み協議に半年、一年を要することも珍しくないと言われています。
このように考えると、今回の参議院選挙結果を受けての「石破首相退陣当然視論」には根拠がなく、そういう誤った考え方を前提に「石破おろし」に加担し、「反石破報道」を行ってきた読売新聞には、何の正当化の余地もないと言うべきです。
「石破おろし」が実現した場合の「名誉毀損訴訟リスク」
【前掲記事】で述べたように、今回の「検証記事」での石破氏個人に対する「虚偽説明批判」が重大な名誉毀損であることは明らかです。それについて、実際に被害者の石破氏から名誉毀損訴訟を提起された場合、読売新聞が検証記事で批判した石破氏の「虚偽説明」について真実性を証明することも、「真実であると信じることについての相当な理由」も示すことも、困難です。
たとえ、「検証記事」で「周辺者の話」とされているのが、「石破氏と親しい記者がオフレコで聞いた話」だったなどということだったとしても、【前掲記事】で述べたように、そもそも、「石破氏の発言」の趣旨の取り違え、あるいは意図的な捻じ曲げが誤報の原因なので、「石破氏が虚偽説明をした」と報じる根拠になるものではありません。
石破首相が、現職の総理大臣である限り、そのような権力者が報道機関に対して名誉毀損訴訟を提起することは現実には考えにくいことでした。しかし、読売新聞も深く関わった「石破おろし」によって、石破首相が首相の座から引きずり降ろされることになり、一政治家の立場になるのです。一国の総理大臣を「噓つき」呼ばわりして名誉を毀損したという「前代未聞の報道犯罪」について法的責任追及を行う選択肢も、石破氏にとって十分にあり得ます。
文春VS読売新聞
この「石破首相退陣誤報」問題に関してはその後、週刊文春による報道と、それに対する読売新聞側の対応がありました。
8月19日に【石破首相強気のウラに読売の“謝罪”があった!】と題する記事が週刊文春の電子版で配信され、20日発売の同誌に掲載されました。同記事で
《グループ本社の山口寿一社長が、今月上旬、石破首相と面会し、首相の退陣報道について「謝罪の意を表明した」としたうえで、「政治部はアンタッチャブルで、自分では制御がきかなかった」と釈明した》
と述べたことに対して、読売新聞は、
「事実無根の記事で名誉が著しく毀損された」
として、抗議書を発行元の文芸春秋に送付し、謝罪と記事の取り消しを求めたとする記事(【本社、週刊文春に抗議書…退陣報道「首相に謝罪の事実ない」】)を8月19 日読売新聞電子版で配信しました。
さらに、上記の「検証記事」を出した直後に【本社、週刊文春に抗議書…「悪意ある虚偽の記述多数」】と題する記事を電子版に掲載し、
《(文春記事は)「全体として 捏造 ねつぞう 」と強調。特に、首相の言葉に関する報道は「取材メモの内容が社外に流出したとの誤解を強く読者に与える点で著しい名誉毀損」だと指摘した》
などと、文春への法的措置も辞さない、全面対決の姿勢を見せています。
「誤報への対応」は、読売グループ山口社長主導か
これらの文春記事への読売新聞の対応は、首相退陣報道が、明白な誤報で、ただちに訂正し、石破首相に謝罪すべきであることを真っ向から否定するものです。文春報道の当事者は「石破首相に直接謝罪した」と書かれた山口寿一読売グループ社長自身であり、そのような方針で臨むことが山口社長の方針だからこそ、文春側に謝罪と記事の取り消しを求めるという対応を行ったのでしょう。
「石破首相退陣へ」の誤報は、政治部マターであり、文春記事で書かれているように、社会部出身の山口社長にとっては、
「政治部はアンタッチャブルで、自分では制御がきかなかった」
というのは、(文春記事のとおり石破首相に直接会って謝罪した事実があったかどうかはともかく)、少なくとも山口社長の「本音」であった可能性が高いと考えられます。
しかし、そのような文春記事に対して、発行元の文文藝春秋社に抗議書を送付し、謝罪と記事の取り消しを求め、それを自社の記事で表に出したのが、当事者の山口社長の意向に基づくものであることは明らかで、この時点で、「石破首相退陣へ」の誤報問題も、山口社長マターになったはずです。
それに加えて、読売新聞では、社会部でも重大な誤報問題が発生し、そのことも、一連の「誤報」問題への山口社長の関与を一層強めることになったと考えられます。
8月27日朝刊1面「公設秘書給与不正受給か 維新衆院議員 東京地検捜査」の記事で、東京地検特捜部の捜査対象者を取り違え、日本維新の会の石井章参院議員ではなく、同党の池下卓衆院議員について秘書給与不正受給の疑いで捜査が進んでいるとの重大な誤報を、一面トップで掲載したのです。
「取材経緯の検証を行った結果、最初の取材で担当記者に思い込みが生じたうえ、キャップやデスクも確認取材が不十分だったことを軽視し、社内のチェック機能も働いていなかったことが誤報につながった。」
として、9月5日付で記事を訂正・謝罪し、前木理一郎専務取締役編集担当と滝鼻太郎執行役員編集局長について役員報酬・給与のそれぞれ2か月30%を返上する処分、小林篤子社会部長を罰俸とし更迭、当日の編集責任者だった編集局デスクをけん責、社会部のデスク、司法記者クラブキャップ、担当記者をいずれも出勤停止7日とするとの社内処分を発表しました。
これにより、読売新聞は、ほぼ同時期に政治部と社会部という報道局内の主要な2つの部で「重大な誤報」問題が発生したことになります。読売新聞の会社組織自体の問題です。
山口社長の本来のテリトリーである社会部でも誤報問題が発生したことによって、一連の「誤報問題」への対応は、山口社長の判断で決まる問題になったはずです。
今回、「退陣報道は、石破首相も含めて十分な取材に基づくもので、首相本人の虚偽説明のために『騙された』結果、誤報になってしまった」という「検証記事」を出すことについても、山口社長の方針が示され、その方針に合わせたのでしょう。
石破首相を「虚偽説明」「ウソつき」と批判し、自民党議員や都道府県連等の批判を高めて総裁選前倒しを実現させて石破首相の「追い落とし」の成功につながれば、「勝てば官軍」で「検証記事」の問題が深刻な事態を招くことはない、というのが山口社長の見通しだったのかもしれません。
しかし、それは、石破首相「追い落とし」が成功し、石破氏が一人の「元総理」となり、権力を失った「一政治家」となった場合には通用しません。
読売新聞による「反石破報道」と「検証記事」による「現職首相ウソつき批判」は、名誉毀損の重大な法的責任を負うリスクを孕みます。日本最大の発行部数の新聞社は、なぜ「政治報道犯罪」に手を染める存在に成り下がってしまったのでしょうか。
すでに登録済みの方は こちら