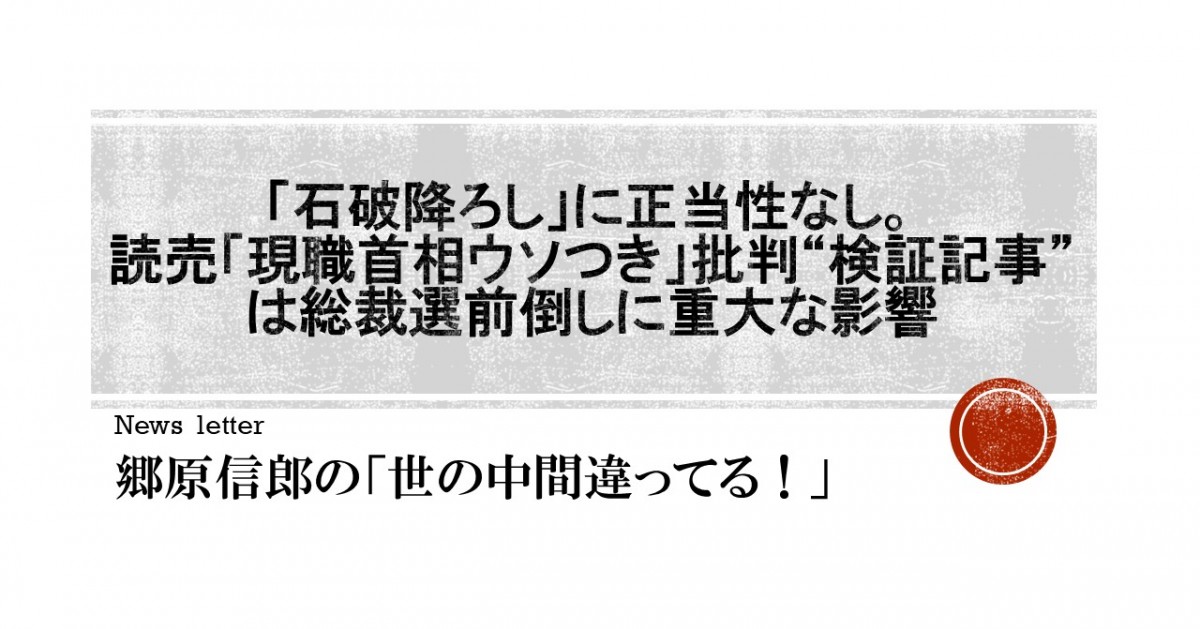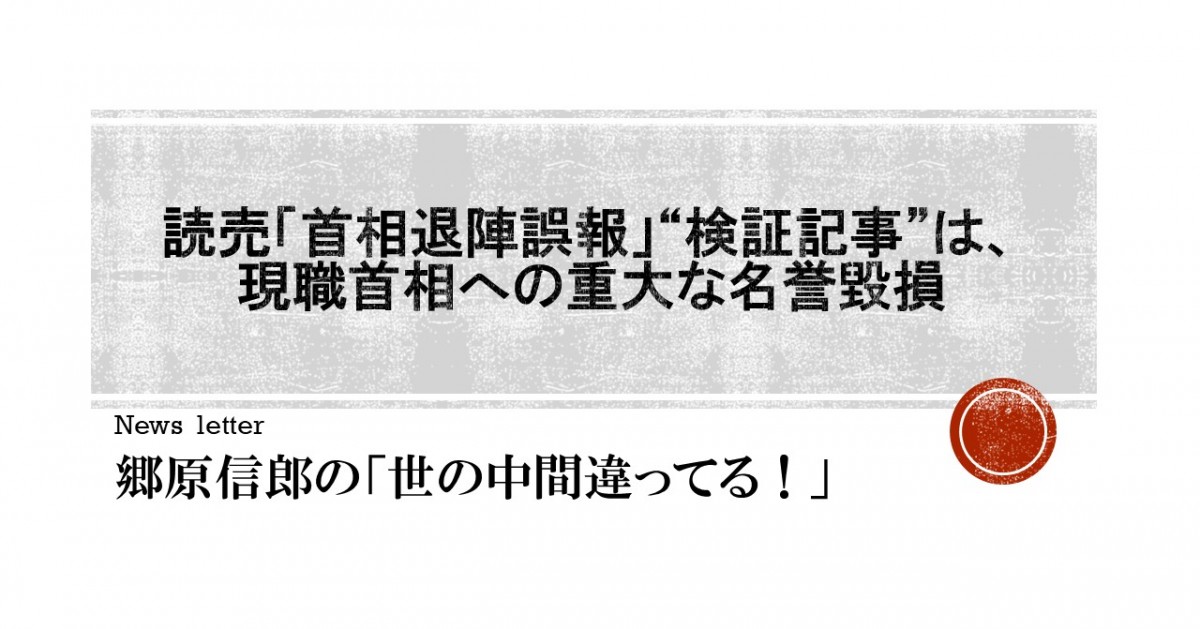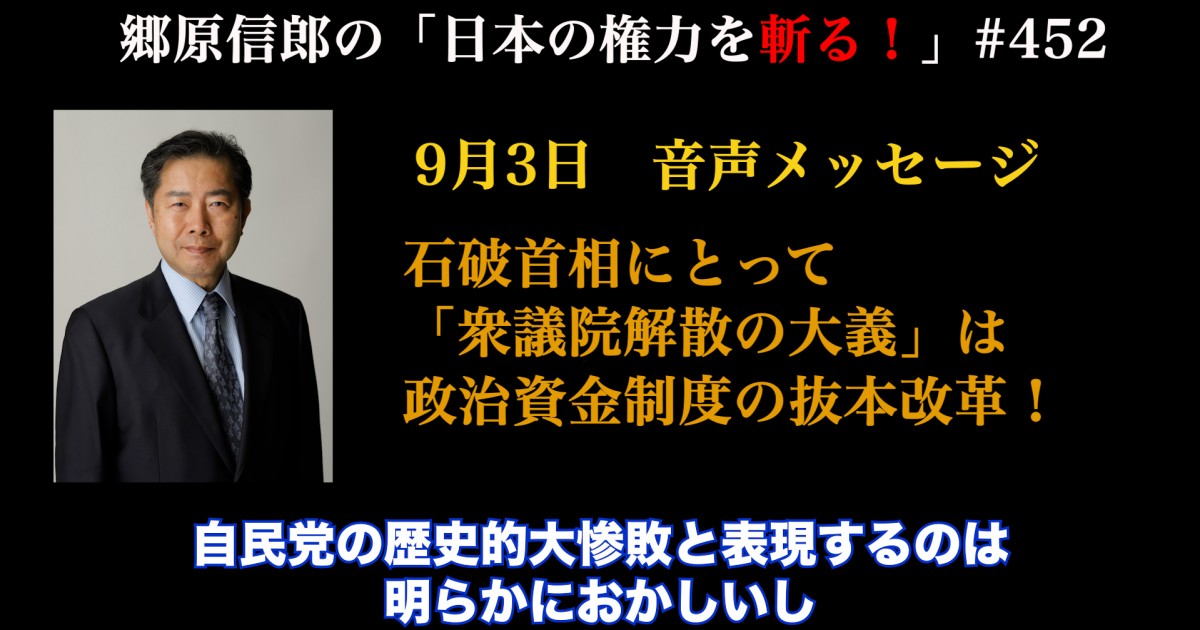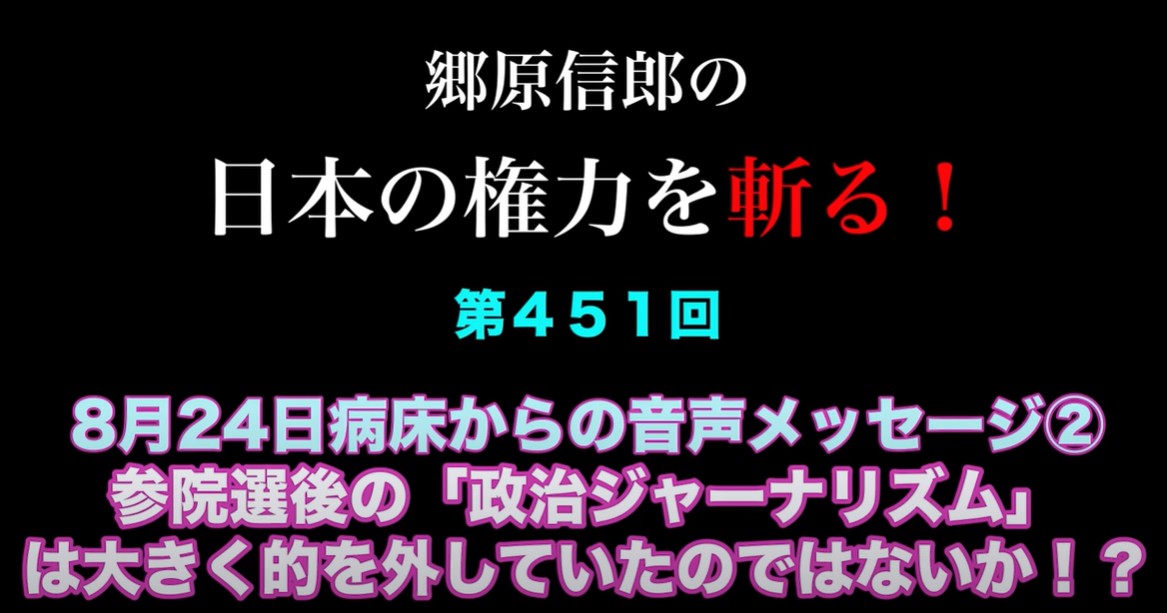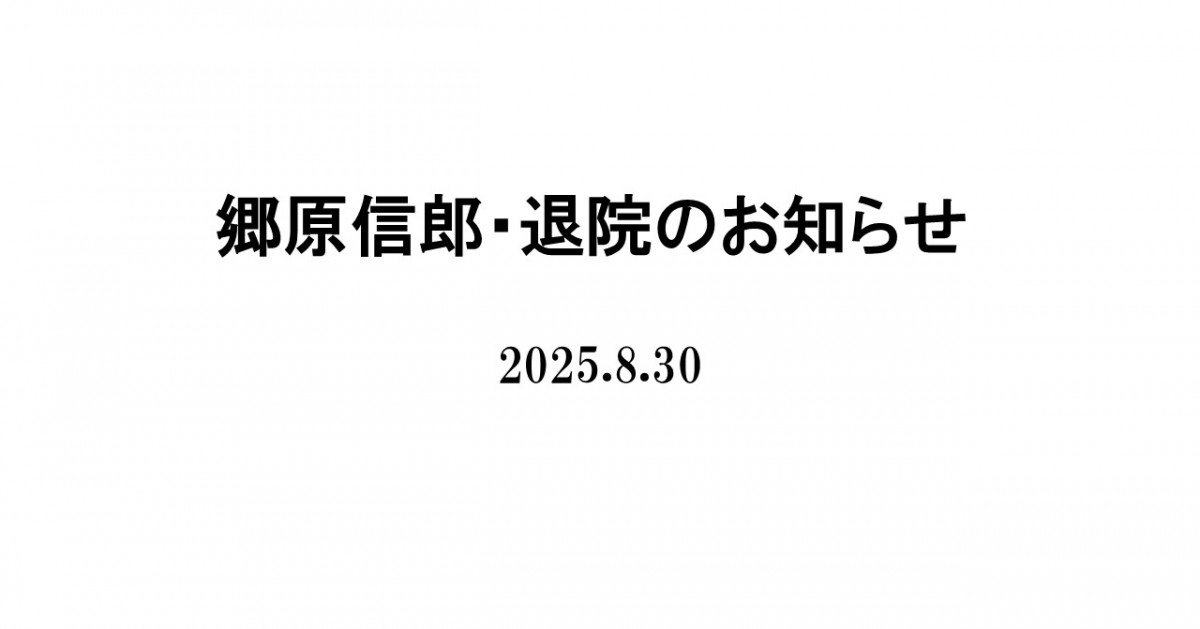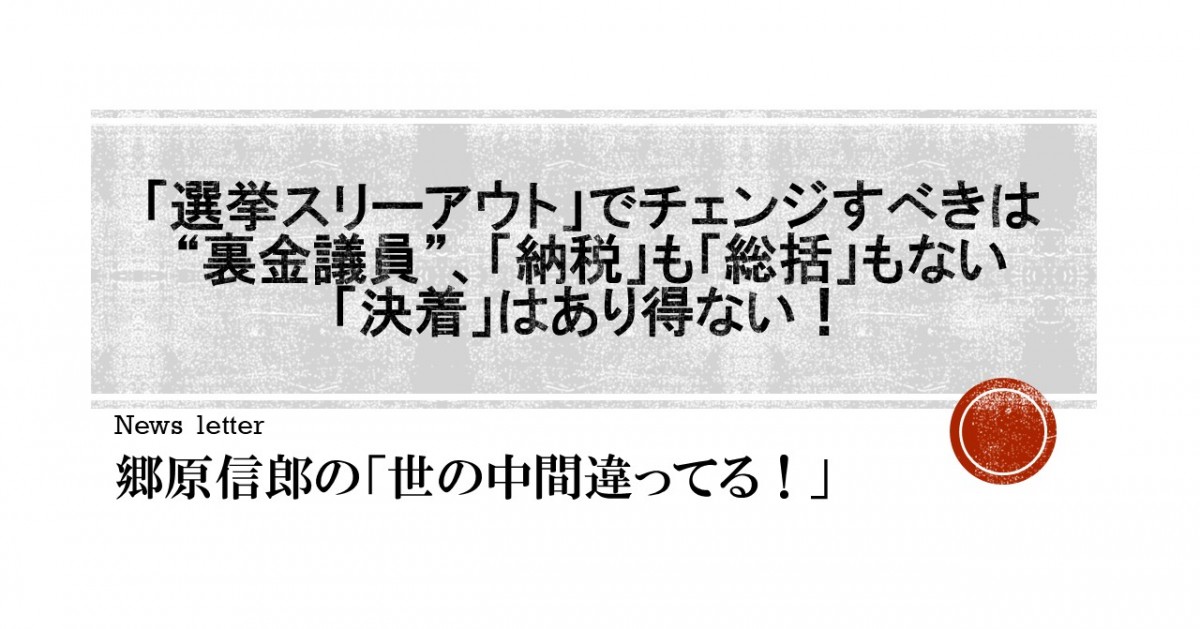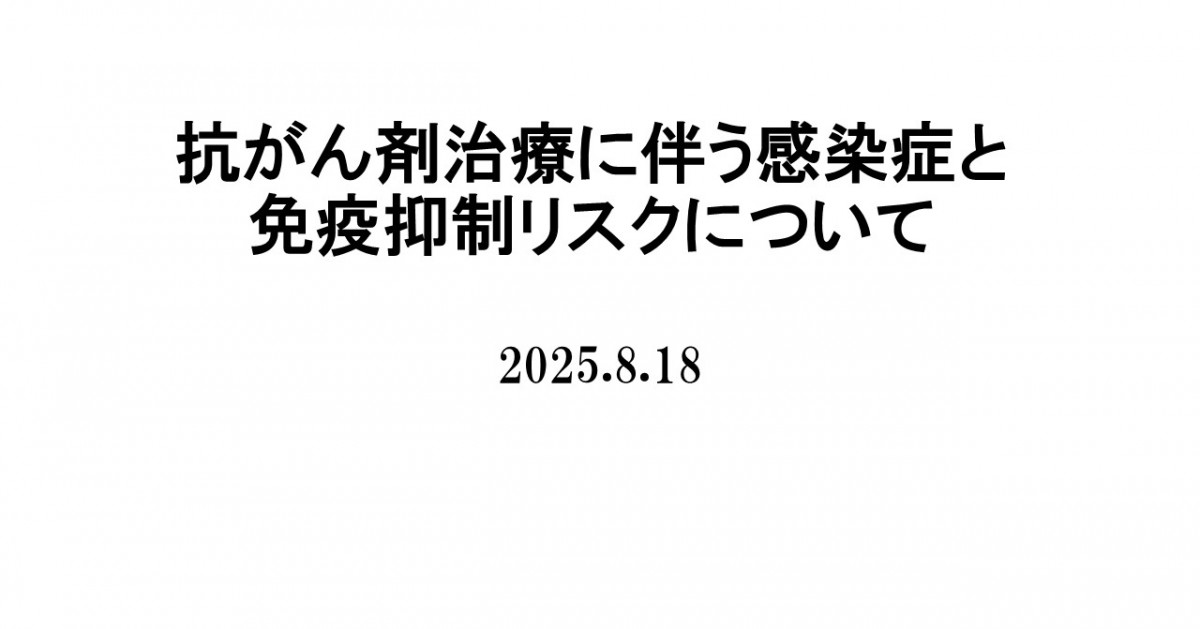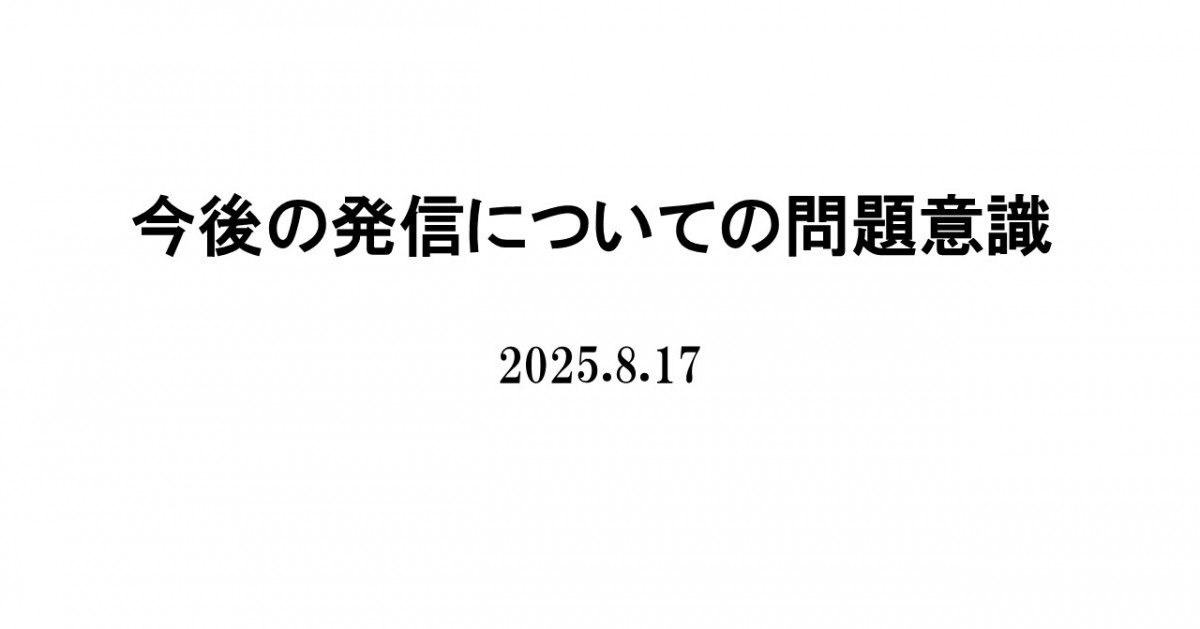大野元議員、裏金事件初公判、検察の主張は破綻。「法の欠陥」を放置したのは政治の責任
自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で初めて、政治家の刑事公判が始まりました。
旧安倍派(清和政策研究会、以下「清和会」)に所属していた元参院議員の大野泰正氏と、その元秘書の岩田佳子氏が政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われ、その第1回公判が10日、東京地裁で開かれました。
大野元議員と岩田元秘書は、
自民党派閥「清和政策研究会」から還流された政治資金パーティーの収入を、資金管理団体「泰士会」の収支報告書に、寄付収入として記さなかった
として起訴されましたが、大野氏は
「虚偽記載について共謀など一切していない。私は無罪を主張します」
と述べて起訴内容を否認、岩田氏は、
「派閥からの寄付と認識していなかった」
として無罪を主張しました。
検察側は冒頭陳述で、大野元議員の事務所では、派閥へ支払う秘書会費や派閥から年に2回受け取る50万円ずつの寄付(いわゆる氷代・餅代)など、派閥関連の収支は、大野氏が代表となっているいくつかの資金管理団体のうち、「泰士会」に計上されていたと指摘。こうしたことから2人が、還流された資金を派閥から「泰士会」への寄付として記すべきだという認識があった、と主張しました。
これだけを見ると、「東京地検特捜部が世間の喝采を浴びて腐敗政治家を摘発して起訴し、ようやくその刑事裁判が開かれた。政治家は、秘書にすべてを任せていたと言って認識や共謀を否定する見苦しい言い訳をする。しかし、検察側は、充分な証拠に基づいて有罪立証に自信を見せた」というお決まりのパターンのように思えます。
しかし、大野氏と岩田氏の刑事裁判はそのような一般的な政治家の事件とは大きく異なります。
「ザル法」の真ん中にあいた“大穴”
現行政治資金規正法には、収支報告書に記載しない前提で政治家個人に提供される『裏金』の処罰が困難だという問題があることを、2023年に公刊した【“歪んだ法”に壊される日本 ~事件・事故の裏側にある「闇」】の第2章「「日本の政治」がダメな本当の理由~「公選法」「政治資金規正法」の限界と選挙買収の実態」で、「「ザル法」の真ん中にあいた“大穴”」と題して指摘してきました。
そして、2023年12月、政治資金パーティー裏金問題が表面化した当初から、ネット記事(【日本の法律は「政治家の裏金」を黙認している…「令和のリクルート事件」でも自民党議員が逮捕されない理由】)や、一部メディアへの出演などで繰り返し指摘してきました。
「裏金の授受」は、受領した事実を記載しない収支報告書を作成・提出する行為が不記載罪・虚偽記入罪等となるのであり、その授受自体が犯罪になるのではありません。
国会議員の場合、個人の資金管理団体のほかに、自身が代表を務める政党支部があり、そのほかにも複数の関連政治団体があるのが一般的です。つまり、一人の国会議員にとって「財布」が複数あることになります。
それぞれの「財布」について、会計責任者が収支報告書を提出する義務はありますが、裏金というのは、領収書も渡さず、いずれの政治資金収支報告書にも記載しないことを前提にやり取りするものであり、通常は、複数ある議員の関連政治団体のうち、どの団体に帰属させるかは考えません。
ノルマを超えた派閥パーティー券収入の還流は、銀行口座ではなく現金でやり取りされ、収支報告書に記載しないよう派閥側から指示されていたとされてます。議員側は、どの政治団体の収支報告書にも記載しない前提で、「裏金」として受け取り、そのまま、どの収支報告書にも記載しなかった、ということです。そうであれば、どの収支報告書に記載すべきだったのかが特定できない以上、(特定の政治団体等の収支報告書の記載についての)虚偽記入罪は成立せず、不可罰ということになります。
パーティー券のノルマ超の売上の還流金について、政治資金規正法の収支報告書の不記載・虚偽記入で処罰することが困難であることは、現行の政治資金規正法からすれば、そのような結果になるのは致し方ないのです。
ところが検察はそのように裏金を受領した議員を、収支報告書の虚偽記入罪などで処罰することは困難なのに、金額が大きかった大野氏、池田佳隆氏、谷川弥一氏の3人について政治資金規正法違反で起訴したのです。谷川氏の場合は、略式命令を受け入れ、違反を全く争わなかったのでそのまま決着しましたが、公判請求された大野氏と池田氏については、検察の公判立証は極めて困難であり、なかなか裁判が始まらないのも検察が立証に行き詰まっているからではないかと指摘していました。
「政治資金の帰属」に関する弁護人と検察官の主張
今回の大野氏と岩田氏の公判での弁護側冒頭陳述でも、当然のことながら、清和会からの還付金は検察が主張するような「泰士会」宛ての寄附ではないという「政治資金の帰属の問題」に関する主張が含まれています。大野氏の政治資金の「財布」には、資金管理団体の「泰士会」のほかに、大野氏が代表を務める「自由民主党参議院岐阜県第三支部」(以下、「第三支部」)があり、「政治資金収支報告書に記載しない金」という前提で渡された還付金がいずれの団体に宛てたものかは、もともと清和会側でも、大野氏側でも認識していないし、それを特定することは困難です。
昨日の初公判では、大野氏は、政治家という立場もあるからか、全体として認識や共謀を否定することに力点を置いていましたが、少なくとも岩田氏の弁護人の主張では、還付金は「泰士会」への寄附ではなく、同団体の政治資金収支報告書に記載する義務はないという点が中心でした。
では、検察は、その「寄附の帰属」の問題について、どのように主張・立証しようとしているのか。
この点に関して、昨日の公判の検察官冒頭陳述では、「泰士会」について、以下のように述べています。
泰士会の主な収入は、清和会からの毎年夏と冬の2回にわたる50万円ずつの合計100万円の寄附及び支援者個人からの寄附のほか、泰士会の政治資金パーティーの会費収入等であり、泰士会の主な支出は、被告人大野の政治活動に伴う飲食費等であり、本件犯行当時は、清和会所属議員の秘書らの集まりである清和会秘書会の年会費も泰士会から支出されていた。
本件犯行当時、大野事務所では、被告人大野の活動のうち、自民党の活動は第三支部の活動、それ以外の活動は泰士会の活動と基本的に整理しており、清和会の活動は、自民党の活動ではなく被告人大野の議員個人としての政治活動であったため、清和会の活動は、基本的に泰士会の活動と整理していた。
そのため、前記のとおり、大野事務所では、前記清和会からの年に2回の合計100万円の寄附を泰士会で受けていたほか、本件犯行当時は、清和会秘書会の年会費も泰士会から支出していた。
そして、「第三支部」については、以下のように述べています。
第三支部は、政党支部であり、被告人大野の支援者であったFが会計責任者として届け出られていた。
第三支部の主な収入は、自民党からの交付金や個人・法人からの寄附等であり、主な支出は、大野事務所の家賃、光熱費等であった。
そして、清和会から「還付金を受けた事実を記載する必要がなく、還付金を費消した際に領収証を徴する必要もないことを説明されて現金で受領した還付金」について、
-
大野事務所では、被告人大野の活動は、自民党の活動は第三支部の活動、それ以外の活動は泰士会の活動に整理されており、被告人岩田もそのことを認識していた
-
清和会の活動は、被告人大野の議員個人としての政治活動であったため、泰士会の活動と整理されていた
-
還付金は、販売ノルマを超えて販売した清和会のパーティー券の代金相当額が戻されるものであることなどから、被告人岩田は、還付金は泰士会に対する寄附金である旨認識していた
などとして、還付金は泰士会に対する寄附金であり、岩田氏もその旨認識していたかのように主張しているのです。
検察官の主張立証の破綻
しかし国会議員の場合、現行の政治資金規正法で、実質的に、政党支部を通してのみ企業団体献金を政治家個人が受けることができるとされていることから、政党支部を企業団体献金と所属政党からの交付金の受け皿、資金管理団体を個人献金の受け皿とするのが一般的で、そのようにして入ってきた寄附を、資金管理団体と政党支部の間で必要に応じて資金移動させ、それぞれ政治活動費や事務所関係費として支出するというのが政治資金処理の実情です。
実際に、裏金議員とされた国会議員の政治資金収支報告書は相当数調べましたが、資金管理団体と政党支部は、上記のように個人献金と企業団体献金とで寄附の受け皿が違うというだけで、事務所経費の支出の分け方は様々です。清和会からの餅代・氷代等の寄附の入金先も、政党支部の場合もあれば、資金管理団体の場合もあります。
裏金事件で唯一逮捕・起訴された池田佳隆元議員の場合も、2023年12月8日に資金管理団体「池田黎明会」の収支報告書を訂正し、安倍派からの寄附約3200万円を収入として記載しています。
池田氏の場合も、検察は、「池田黎明会」の収支報告書の虚偽記入で起訴しましたが、その訂正以前に受けていた清和政策研究会からの寄附は、「池田黎明会」ではなく「政党支部」に入金され、政党支部の政治資金収支報告書に記載されていました。そのような実態からすれば、池田議員に関連する政治資金について、清和会から入ったお金を「池田黎明会」の収支報告書に記載すべき義務があったとも言い難いのです。
大野氏の事件について、「国会議員の活動のうち、自民党の活動は第三支部の活動、それ以外の活動は資金管理団体の活動と整理されていた」という理由で寄附の宛先が「泰士会」だというのも、検察が苦し紛れに考え出した主張だと考えられます。
このような検察官の主張は、明らかに「無理筋」です。今後の公判では、大野氏と岩田氏との共謀関係や、還付金が「泰士会」宛の寄附であることについての認識など、一般的にこの種の事件で争点になるような点も含めて審理されていくでしょうが、いずれにしても、「還付金は泰士会宛の寄附だ」とする検察官の主張は明らかに不合理であり、そのようなことを認める供述調書がいくつか存在したとしても、信用性はほとんどありません。まともな刑事裁判所が、そのような主張を認めるとは考えられません。
大野氏と岩田氏の刑事裁判は、結論としては無罪という結末になる可能性は高いと考えられます。
「法が機能していない現状」を放置した政治の怠慢
このような、政治家個人が受領した裏金は処罰が困難だという「政治資金規正法の大穴」問題のために検察の有罪立証が困難であることは、これから刑事裁判が始まることになる池田氏の事件でも同様で、また、検察が、金額が比較的僅少だとして起訴猶予処分でごまかしていた多くの国会議員の秘書の政治資金規正法違反も、争われれば刑事裁判で同じような問題が顕在化します。
もちろん、今回の政治資金パーティー裏金問題というのは、自民党派閥における政治資金の不透明性が端的に表れた事件であって、裏金議員やその秘書が処罰を免れること自体が、社会的には到底許容できないことです。政治資金パーティーで多額の政治資金を集めておきながら、それを収支報告書にも記載不要の裏金として、自由に使える金として所属議員に分配し、それが発覚しても、検察が政治資金として訂正処理することを積極的に示唆したために所得税すら払わないで済まされるということは、多くの国民にとって到底許せることではありません。
そういう意味で、今回の大野氏らの政治資金規正法違反事件から始まる刑事裁判での検察の主張立証の破綻は、今の日本の政治に関して「法が全く機能していない現状」を象徴するものだと言えます。
7月の参院選後の一か月半にもわたる「石破降ろし」が最終的に成功し、自民党では一年前のデジャヴともいえる「総裁選騒ぎ」が再び繰り返され、マスコミもそれに乗せられていますが、まさに、その時期に顕在化した「政治資金パーティー裏金事件の刑事裁判の現実」を直視すべきです。
すでに登録済みの方は こちら