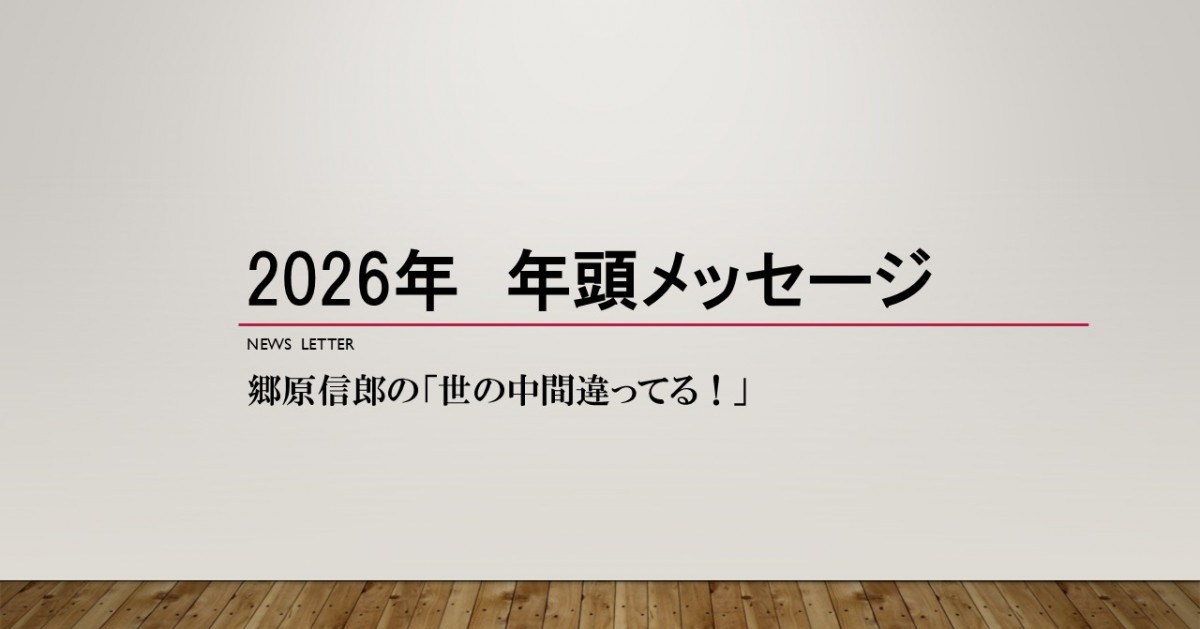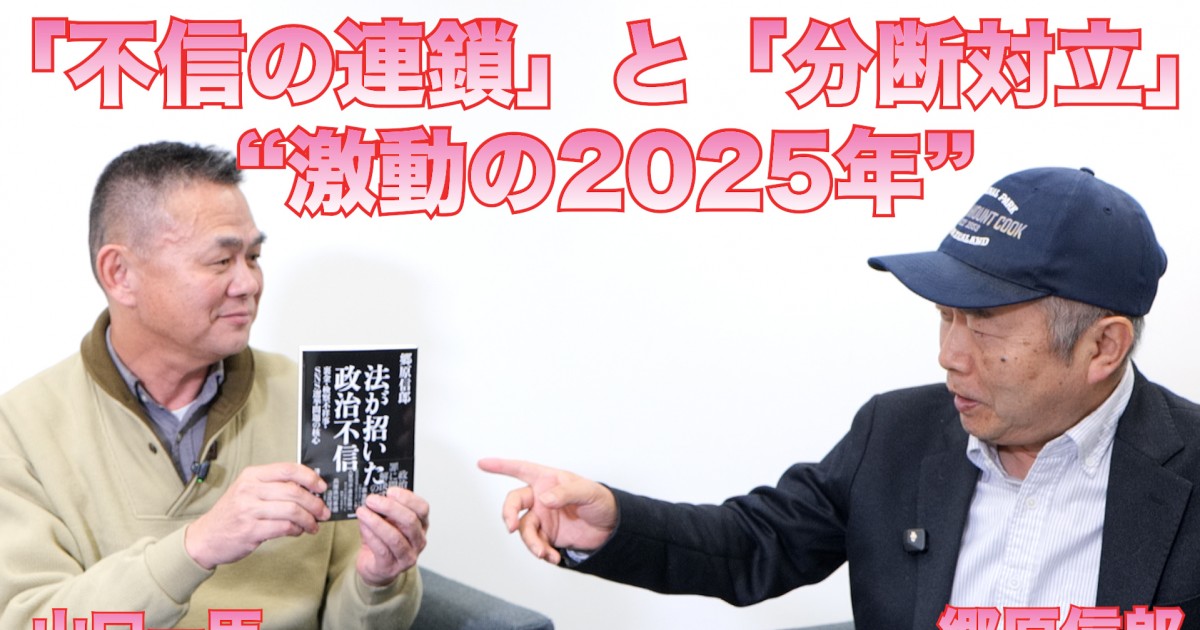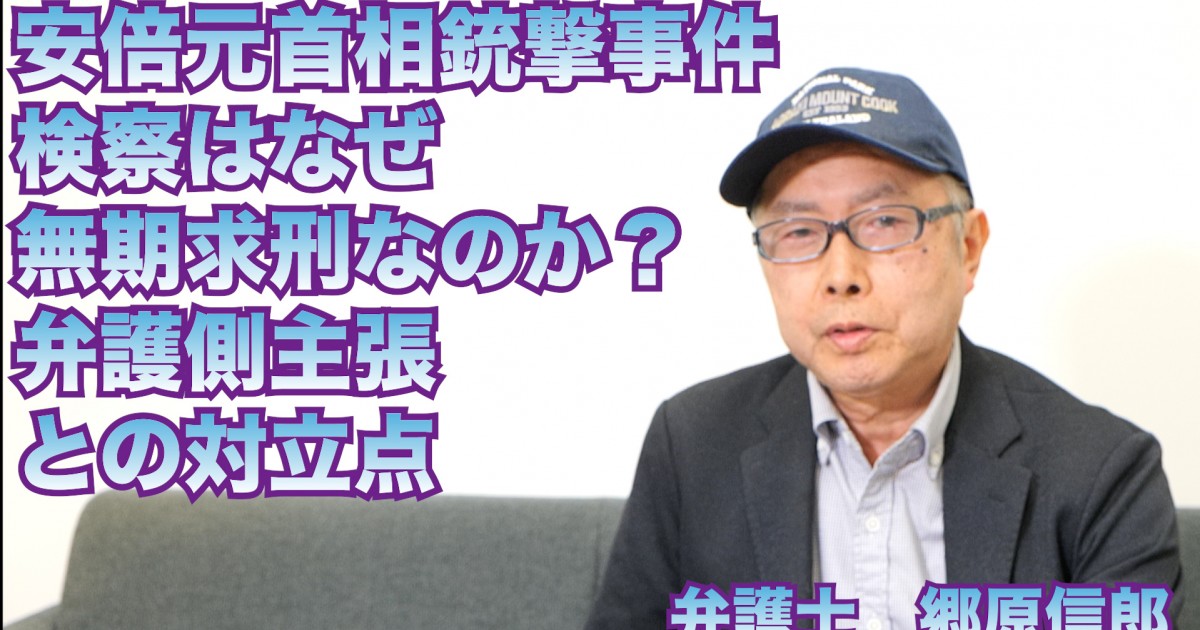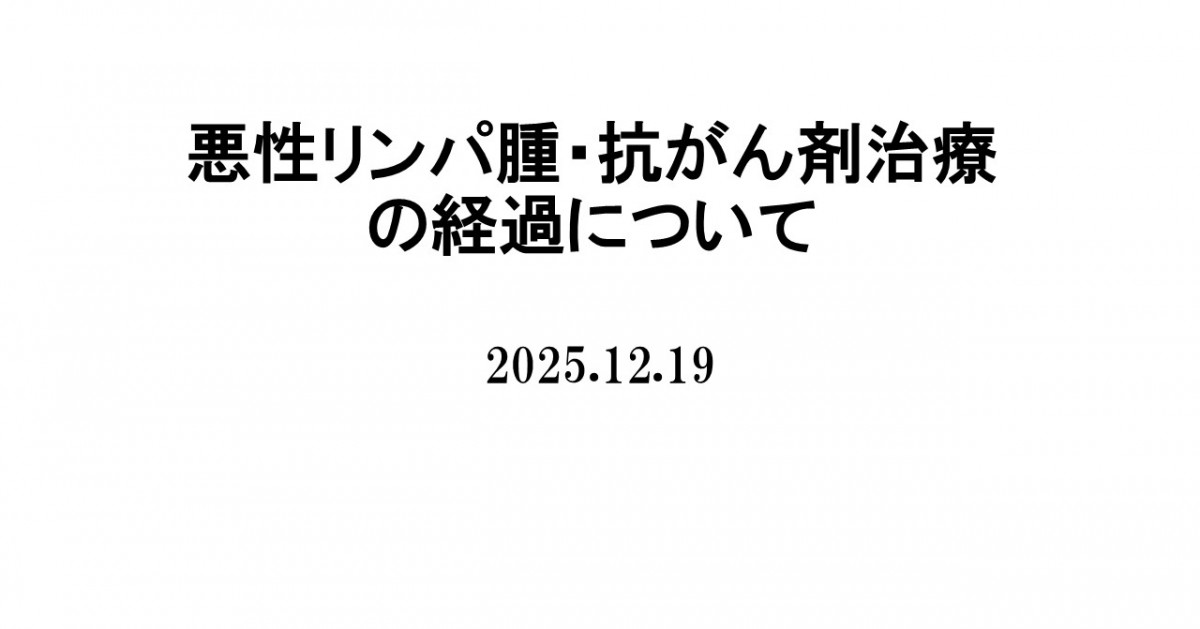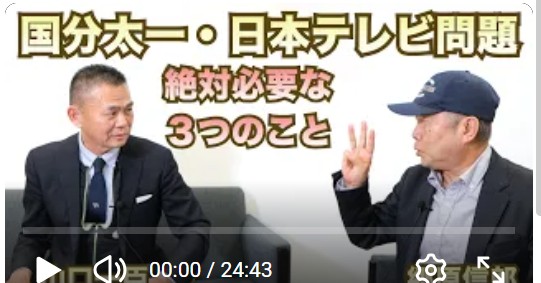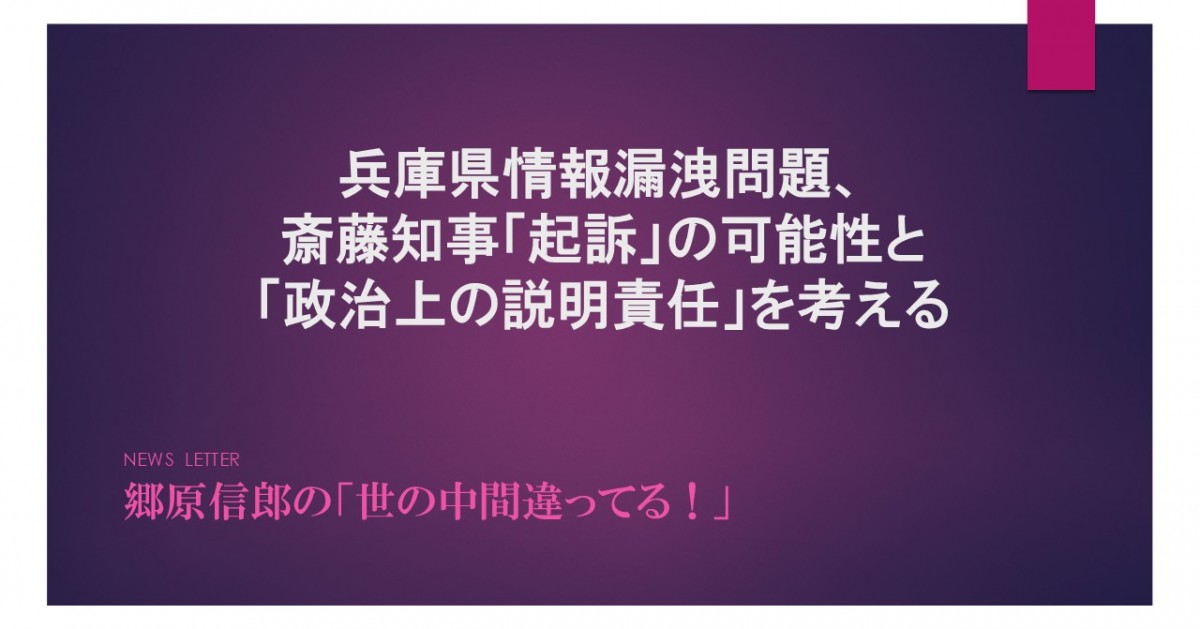斎藤元彦氏公選法違反事件、折田氏note記事の内容と裏付け証拠を徹底分析する
斎藤知事、merchu社の公選法違反事件の発端となった折田氏note記事
今回の告発の発端となったのは、折田氏が11月20日に公開したnote記事です(現在公開されている記事は修正されていますので、公開当時の記事をもとに、適宜修正点について言及します。なお、修正箇所についてはまとめ記事が複数存在し、また、当時の記事も魚拓サイトなどで確認できます。)。
note記事では、斎藤氏の選挙戦において、merchu社に斎藤氏が訪問し、
「ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました。」
と、依頼があったことを明かし、その詳細な手法まで記されていました。
人の供述として何に証拠価値があり、何が信用性があると評価されるかといえば、何と言っても、自分自身の意志で書いた文章です。その内容が本人の認識・記憶と違うとすれば何らかの原因によって記憶に誤りが生じたか、或いは記憶と異なることを誰かから強制されて書かされたか、いずれかです。そういう事情がない限り、自分自身で書いた文章というのは刑事事件の証拠としては極めて証拠価値が高いものと言えます。
一方で、警察官や検察官が作成する供述調書というのは、捜査機関側の意図を持って作成され、時として本人の言ってることと全く異なったことが供述調書に書かれ、何らかの心理的な圧迫を受けて署名してしまうということが、過去には枚挙にいとまがありません。
そういう意味で、今回の公選法違反事件の発端となった折田氏のnote記事の内容を詳細に分析するとともに、折田氏が別途行っている言動や、選挙期間中に関わりがあった関係者の人たちの言動などから、note記事の信用性、証拠価値を明らかにして行きたいと思います。
まず、前提として重要なことは、一般的な公選法の理解からすれば、選挙コンサルタントや選挙広報などについて、「業務として報酬を得て関わることは原則として許されない」ということです。
有償でも許されるのは、政治活動に関する業務か、機械的労務に限られます。選挙運動に対して主体的・裁量的に企画立案を行った場合、報酬を受ければ買収罪となり、ボランティアで行うよりほかありません。(※詳しくはこちらの記事【斎藤元彦氏ら告発事件に関する公職選挙法解釈の基本的事項】をご覧ください)
しかし、政治活動と選挙運動はそう簡単に切り離せるものではなく、ここまでが業務で、ここからがボランティア、などと単純に割り切れるものではありません。そのため、選挙コンサルタントや選挙広報などを行う業者は、いままで、対価を得るのであれば、政治活動の段階にとどめ、選挙運動には加わらないことにしたり、選挙運動にも関与するとしても、グレーな面があるため、ボランティアであることをできるだけ徹底し、表に出ない形で関与して黒子に徹することが鉄則であると理解されてきました。
しかし、このnote記事は、選挙に関与し候補者を当選に導いたことを公言し、その業務内容の詳細を自ら明かすという、通常ではあり得ない、かなり異例な形となっています。
以下、note記事の内容を見ていきます。
merchu社および折田氏が斎藤氏の選挙戦に関わるきっかけ
note記事では、merchu社および折田氏が斎藤氏の選挙戦に関わるきっかけについて、
「とある日、株式会社merchuのオフィスに現れたのは、斎藤元彦さん。
それが全ての始まりでした。
ご本人が何度も口にしている通り、政党や支持母体などの支援ゼロで本当にお一人から始められた今回の知事選では、新たな広報戦略の策定、中でも、SNSなどのデジタルツールの戦略的な活用が必須でした。
兵庫県庁での複数の会議に広報PRの有識者として出席しているため、元々斎藤さんとは面識がありましたが、まさか本当に弊社オフィスにお越しくださるとは思っていなかったので、とても嬉しかったです。」
と述べられていて、自身のSNS戦略が今回の選挙で重要であること、斎藤氏からの往訪がきっかけであること、などが記載されていましたが、上記の文はその後すべて削除されています。なお、9月29日に、merchu社に斎藤氏が訪れたことについては、当事者に争いはなく、間違いのない事実です。
さらに、斎藤氏が会社往訪の際、斎藤氏にプレゼンした状況の写真も、
merchuオフィスで「#さいとう元知事がんばれ」大作戦を提案中
という説明文とともに掲載され、その説明資料である、
兵庫県知事選挙に向けた広報戦略のご提案 #さいとう元知事がんばれ
との資料表紙の画像も掲載されています。
このプレゼン状況の写真では、上記の「広報戦略のご提案」の提案資料がメイン画面に映し出されているほか、折田氏側のノートパソコン画面に、SNSの活用によって下馬評より多くの得票に成功した都知事選候補・安野貴博氏の選挙総括noteも映っており、安野氏の選挙におけるSNS戦略も補助的にプレゼンに使われ、参考にされていたことも伺えます。
なお、後日、上記画像の説明文は、
オフィスで「#さいとう元知事がんばれ」を説明中
に変更されています。
SNSにおける広報戦略の方針
note記事では「SNS運用方針」と題したスライド画像が掲載されており、
SNSを活用して「斎藤知事を応援したい」「兵庫県をよくしたい」という想いをプラットフォーム化し、ムーブメントを起こす!!!
との方針の下、Xなどの「本人アカウント」と、公式の「応援アカウント」を「県民にメッセージを投げかけ、今回の選挙を自分ごと化、さらには応援してもらう」という狙いの下で連動させ、相乗効果を目指す旨が記載されています。
さらに、選挙戦を3つに分けた「SNS運用フェーズ」というスライドも投稿されており、そこには、
10月1日~13日 フェーズ1:種まき
立ち上げ:運用体制の整備
10月14日~31日 フェーズ2:育成
コンテンツ強化(質)
11月1日~17日 フェーズ3:収穫
コンテンツ強化(量)
と記載されていて、11月17日の投開票日まで、上記のSNS運用方針にもとづき、戦略的にSNS運用を行っていくことを、折田氏側が提案したことが明示されています。
さらに、こうしたスライドによる提案に対し、
「ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました。」
と述べています。
なお、後日、「SNS運用フェーズ」のスライド画像と、「ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました。」との一文は削除されています。
選挙戦を通じたイメージ戦略
note記事では、「まず、プロフィール写真の撮り直しからスタート」したと記載されています。
「3年前の兵庫県知事選挙の時のイメージは、今の斎藤さんのイメージと異なるため、撮り直しのご提案をしました。大阪にプライベートスタジオをお持ちの信頼できるカメラマンさんと、友人に紹介してもらったヘアメイクさんに急遽ご依頼をしました。」
とし、
「全ての告知物に使われる重要な写真なので全員で念入りにチェック」
したとも記載されています。
さらに、折田氏側が「コピー・メインビジュアルの一新」を提案し、実際、9月29日の折田氏側の提案資料通りのコピー・メインビジュアルの一新が行われ、斎藤氏は現在まで、その一新されたコピー、メインビジュアルを使い続けています。
なお、折田氏側は、このコピー・メインビジュアルの理由について、
「カラーは、兵庫県旗の色を意識した「兵庫ブルー」をベースとした斎藤さんオリジナルの「さいとうブルー」に一新しました。斎藤さんの持つ、芯の強さと柔らかさを、グラデーションカラーで演出しています。グラフィックエレメントは、ご本人の出身地である須磨の海をイメージした波を採用しました。右斜め上に向かわせることで、 今回の選挙戦を突破し、斎藤さんの率いる改革が進み、兵庫が躍動していく様子を表しています。また、斎藤さんご自身の「人生」をも表しているのです。」
などと詳細に説明もしています。
さらに、
「メインビジュアルの統一を徹底するため「デザインガイドブック」の作成も合わせて行いました。選挙カーや看板を制作してくださる業者に配布し、統一したデザインで素敵に仕上げていただきました。」
とも述べており、選挙運動全般について、このコピー・メインビジュアルで統一されるような仕組みを作ったことも明記されています。
SNSアカウントの立ち上げの戦略
X公式「応援アカウント」については、note記事で
「プロフィール撮影やコピー・メインビジュアルの作成が完了したタイミングで、【公式】さいとう元彦応援アカウントを立ち上げ、ご本人のSNSアカウントとは別に、応援したい人が集えるハブとして運用を開始しました。」
と述べています。なお、「応援アカウント」としての運用開始は2024年10月7日です。
そして「セキュリティ」について
「全てのアカウントで、認証アプリを活用した2段階認証の設定を徹底し、乗っ取りやアカウントバンなどへの対策を行いました。」
と記載しています。
さらに、「公式アカウントとしての信頼感の担保」の方法として、
「X本人アカウントが、この公式応援アカウントをフォローし、フォロー数を1としたことで、本人公認の公式アカウントであることが明示され、ユーザーが偽アカウントなどと混乱しないような対策を施しました」
と述べています。
そのうえで、折田氏側が運用面でこだわったのが「ハッシュタグ」だと記載しています。
「斎藤さんへの世の中の見方を変えていく上で重要だったのが、ハッシュタグ「#さいとう元知事がんばれ」です。
当時、様々なアカウントで多種多様なハッシュタグが使用されており、公式としてタグを一本化して発信することで、応援の流れに方向性を提供する必要があると考えました。また、タグが統一されてポスト数が増えていくことで、アルゴリズムにも有利に働くため、急速な支援の輪の広がりも期待できます。
「#さいとう元彦がんばれ」ではなく、あえて「知事」を入れることで、「さいとうさん=知事」という視覚的な印象づけを狙いました。さらに、「元彦」さんと「元知事」を掛け合わせて、「前知事がんばれ」ではなく「元知事がんばれ」としたのも、こだわったポイントです。ここは、ご本人も気に入っていました!
ハッシュタグというシンプルで簡単に見えるワードでも、それをどのように拡散してもらいたいのか、表記揺れなどを最小限にできるか、入力しやすいかなど様々な視点を考慮して設計することが大切です。」
と述べ、ハッシュタグの統一が、拡散にとっていかに重要か、また、ハッシュタグの視覚的効果などを詳細に語り、こうした緻密な戦略について、とくに「元彦」さんと「元知事」を掛け合わせた点を、斎藤氏も気に入っていたことも明記していました。
こうした戦略があって、
「2024年10月7日のX公式応援アカウント公開の翌日には、約2万件の投稿に付与されトレンド入りしました」
と、自身の広報戦略の成果を誇っていました。
なお、後日「ここは、ご本人も気に入っていました!」の一文は削除されています。
既存の選挙媒体の戦略
note記事では、ポスター・チラシ・選挙公報・政策スライドといった、既存の選挙媒体についても、折田氏側が関与していたと記載されています。具体的には、
「今回、既存のやり方は通用しないと考えていたため、紙媒体も既存の型にははめず、斎藤さんのことを分かりやすく様々な年代の県民の皆さまに届けるためにはどうしたら良いのか、仕様やサイズの異なるそれぞれの媒体でのベストをデザインチームと日夜追求しました。斎藤さんの今回の選挙におけるブランドイメージを統一すべく、全ての制作物は先述のデザインガイドブックに準拠する形で制作しています。
中でも最も作成に時間を要したのが、こちらの公約スライドです。ご本人から上がってくる文字のみのワードファイルを読み解き、どのような方でも見やすいデザインを意識したスライドに仕上げるため、2024年10月23日に行われた記者発表のギリギリまで手直しをしていました。」
「当日の発表では、公約スライドをパネルとして印刷していただき、多くの媒体に掲載されました。選挙期間中には事務所の壁にも掲示されており、県民の方に斎藤さんの政策や想いを届けることができました。
ご本人から、「1番最初に政策発表記者会見ができて良かった」という言葉を頂き、大手では出せないスピード感や小回りの利いた対応が功を奏したのではないかと振り返ります。実際、全広報活動において、「先手」を意識しておりました。」
などと述べ、斎藤氏からは「文字のみのワードファイル」だけが提供されたこと、それを読み解きスライドにするのに「最も作成に時間を要した」こと、自身が考えた「コピー・メインビジュアル」との統一にこだわったこと、他の候補に先んじて公約のアピールができ斎藤氏からも喜んでもらえたこと、選挙期間中にも事務所の壁に掲示されていたことなど、苦労した様子が詳細に記載されています。
SNSの運用戦略
SNSの運用については、
「斎藤陣営が公式として運用していたのは、以下のX本人アカウント、X公式応援アカウント、Instagram本人アカウント、YouTubeです。TiktokやLINEなど他にも様々なSNSがあるため、リソースが潤沢に準備できる陣営であれば、全方位的な運営ができたのかもしれません。ただ、今回は本当に限られたリソース(皆さま本業もお忙しい)での運営でしたので、戦略に基づき最適な媒体を取捨選択しました。私のキャパシティとしても期間中全神経を研ぎ澄ましながら管理・監修できるアカウント数はこの4つが限界でした。」
と記載されており、折田氏個人としての限界、および斎藤陣営のボランティアのリソースの少なさが原因で、媒体を絞らざるを得なかったことが述べられています。
また、SNSの運用における戦略については、
-
ブランドイメージの統一
-
ご本人のリアルな姿や人柄が伝わるコンテンツを届けること
-
政策を分かりやすいビジュアルや表現で県民に届けること
-
各SNSに適したレイアウトや内容に最適化して届けること
-
できる限り配信回数を増やして多くの情報を届けること
といったポイントが挙げられており、実際、「本人アカウント」や「応援アカウント」などで、そのような戦略に沿った投稿がなされていることも確認できます。
なお、ここで紹介されている「X本人アカウントの投稿」の画像では、下欄に「ポストのエンゲージメントを表示」と記載されています。これは当該アカウントに管理権限がある者がログインした場合にしか表示されない事項であり、折田氏がX斎藤氏本人名義アカウントにログインできる権限があったものと理解できます。
さらに折田氏は、
「私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、文章フォーマット設計、情報選定、校正・推敲フローの確立、ファクトチェック体制の強化、プライバシーへの配慮などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました。写真および動画の撮影については、現地で対応してくださっているスタッフの方々にお願いすることをベースに、私自身も現場に出て撮影やライブ配信を行うこともありました。」
と述べ、写真や動画撮影など、現場作業は手伝う程度であるにしても、すくなくとも「SNS全般」について、また立ち上げだけでなく、その後の「運用フェーズ」においても、責任ある立場で任されており、戦略を考え、運用について管理・監修等を行っていたことを明らかにしています。
そして最後に、
「今回の支援期間中にフォロワー数は以下の通り急増し、注目度の高さを日々感じていました。結果、X公式応援アカウントは、東京都知事選挙で盛り上がりを見せた【公式】石丸伸二 後援会のフォロワー数54,000を超えておりました。
2024年11月19日、斎藤さんが第54代兵庫県知事に就任されたと同時に「#さいとう元知事がんばれ」から「#さいとう元彦知事がんばれ」へとハッシュタグをアップデートすることで、この物語は無事に幕を下ろしました。」
と、当選までを「支援期間」とし、選挙を通じて、SNSで盛り上がったとされる都知事選の石丸氏を超えるフォロワーを獲得したことを成果として誇示しています。
折田氏自身の思い、苦労など
折田氏は、note記事で選挙戦を振り返って、「選挙は広報の総合格闘技」であり、「質・量・スピード全てが求められ、食べる暇も寝る暇もない程で」、「脳みそを常にフル回転し続けなければならない点が、最もハード」であり、「大きな試練」であったと振り返っています。にもかかわらず、「大手広告代理店がやっている」、「都内のPRコンサルタントが手掛けている」、「400人のSNS投稿スタッフがいた」などと「デマ」が拡散しており、
「驚きを隠せないと同時に、「私の働きは400人分に見えていたんや!」と少し誇らしくもなりました。そのような仕事を、東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです。」
と、今回のnote投稿の動機のひとつであろうエピソードを話しています。
そして最後に、
「今回の知事選は、兵庫県の未来だけでなく、今後の日本、そして政治や選挙のあり方にすら大きな影響を与える重要な選挙であったと考えており、約1か月半、全身全霊で向き合ってきました。」
「特定の団体・個人やものを支援する意図もなく、株式会社merchuの社長として社会に貢献できるよう日々全力で走り続けたいと思っています。」
などと語っています。
note記事の法的評価と信用性評価
note記事の記述内容が事実であるとすれば、折田氏、および折田氏が社長を務めるmerchu社が、本件知事選挙に向けた広報戦略全般を斎藤氏に提案し、提案した戦略通りに、投開票日まで、組織的かつ継続的なインターネットでの選挙運動が行なわれたことが具体的に明らかにされているといえます。
また、note記事では、折田氏はmerchu社としての業務と、折田氏個人としての活動を切り分けてはおらず、むしろすべての広報戦略について、merchu社という、兵庫の小さな会社が担っていたことを誇ってすらいます。さらにnote記事に記載のある、投開票日までのすべての「SNS運用フェーズ」で一貫したSNS戦略の構築、運用を行っていることや、「広報全般」を任されてから、投開票日までを「支援期間」と称していること、「皆さま本業もお忙しい」ためにリソースが限られるなかで、折田氏自身は「食べる暇も寝る暇もない程」の忙しさのなか、約1か月半、全身全霊で知事選に向き合ってきたことなどについても、素直に読む限りは、折田氏が、merchu社の業務として広報戦略全般を請け負い、投開票日まで全力で業務に取り組んでいた、としか理解のしようがないものとなっています。
こうしたことから、note記事を前提とすると、総務省のガイドラインでも指摘されているように、本件は「業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行って」いる事案そのものであり、さらにはその立案にもとづいた選挙運動自体も行っているのであって、「当該業者は選挙運動の主体」であるため、当該業者への報酬の支払は買収罪となるものと考えられます。
では、note記事の信用性についてどのように評価すべきでしょうか。
折田氏が代表を務めるmerchu社は社員数名の小さな会社ですが、令和6年度の実績を見ると、広島県の「SNS運用支援業務」が約1300万円、広島市の「SNS活用プロモーション業務」「広島ピースツーリズムフォトコンテスト等実施業務」「佐伯区のプロモーション推進委託業務」が約950万円、高知県が「高知県SNS公式アカウント分析等委託業務」で約250万円、徳島県が「SNSを主軸とした徳島県新時代情報発信業務委託」で約800万円など、自治体のSNS支援業務を多く受注して、ひとつの得意分野としていました。
そうだとすれば、merchu社および折田氏は、選挙に関わるのは初めてであり、公選法に対してあまりに無知であったため、結果としては大きなマイナスプロモーションとなってしまいましたが、今回の自治体選挙での“実績アピール”のための本件note記事は、兵庫県を含めた自治体のSNS支援業務について、次の仕事につなげようという意図があったことは明らかです。
そして、自治体との業務は信用が非常に大事になります。兵庫県の知事選での実績のPRに虚偽があるのであれば、兵庫県を含め、他の自治体との信頼関係は容易に毀損すると思われ、merchu社の業務状況を客観的に見る限り、折田氏が多少実績を誇張することはあり得ても、虚偽を述べる合理的理由はかなり乏しいと言わざるを得ません。
また、折田氏は、これまで指摘したように、公選法違反の指摘等を受け、斎藤氏との直接のやりとりをうかがわせる文言など、多くの点をnote記事から削除、修正しているのですが、冒頭の一文、「今回広報全般を任せていただいていた立場として、まとめを残しておきたいと思います。」との文言は変えることはありませんでした。
斎藤氏の代理人の奥見弁護士らから「盛っている」などと指摘されてもなお、「広報全般を任せていただいていた」という点は削除、修正をしないのですから、折田氏はこの点に絶対の自信を持っているか、強いこだわりを持っている、と考えるのが通常です。
少なくとも折田氏は、「広報全般を任せていただいていた」と自負していて、虚偽を述べているつもりはないものと解されます。
note記事と整合する折田氏本人の発信
また、note記事と整合する折田氏の発信が、note記事の前から、折田氏のインスタグラムに見受けられます。
まず、選挙期間中である11月14日の投稿で、note記事と同様の記述として
「そんな中、広報PRのプロとしての私のご提案を聞きに来てくださったのが全ての始まりでした。」、
「わざわざオフィスまでお越しくださったのがとても嬉しかったです」、
「斎藤さんご本人の実績、政策、お約束などは、チラシ・選挙公報・公約スライドなど紙媒体さらには以下のデジタルツールで脳みそを毎日最大限にフル回転させながら分かりやすいデザインを心がけてお届けしています」
などの記載が見受けられ、広報のプロとして、この日も選挙に主体的・裁量的に関わり続けていることが示されています。
当時勢いは感じていたとは思いますが、いまだ優勢とは言い難く、まだ結果の判らない選挙に関して、自身の仕事に関係する関わりについて虚偽を述べる合理的理由は見出しがたく、これと整合するnote記事の記載は、事実である可能性が高いと思われます。
さらに、折田氏は選挙後、note記事投稿前の11月18日に、以下のような文章を含むインスタグラム投稿を行っています(なお、現在でも閲覧可能で、修正はされていません)。
約1ヶ月半の四六時中スマホを握りしめて対応し続けたこの日々が終わってしまうのは、寂しく思いましたが、その他もやることがたくさんで、まだまだ全く落ち着く気配がありません
今回は中から見ていても、本当に様々なドラマやストーリーがあり、事実に基づいたドキュメンタリー映画を作って欲しいぐらいです!笑
というのも相変わらず事実に基づかない報道が早速出回っており、私としては非常にもどかしく思っております。
たとえば、私が関わらせていただいている広報PR周りでは、【SNS投稿を担う約400人のスタッフが原動力】という内容を各大手メディアが報道していますが、【約400人のSNS投稿スタッフは陣営内にはいません】。
公式として、世の中の情勢に鑑みて、自らが立てたフェーズごとの戦略に基づき、県民の皆さまに【事実を正しく伝える】ために1つ1つ慎重に情報を精査し、個人情報保護の配慮やファクトチェックなど、かなり神経を研ぎ澄まして本当に信頼できる少数精鋭のチームの皆さまと力を合わせて運営してきました
そのような運営を常に心がけていた側からすると、何をソースにして、どんなファクトチェックをしたら、「400人の投稿スタッフが関わっている」と受け止められるような情報をさも事実であるかのように世に出せるのかが全く理解できません
逆に有志のボランティアの発信者は400人どころではなく、4,000人も40,000人もそれ以上にたくさんいたはずです。それぐらい大きく応援の輪が広がりました
今回の一連の流れの中で、マスメディアがどれだけいい加減な情報を流布しているか身をもって知ることができました。
本当に情報が溢れる世の中だからこそ、様々な媒体からできる限りの情報を入手して、自分の目で見て、耳で聞いて、何が本質なのか追究する姿勢が何よりも大切です。
SNSですら、あくまでも一つのメディアであることを忘れてはなりません。
だからこそ、情報の発信者はより真摯に、真剣に、事実を届けることに向き合う必要があると思っています
世の中では、折田氏を“キラキラ女子”扱いし、自己顕示欲からnote記事で自己の実績を盛ったかのような話がまことしやかに流布していますが、少なくとも18日のインスタグラムの投稿では、前日の17日の日経新聞の記事に、斎藤氏の勝因の一つとして「攻勢の原動力となったのは、SNSへの投稿を担う約400人のスタッフだ」などと事実無根の記事を書かれ、自己の頑張りがなかったことにされそうになったことに怒り、ファクトを報じろ、という文脈において、「約1ヶ月半の四六時中スマホを握りしめて対応し続けた」、「公式として、世の中の情勢に鑑みて、自らが立てたフェーズごとの戦略に基づき、県民の皆さまに【事実を正しく伝える】ために1つ1つ慎重に情報を精査し、個人情報保護の配慮やファクトチェックなど、かなり神経を研ぎ澄まして本当に信頼できる少数精鋭のチームの皆さまと力を合わせて運営してきました」などと、ファクトとしての自己の業務を記載していることは明白です。
日経新聞に対してファクトを報じろと批判しつつ、自己の実績について盛って記載するということは、通常でも考え難く、また、広報を生業とする者が広報業務に関してそのようなことを行うことは、自殺行為に等しいものと思われます。
「自らが立てたフェーズごとの戦略に基づき」などの、上記投稿にある折田氏の主体的・裁量的な活動をうかがわせる記述は事実である可能性が極めて高く、これと整合するnote記事の記載は、事実であるといえます。
note記事と整合する周囲の発信
週刊文春 (1月23日号)などの報道によれば、斎藤氏の後援会事務所が入る物件のオーナーで、21年の前回選挙での選挙運動を手伝っていて、9月29日の斎藤氏のmerchu社往訪にも同席していたK氏が、10月5日に上原みなみ神戸市議(報道時は匿名)と面会した際、上原氏は斎藤氏を支援しようと名乗り出て、特にSNS戦略で協力を申し出ていたところ、明くる6日朝、この市議のもとにK氏から
「昨日の会議内容 Sns監修はメルチュさんにお願いする形になりました」
として、申し出を断るLINEが届いたとしています。
上原氏も、
“「SNS監修はメルチュ折田楓さんにお願いすることになりました」というLINEを受け取ったのは私です”、
と報道を認めるYouTubeを発信しており、文春の報道内容や、森けんじ氏の「選対会議」に関する発信なども合わせて考えると、10月5日に、斎藤陣営で「選対会議」が開催され、merchu社に対し「SNS監修」を依頼することが決定したことは明らかです。
斎藤氏を支援し、斎藤陣営と関わりの強い森けんと西宮市議会議員が、自身のXにおいて、メディアからSNS戦略について取材があった際、
「結論、陣営側としてSNSをお願いしていた方はお一人のみです。」
と答えたと、11月19日16時すぎに投稿しています。
また、同じ会話の流れのなかで広報担当が誰かを詮索する返信が続き、同日17時頃に
「いえ違います。ボランティアメンバーではありません。」
とも投稿しています。
さらに、前記の折田氏のnote記事が11月20日の9時過ぎに投稿されると、森氏は同日10時50分頃に
「今回の選挙においてSNSや紙媒体等担当された方です!裏話?等、詳しく書いているので是非ご覧ください」
と、折田氏のnote記事を紹介する投稿をしています。
こうした投稿から、森氏としては、主要なSNS戦略を折田氏一人が担っていた、という認識をもっていたことがわかり、note記事と整合的です。
なお、森氏はのちに、自身の上記投稿が問題視されるようになり、11月19日16時頃の投稿を「SNSのボランティアが400人でなく1人」という意味だ、などと述べ、note記事を肯定しないかのような主張をするようになっていますが、それに続く「ボランティアメンバーではありません」という投稿と完全に矛盾していて、公選法違反も問題表面化後に変節した言動は信用性に欠けるものと思われます。
さらに、斎藤氏を支持する姫路市議の高見ちさき氏も、自身のXで、11月19日に、前述の折田氏の18日のインスタ投稿を紹介するため、
「斎藤知事のSNS関連を全てになってくださってた折田さんの投稿です(折田氏インスタURL)メディア各社は、どうせなら400人分の働きをする折田さんのPRをしてくれ~!」
と投稿し、折田氏のnote記事への批判が高まった11月24日には、
「斎藤事務所の許可を得た記事である以上、折田さんだけが過剰にバッシングを受けるというのはいかがなものかと思います。」
とも投稿しています。
高見氏は、SNSに不適切な投稿を繰り返しているとして市議会から辞職勧告を受けている人物で、その発言の信用性には注意が必要と思われますが、斎藤氏に不利になる形で虚偽を述べる理由はなく、「斎藤知事のSNS関連を全てになってくださってた」との投稿には一定の信用性があり、折田氏のnote記事の信用性を補強するひとつの材料となり得るものと解されます。
以上述べてきたところから明らかなように、折田氏のnote記事は、今回の公選法違反事件の発端であるとともに刑事事件の証拠としても極めて重要なもので、しかもその信用性に疑問を差し挟む余地はほとんどありません。折田氏は、捜査機関の取調べを受けていると考えられますが、その供述内容は、note記事に沿った内容で、捜査機関や検察官も信用性を認めているはずです。
すでに登録済みの方は こちら