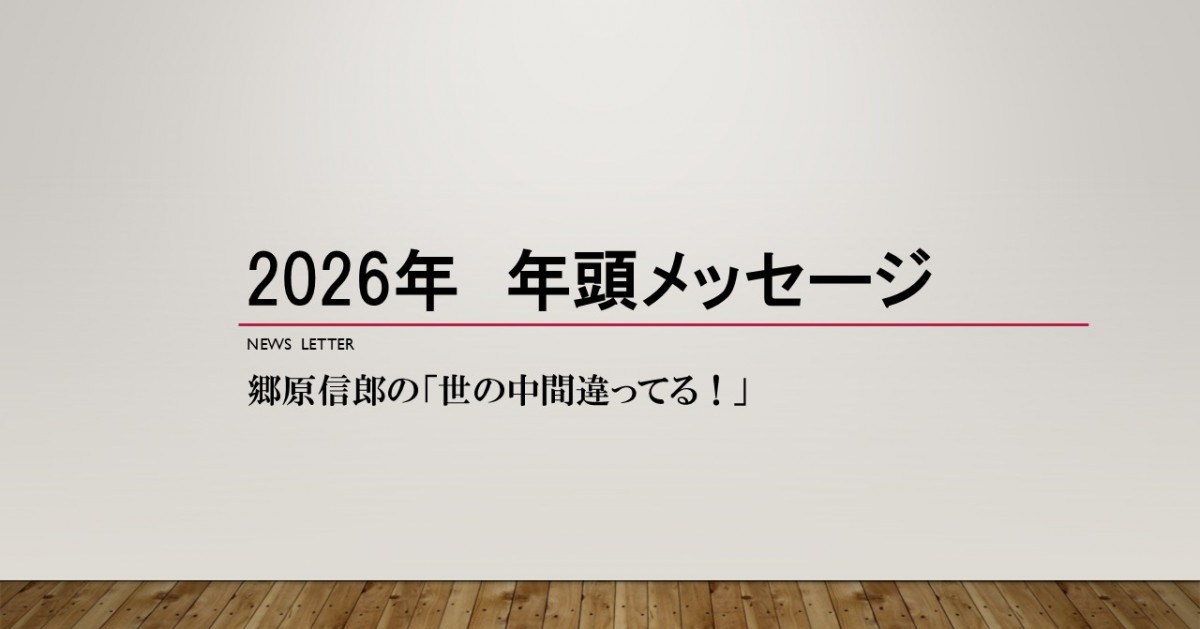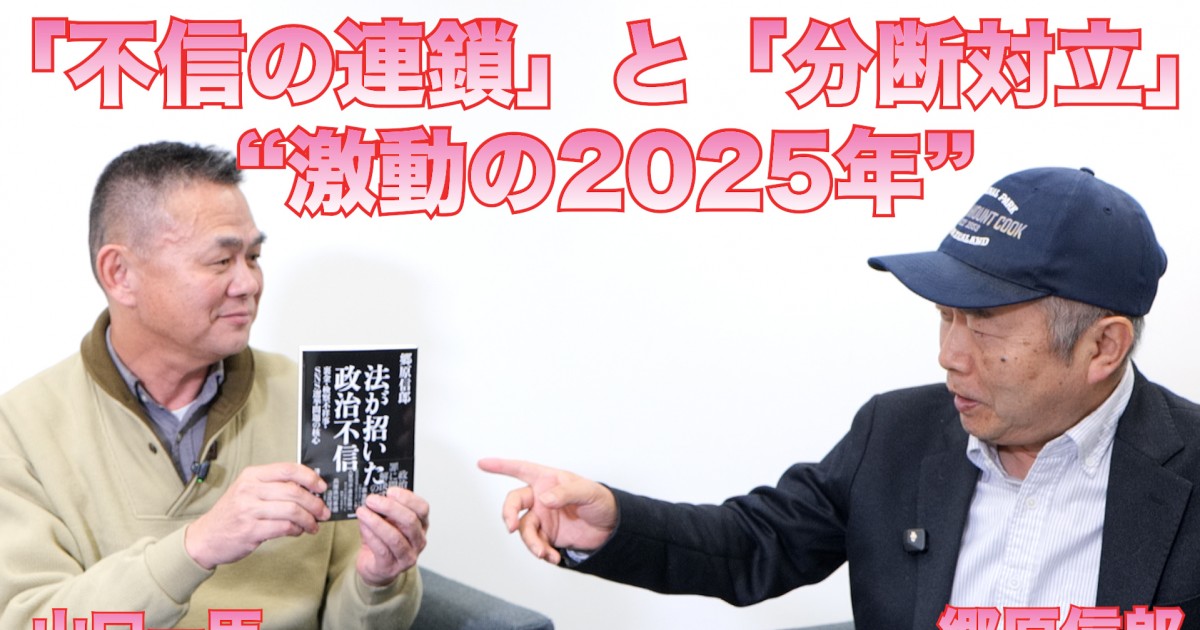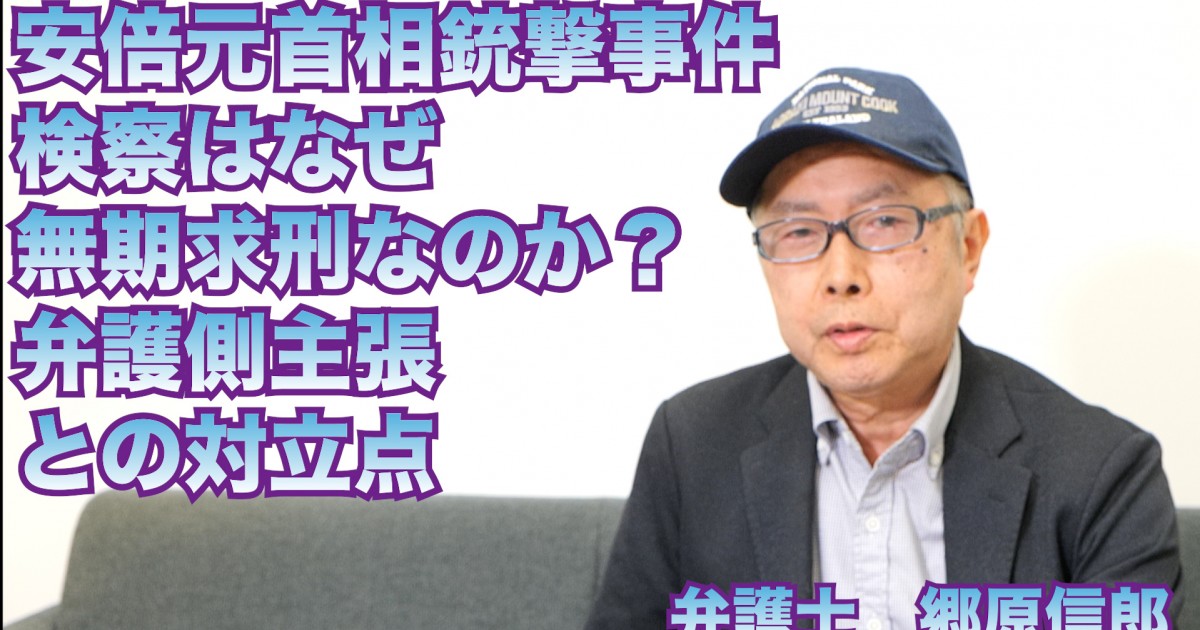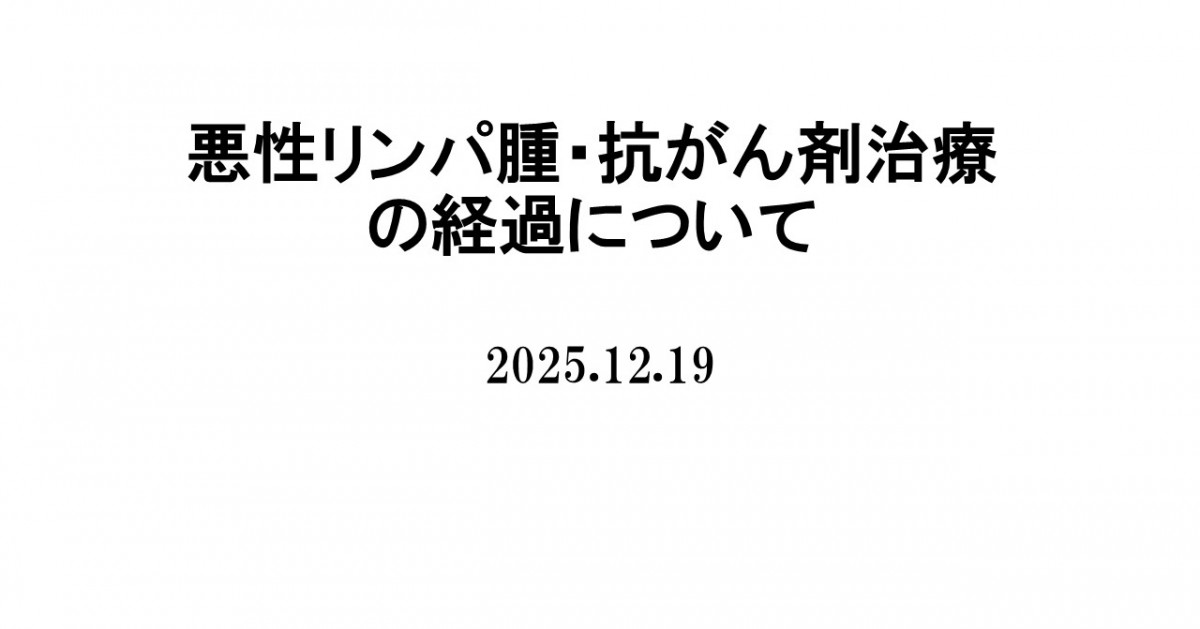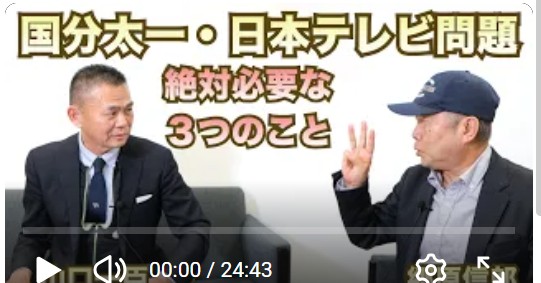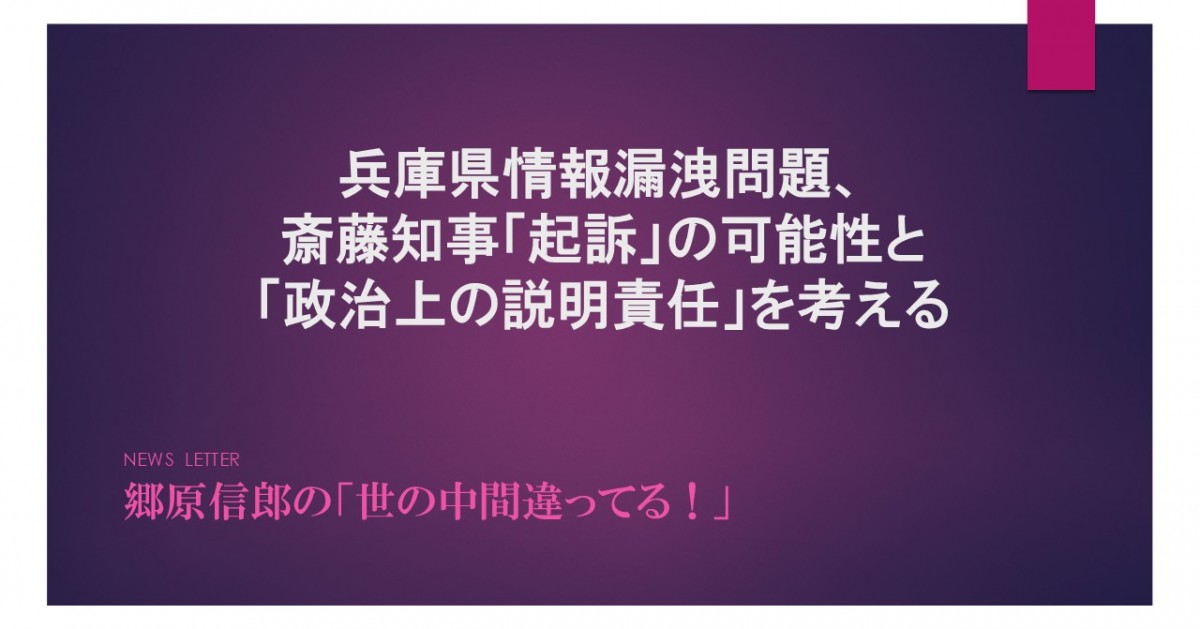斎藤知事・merchu社公選法違反事件、「追加告発」を含め、改めて解説します
7月15日に悪性リンパ腫でICUに緊急入院し、23日に一般病床に移った後も、治療のため入院が続いていましたが、8月29日には退院して通院治療に切り替えることになりました。お蔭様で、退院後の経過も順調で、現在では、抗がん剤の副作用による味覚障害と手足のしびれには悩まされていますが、免疫抑制のため感染リスクへの対応に留意しつつ、ほぼ通常どおりの業務が行える状態にまで復活しました。
ここまで短期間で奇跡的とも思える回復ができたのは、緊急入院公表以降、私を支えてくれた家族や事務所スタッフ、そして、このニュースレターの読者の皆様からのコメント、XやYouTubeなどの私の発信へのコメント・リプライなどで、本当に多くの皆様から、お見舞い、励まし、私の回復を願う心のこもったメッセージを頂いたおかげです。心から深く感謝します。
こうして、ほぼ「エンジン全開」とも言える状況になりましたので、今後、体調に留意しつつ、これまで以上に「法と正義」を取り戻すための活動に取り組んでいきたいと思います。
2024年11月の兵庫県知事選挙をめぐる斎藤元彦知事らの公選法違反事件、刑事処分に向けた捜査は、最終段階に入っていると考えられます。そう遠くない時期に神戸地方検察庁が刑事処分を行うことになると思われます。その際、事件の社会的影響を考えれば、公選法違反事件としての内容が、世の中に、とりわけ、兵庫県民の皆さんに、正しく受け止め理解される必要があると考えられます。
最近の検察庁の運用では、起訴の場合も不起訴の場合も、刑事処分の内容や理由についての説明はほとんど行われておらず、検察の説明では、事件の内容や処分の理由を理解することはできないのが実情であることを考えると、今回の公選法違反事件については、別途、事実関係や関連する公選法の解釈などについて、全体を取りまとめて、その内容を公表することが必要と考え、いくつかの記事に分けて解説を皆さんにお送りすることにしました。
昨年12月初めに私と神戸学院大学上脇博之教授が告発を行い、告発状を公表した後に、多くの兵庫県民の方々から情報資料が提供され、マスコミで報道されたものも含め、把握した資料・情報は相当な量に上っていました。それらについて、私の事務所「郷原総合コンプライアンス法律事務所」の法務コンプライアンス調査室長の佐藤督とともに逐次取りまとめを継続してきました。
関連する公選法の判例・文献などを幅広く収集し、分析検討する中で、本件は、221条1項1号よりむしろ同条項2号の「利害誘導罪」を適用すべき事案ではないかと指摘してくれたのが佐藤で、私の入院中のことでした。退院後、私の方でも検討した結果、「斎藤氏の代理人の奥見弁護士の説明を前提としても利害誘導罪に該当することは否定する余地がない」との判断に至り、上脇教授とも協議した上、今年9月5日付けで、神戸地検に追加告発状を提出しました。
追加告発といっても新たな事実を追加したのではなく、当初の告発状では公選法221条1項1号の「買収罪」として告発事実を構成していたのを、221条1項2号の「利害誘導罪」にも該当するということで、再構成した告発事実を追加し、検察官としての起訴事実の構成の選択肢として提示したものです。
もちろん、我々告発人側としては、当初から買収罪についても嫌疑は充分だと考えており、現時点までに捜査機関が収集した証拠から、当初の買収罪で起訴の可能性も十分あります。しかし、捜査結果や収集された証拠の中身は知りようがありませんので、被疑者側の弁解を前提にしても公選法違反を免れることができないと考えられる罰則適用と事実構成がある以上、それを選択肢として提示しておくことが必要と考え、追加告発状という形で神戸地検に提出したものです。
この追加告発状提出については、まず検察庁の方で充分にその内容を把握して、刑事処分に向けての検討に活かして頂くことが必要だと考え、公表は行わず、これまで本件について問題意識を持って取材してくれていると認識している一部の記者に個別に情報・資料を提供するにとどめていました。提供したマスコミの一部で、追加告発について記事化の動きがあるようですので、私の方でも、今回、数回に分けて出す解説記事の初回の本稿の中で、追加告発状提出にも言及することにしました(追加告発状で追加した公選法221条1項2号による告発事実と、利害誘導罪の解説は、別途、個人ブログ「郷原信郎が斬る」に掲載しています)。
本稿では、昨年11月の県知事選直後に公選法違反疑惑が表面化した当初からの経過を振り返り、この事件について問題となるポイントを全体的に整理したいと思います。
斎藤知事ら公選法違反事件、告発に至る経緯
2024年11月17日投開票の兵庫県知事選挙で斎藤元彦氏が当選した直後、同月20日に、広報・PRのコンサルティング会社「株式会社merchu」(以下「merchu社」)の代表取締役折田楓氏が、斎藤氏からSNS広報戦略を任されたことと業務内容の詳細を自ら明かすnote記事を投稿しました。
同記事に関して、インターネット上で、同業務について斎藤陣営から報酬が支払われていれば公選法違反(買収)、無報酬だったとすると、merchu社から斎藤氏に対する寄附として公選法違反、政治資金規正法違反の問題が生じるとの指摘が相次ぎました。
11月27日の斎藤氏による兵庫県知事定例会見において、本件note記事に関する質問を受けて、同会見終了後に、斎藤氏の代理人の奥見司弁護士による会見がおこなわれ、斎藤氏側からmerchu社に支払ったのは、
(1)「公約のスライド制作 30万円」、
(2)「チラシのデザイン制作 15万円」、
(3)「メインビジュアルの企画・制作 10万円」、
(4)「ポスターデザイン制作 5万円」、
(5)「選挙公報デザイン制作 5万円」
の5項目(税込み合計71万5000円)
であることと、それらの請求書を公表し、
merchu社にはSNS広報を依頼しておらず、折田氏がボランティアとして選挙に協力したに過ぎない
との説明がありました。
そこで、note記事に記載されたmerchu社のSNS広報戦略業務と斎藤氏側からmerchu社への71万5000円の支払について、公選法上の問題について検討したところ、note記事は、その作成経過、内容自体から信用性が極めて高いと考えられる上に、斎藤陣営の幹部のX投稿等によって裏付けられていること、一方で、斎藤氏の代理人奥見弁護士による説明は不合理な点が多々あって到底信用できず、斎藤氏側からmerchu社にSNS広報を依頼し、71万5000円にはその報酬が含まれている疑いが濃厚と判断されました。
そこで、12月2日、神戸学院大学上脇教授とともに、神戸地検と兵庫県警に対して、斎藤知事と折田氏を被告発人とする公選法違反の告発状を提出しました。
告発後、県民から提供された多くの情報・資料、捜査の進展
同告発状は、同年12月16日に受理され、2025年2月7日にはmerchu社側に捜索差押の強制捜査が行われたと報じられました。6月20日には兵庫県警が捜査結果についての書類、証拠物等を検察官に送付し、現在、神戸地方検察庁で、刑事処分に向けて最終段階の捜査と検討が行われているものと思われます。
この告発については、マスコミでも斎藤知事が公選法違反で告発されたことが大きく報道され、告発の時点で告発状をネット上で公開したこともあり、その直後から様々な情報資料が告発人の私のもとに提供されました。
公選法違反の買収事案の中でも選挙人に対する投票買収などでは、当事者間における金銭等のやり取りの有無が最大の問題となりますが、本件の場合、候補者側から一定の金銭の供与があった事実は明らかであり、最大の問題は、その金銭の供与を受けた側が選挙運動を行った事実の有無でした。
今の時代は、街頭での選挙運動に関してネット上に様々な映像・音声、コメント、情報などが溢れており、まさに選挙運動の実態がネット上に晒されているとも言えます。兵庫県民等から多数提供された情報の中には、本件に関連すると思われる貴重な情報もありました。 中にはmerchu社のSNS 運用に関連する業務について、ネット上の公開情報を収集し、取引先の地方自治体に情報公開請求を行って、契約内容に関する資料を提供してくれた人もいました。
また、折田氏がnote記事に記載しているSNS 運用の内容について、関連するアカウントの情報を詳細に分析し、SNS 広報戦略 について分析・検討した結果のレポートを送付してくれた人もいました。このような資料情報については、適宜、告発に関連する追加資料情報として神戸地検担当検察官に送付をしました。また、マスコミでも、その後、関係者の取材に基づく報道が多数行われました。これらにより、告発後に告発人として把握した資料・情報について、調査室長の佐藤とともに逐次取りまとめを行ってきたことは、冒頭で述べたとおりです。
そこでまず、本件について、これまでに明らかになったことを踏まえて、公選法違反事件の刑事処分において何がポイントになるかを考えてみたいと思います。
刑事処分を考える上での2つのポイント
公選法違反事件の刑事処分との関係で、本件を全体としてみると、2つのポイントに分けて考えることができます。
第1に、兵庫県知事選挙において、折田氏とmerchu社の行為の内容、斎藤氏側から何を依頼され、何を行ったのかです。
折田氏は、自分自身で作成して投稿を続けていた個人ブログのnoteに、昨年11月20日に、merchu社が斎藤氏側からSNS運用を全面的に任せられ実行していった状況を詳細に書いた記事を投稿しました。このnote記事が、その作成経過、内容自体から信用性が極めて高いと考えられる上に、斎藤陣営の幹部のX投稿等によって裏付けられていることは、告発の時点でも、公選法違反の嫌疑の重要な根拠となりました。
それに加え、告発後に提供された様々な情報・資料により、少なくとも、告発の時点と比較して、note記事を裏付ける証拠は一層豊富になっています。
一方で、note記事を「盛っている」などとして信用性を否定し、
「merchu社にはSNS運用を委託していない。折田氏は無償のボランティアとして斎藤氏を応援し、公式応援アカウントの取得、記載事項のチェック、街頭演説会場などにおける動画の撮影、アップロードなどを行った。」
というのが斎藤氏の代理人奥見弁護士による説明であり、斎藤氏側の主張です。
告発の時点でも、このnote記事の信用性を否定する斎藤氏側の説明・主張は極めて不合理であることを指摘しましたが、その後、マスコミ報道や、告発人に提供された資料・情報によってnote記事の信用性が裏付けられたことにより、斎藤氏側の説明が不合理であることは否定し難いものになっています。
merchu社が斎藤氏側からSNS運用を全面的に任せられ実行したこと、それが主体的、裁量的に行われた選挙運動であることが一層明白になったことにより、「merchu社にはSNS運用を委託していない。折田氏は無償のボランティアとして斎藤氏を応援しただけ」という斎藤氏側の主張は強く否定されることになります。
しかし、第1の点について、兵庫県知事選挙において、折田氏とmerchu社が、斎藤氏側からSNS運用を依頼され、実行したこと、それが斎藤氏のための選挙運動に当たることが明らかになっても、それだけで、斎藤氏らの公選法違反について犯罪の立証が可能となるわけではありません。問題は、その選挙運動に対して対価が支払われたと言えるかです。
71万5000円の支払の公選法上の違法性
そこで、第2の点は、斎藤氏側からmerchu社に支払われた71万5000円の公選法上の違法性がどのように判断されるのかという問題です。
この71万5000円の支払について、斎藤氏側は、
「(1)は政治活動の費用、(2)~(5)は選挙の準備活動のための支払いであり、選挙運動の対価ではない」
と主張しています。
一方、本件告発では、
「merchu社は、折田社長を中心に斎藤氏側から兵庫県知事選挙におけるSNS運用を任せられ選挙運動を行った。71万5000円はその選挙運動の対価に該当する」
と主張しています。
斎藤氏側が、「(1)は政治活動の費用、(2)~(5)は選挙の準備活動のための支払」だとしている71万5000円について、買収罪が成立するとすれば、以下の3つの構成が考えられます。
(ア)(上記第1の点について、「兵庫県知事選挙において、折田氏とmerchu社は、斎藤氏側からSNS運用を依頼され実行し、それは斎藤氏のための選挙運動に当たる」との前提で)71万5000円は、実際には、SNS運用等の選挙運動の報酬であったが、請求書上の名目を(1)~(5)として支払った。
(イ)斎藤氏側がmerchu社への71万5000円の支払の理由として、依頼したことを認めている(1)~(5)は選挙運動に該当し、買収罪が成立する。
(ウ)斎藤氏側が説明するとおり、折田氏がボランティアとして斎藤氏を応援していたのであれば、「選挙運動者」であり、(1)~(5)が機械的労務だとしても、いかなる名目であれ、斎藤氏側からの折田氏側への報酬支払は、買収罪に当たる。
(ア)については、いくらmerchu社側がSNS 運用を斎藤氏のために行った事実があり、71万5000円がその報酬として支払われた疑いが強いとしても、実際に他の名目で支払われている以上、それらが SNS 運用という選挙運動の対価を含む趣旨で支払われたことを立証するためには、当事者間でその旨の合意があったことの証拠が必要です。それを当事者が認めなければ、原則としてそのような認定は困難です。
(1)~(5)の業務の一部が実際には行われておらず、発注の実体がないということであれば、SNS 運用という選挙運動の対価であることが客観的に明らかですが、そうでない限り、被疑者側の自白がなければ、(ア)の構成は取りえないということになります。
(イ)については、実際に支払いの名目とされている(1)の公約スライドの作成、(2)~(5)の各種デザインなどとして行われた行為が、知事選挙で斎藤氏を当選させるための主体的・裁量的な行為であるかどうかが問題となります。
(1)については、公約スライド作成の目的が一般的な政治活動のためのものだったのか、兵庫県知事選挙での当選を目的とするものであったのかがまず重要となります。そして斎藤氏側から公約のワード文章を受け取り、それをスライド化する作業に、斎藤氏を知事選挙で当選させる目的がどれだけ強く表れているのかが重要です。
(2)~(5)については、そのうち、(2)のチラシのデザイン、(4)のポスターのデザインは、作成費用が公費負担の対象なので、デザインと印刷の両方を併せて業者に依頼すれば、すべて公費負担にすることができたはずです。それを、敢えてデザインだけmerchu社に発注したのは、斎藤氏を当選させるためデザインの統一化を図るという「主体的裁量的な行為」としてのデザインを依頼するためではないかが問題になります。
最後の(ウ)は、71万5000円について、斎藤氏側の説明の通りであっても、特定の候補者を当選させるための選挙運動を実際に行っている「選挙運動者」に対する支払いは、機械的労務の対価であっても買収罪に該当するという判例法理によれば、買収罪の成立は免れられないという考え方です。
ここで問題になるのが、斎藤氏側が認めているのは折田氏が個人のボランティアとして斎藤氏の選挙運動を行っていたことであり、一方で支払先は折田氏個人ではなくmerchu社という法人だということです。merchu社のような実質的に折田氏の個人企業のような法人に対する支払いは個人への支払いと同視できると考えるのが合理的です。買収罪と犯罪の性格、構成要件が類似している贈収賄罪では、収賄者が管理・支配する法人への支払を収賄者への賄賂と認めた例は数多くあります。最近の例では、五輪汚職事件で収賄で起訴された高橋治之氏とコモンズの関係があります。
しかし、公選法違反の買収罪は、これまでは選挙運動者が個人、その対価支払も個人というのが通常で、法人が絡んだ選挙運動や法人への支払いが問題になることは殆どありませんでした。それだけに法人への支払いを買収罪でどのように処理するかは、SNS運用等が重要な選挙運動の手段になってきたことに伴う公選法をめぐる今後の一つの課題でもあります。
その点について検討する中で、公選法221条1項2号の利害誘導罪の適用という重要な選択肢に思い至ったということです。この利害誘導罪は、会社等に対して利益を供与して、それと特殊の直接利害関係を利用して有する個人の選挙運動を誘導することで成立します。これまで、買収罪では、贈収賄のように法人を個人の財布とみなす事例が見当たらないのも、公選法には利害誘導罪があるからとも考えられます。
以上の第1及び第2の点について、詳細な分析検討を行っていきます。
第1の点については、次の投稿【折田氏note記事の内容と裏付け証拠、斎藤氏側説明を徹底分析する】で詳しく述べます。それに続く【斎藤氏側からmerchu社に支払われた71万5000円についての買収罪の成否】では、第2の点について詳しく論じます。
すでに登録済みの方は こちら