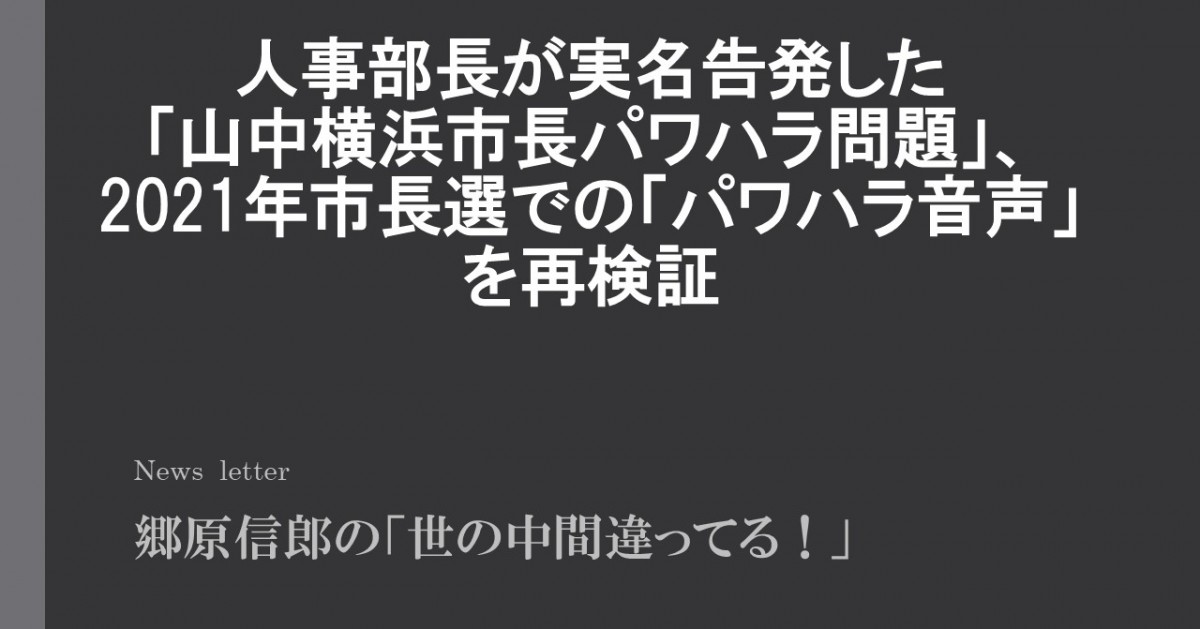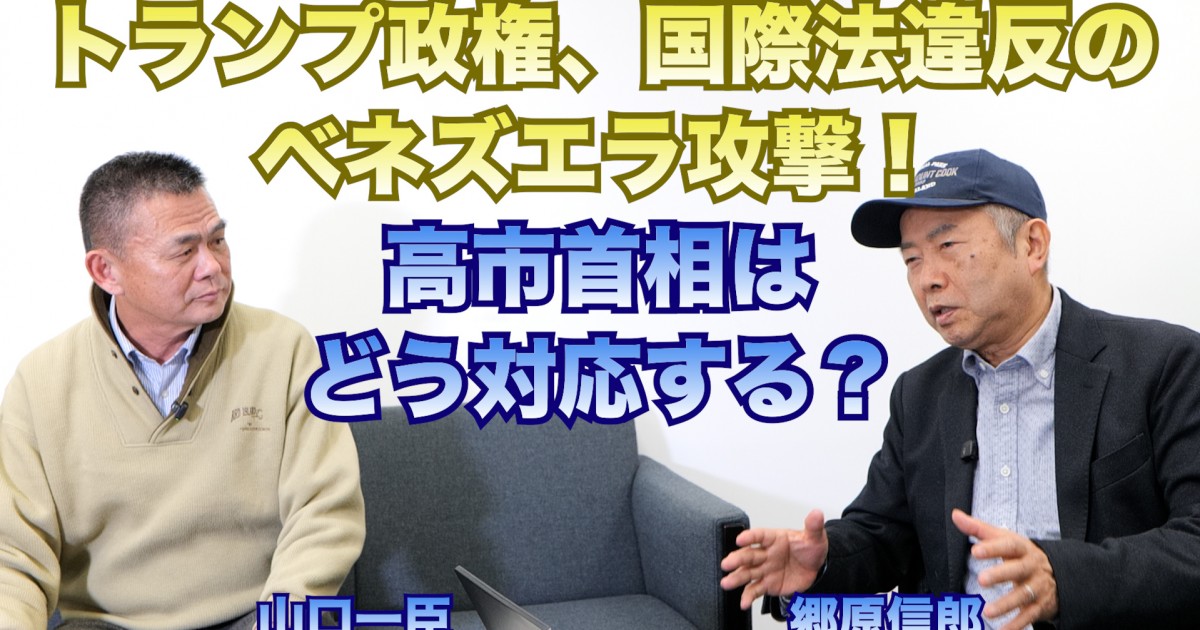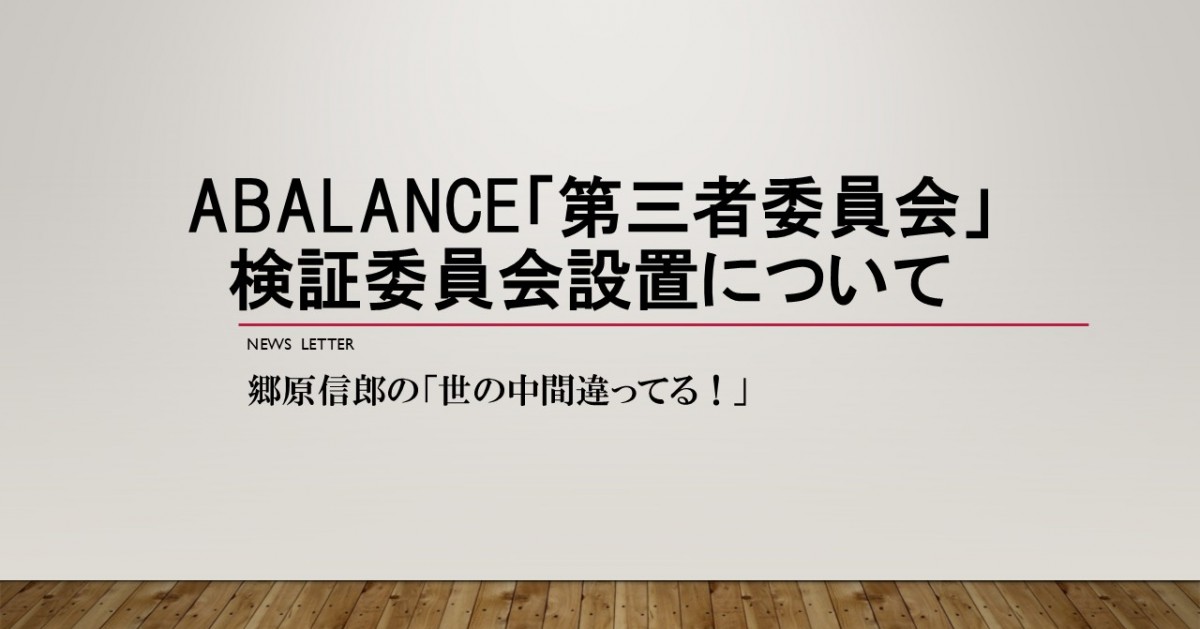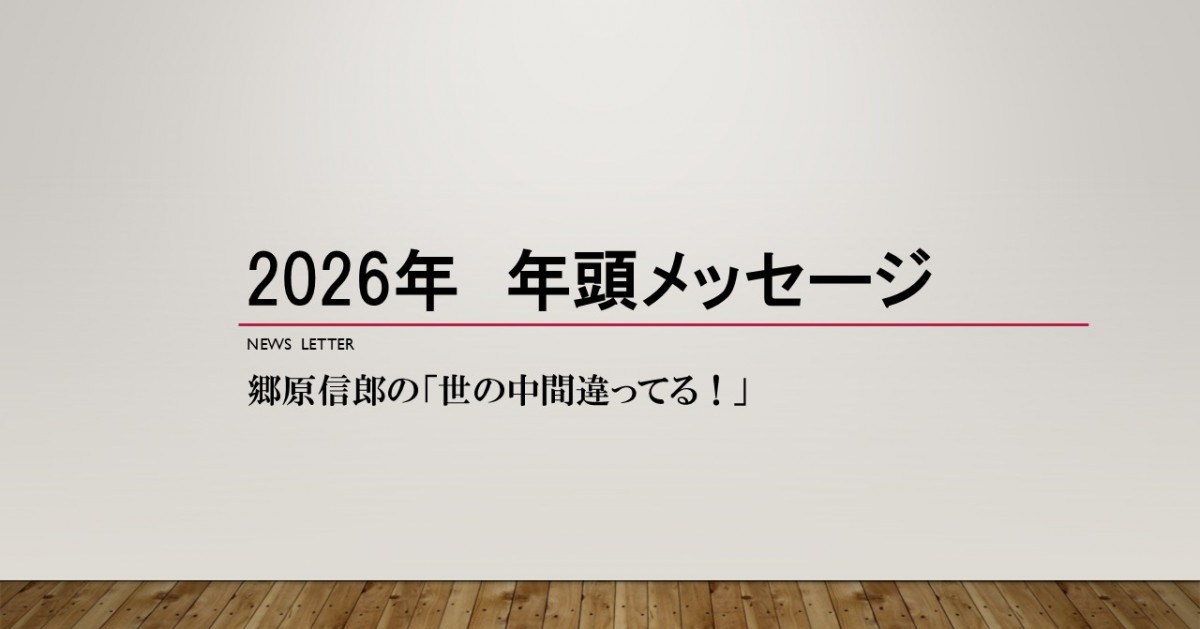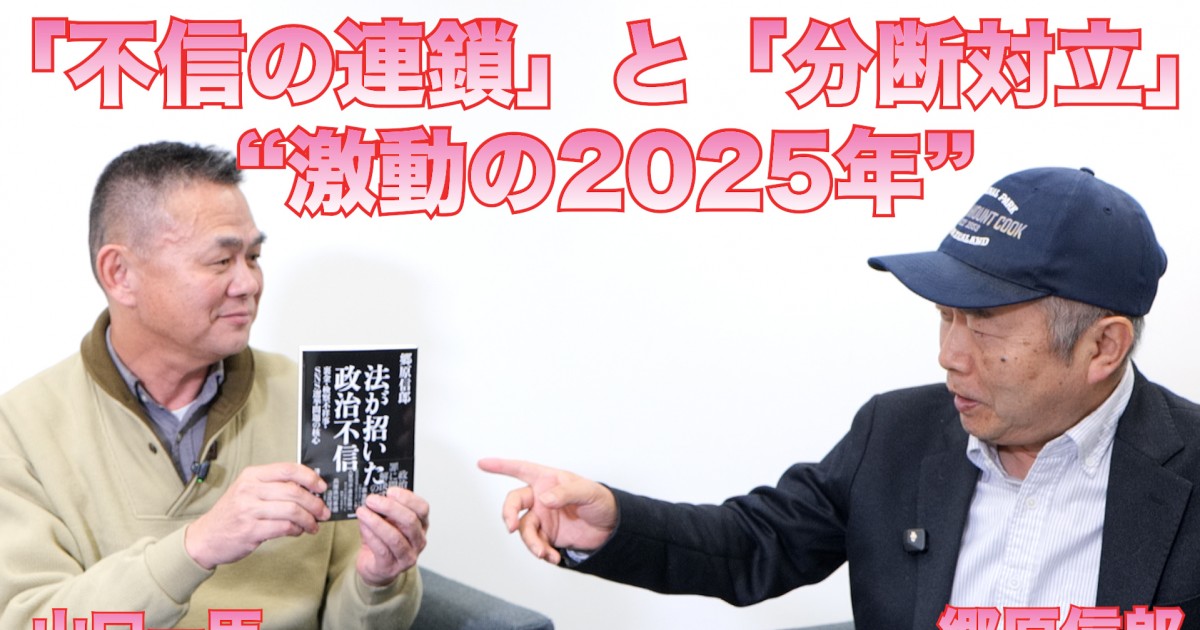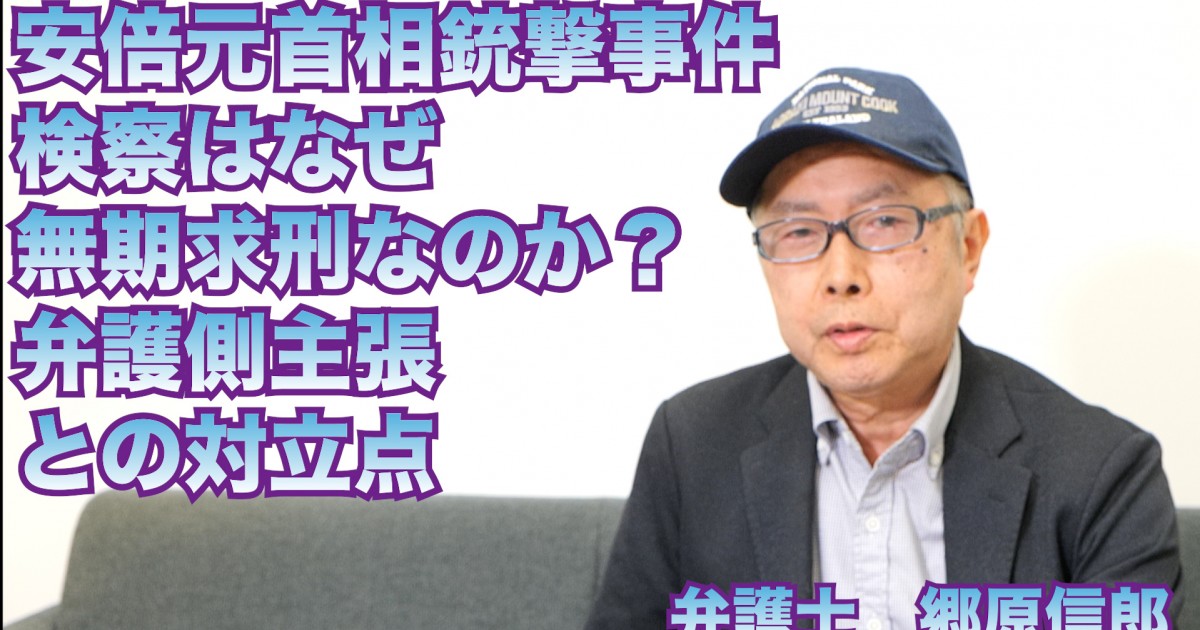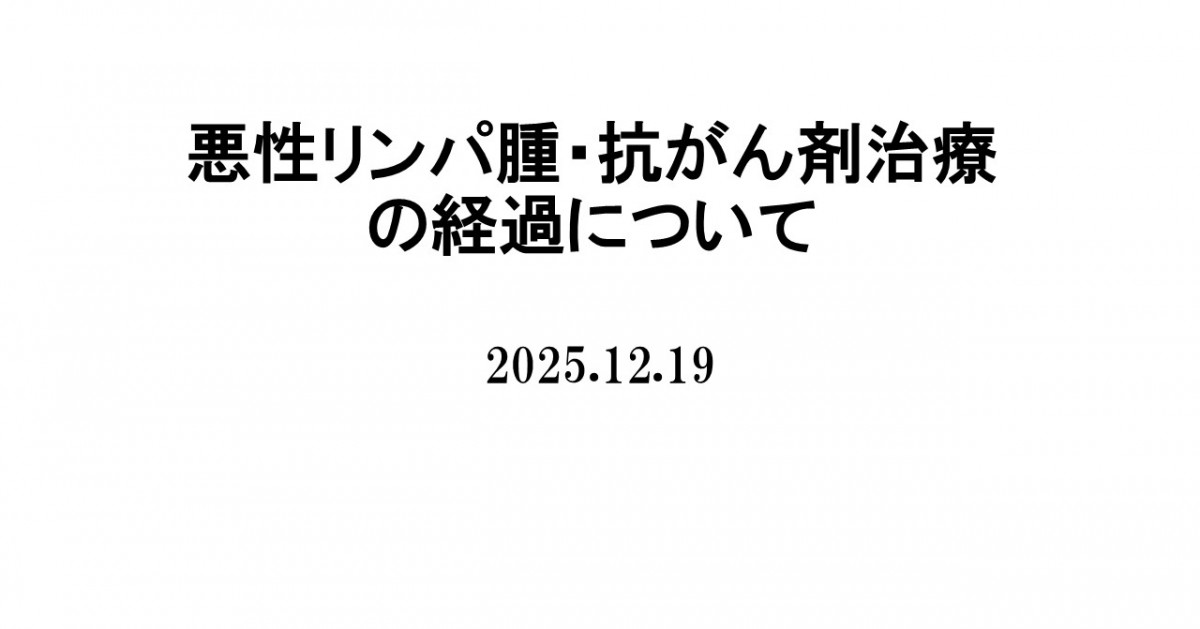侮辱罪の法定刑引き上げで、一層重要となる“略式手続の正確な理解”
6月26日付けの神戸新聞に、以下のような記事が出ました。
神戸区検は25日までに、X(旧ツイッター)に投稿した個人を侮辱する発信をしたとして、元民放アナウンサーの男性(64)を侮辱罪で略式起訴し、神戸簡裁が科料9千円の略式命令を出した。男性は同日、処分に対し不服申し立てをする意向を明らかにした。
兵庫県の告発文書問題に関連する書き込みをした投稿者に対して、男性がユーチューブで侮辱するような発言をしたとされる。
斎藤元彦知事をめぐる様々な問題で斎藤派・反斎藤派の分断対立が続く兵庫県で、侮辱罪で科料の略式命令を受けたこの男性について、一部のYoutuberらがSNS上で「犯罪者」「前科者」などと騒ぎたて、男性が正式裁判申立の方針を明らかにする事態となっています。
「略式手続」とは
「略式手続」は、罰金・科料という比較的軽微な刑事事件の簡易迅速な処理手続であり、道路交通法違反、交通事故、暴行・傷害等の多数の事件が、この「略式手続」で処理されています。
この略式手続が、SNSやインターネット上での悪質な誹謗中傷が社会問題化したことを受け、令和6年の刑法改正による法定刑引き上げが行われた「侮辱罪」に適用されたのが、この事件です。
侮辱罪については、従来の拘留・科料から、法定刑が長期3年以下の拘禁刑、罰金・科料に引き上げられたものの、実際には、略式手続で罰金・科料で処理されるものが多いと考えられます。
侮辱罪は、名誉毀損と同様に、公然と人の社会的評価を低下させる発言を行う行為であり、事実の摘示による名誉毀損とは異なり、事実の摘示を伴わない意見・論評である場合が多いです。侮辱発言の原因となった「被害者」側の行為が先行している場合などでは、そのような行為や侮辱発言の正当性をめぐって評価が難しいケースも生じます。それだけに、「略式手続」という手続が正しく理解されていないと、思わぬ社会的混乱を引き起こすことになりかねません。
今回の男性と、X(旧ツイッター)に投稿した個人との間の事件での騒ぎも、「略式手続」への誤解が大きな要因となっています。
「略式手続」についての誤解
被疑者が略式手続に応じて略式命令が出されるのは、被疑者が犯罪事実を認める場合に限られるかのような認識があるようですが、それは誤りです。
「公訴提起」と「略式命令の請求」という二つの訴訟行為が併せて行われるのが検察官による「略式起訴状の裁判所への提出」です。略式請求の起訴状には、「公訴を提起し、略式命令を請求する」と書かれています。つまり、法律上「略式起訴」という一個の法律行為があるわけではありません。
略式手続に対する被疑者の同意書は、
《略式請求が行われると、裁判官が略式命令を発し、その送達ののち「14日経過で略式命令が確定」する、又は、その間に「正式裁判申立て」がなされると通常公判になる(この場合は、略式命令は失効する)》
という「略式手続」を取ることに同意するものに過ぎず、略式同意書に署名することには、公訴提起について公訴事実を認めるという意味はありません。
検察官としては、略式手続きへの同意書(略式請書、通称「りゃくうけ」)をとるときに、罰金・科料求刑で起訴する方針を述べることが多いと思いますが、必ずではありません。最終処分が決まっていない時点で、「略式請求をすることになった場合に」と言って、条件付で略式同意書への署名を求めることもありますし、同意書への署名をさせた後に、上司の決裁の段階で不起訴になることもあり得ます。
また、否認事件であっても、罰金以下の求刑を予定している事件で、検察官が証拠十分と考えた場合は、否認している被疑者に罰金求刑で略式請求を行う方針を告げ、略式命令に対して14日以内に正式裁判を申立てることができると説明した上で、略式手続への同意を求めることもあります。
その典型例が、拙著【法が招いた政治不信】(KADOKAWA)で紹介した、私が長崎地検次席検事時代の2003年に捜査指揮をした自民党長崎県連事件の最終着地点となった政治資金パーティー裏金をめぐる政治資金規正法違反の事件です。
当時長崎県議会議長だったK氏は、最初の取調べでは裏金の取得と政治資金規正法違反を認めていましたが、その後、否認に転じていました。
最終処分を行う時点で、次席検事の私が直接K氏に略式手続の告知を行いました。
「罰金求刑で起訴します。それについて、裁判所に略式命令を請求します。略式命令というのは、正式な公判を開かず、書面審理だけで裁判所に罰金支払の命令を出してもらう制度です。略式命令に対しては、14日以内に正式裁判を申立てることができます」
と説明し、略式手続に同意するかどうか意向を確認しました。
K氏は、同意書に署名した上、
「弁護士と相談し、正式裁判を申立てることになると思います」
と述べました。その直後、マスコミにも『無実であり、正式裁判を申立てる』と述べていましたが、結局、正式裁判は申立てず、政治資金規正法違反の略式命令が確定し、K氏は県議会議員を失職しました。
つまり、検察官が被疑者に略式手続への同意を求めることは、起訴することの告知とは別の行為であり、略式手続の同意は、あくまで手続への同意であって、犯罪事実を認める意味ではありません。
同意すると、略式命令が送達され、それに応じるかどうか考慮する期間として、正式裁判申立期間の14日間が経過して、初めて犯罪事実が確定し、罰金・科料が前科となります。
ここで重要なことは、略式手続自体は非公開の書面審理であって、罰金・科料の納付を命ずる略式命令が被疑者に送達されるだけなので、「被疑者の処罰」が世の中に公開されることは予定されていません。検察官も、それを前提に略式手続の告知を行っているはずです。
略式手続告知の際、検察官は、「1万円以下の科料」について、同じ「カリョウ」でも、行政罰としての「過料」ではなく、刑罰としての「科料」であることを丁寧に説明するのが望ましいのですが、全てのケースでそこまで説明されているとは言い難いでしょう。
実際に略式命令が送達されれば、科料を支払わない場合の「労役場留置」のことまで書かれていることから、一般人であっても刑事罰であることはおそらく認識できると考えられますが、それもあって、略式手続きの告知の際に十分に理解させる説明が行われないこともあります。
被疑者側は、略式手続を告知された際には、「非公開の書面審理で少額の金銭支払を命じられ、支払うことで終わり」と認識することも多いのではないでしょうか。
しかし、告訴人の「被害者」側には、処分通知書が送付され、そこに、「処分区分 起訴」と書いてあると、略式手続と認識することなく、被告訴人が「起訴された」と認識します。そして、告訴人が被告訴人と対立しているような場合には、それを世の中に明らかにしようと考えることになります。
男性は、既に正式裁判の申立の方針を明らかにしており、その主張は、今後、裁判に至る手続の中で明らかにされるものと思われますが、本件で、侮辱罪で略式命令を受けた男性のYouTubeでの発言の原因となったのは、匿名Xアカウントでの阪神淡路大震災30年の慰霊のために神戸を訪問された天皇皇后両陛下と斎藤知事との写真に、「誰が黒幕なの?」「丸尾です」などの言葉が交わされたかのような会話文を加えた画像です。
兵庫県民であれば、このような投稿がネット上で拡散されていることに対して強烈な反感を抱くのは当然とも言えるのであり、男性としては、意見論評としての正当性があり、違法性が阻却されるなどと主張することになるのではないかと考えられます。
このように考えると、「略式手続」であっても、従来、その大半を占めていた道交法違反、暴行、傷害の事件とは異なり、侮辱の事件の場合、刑事事件としての評価が単純ではないものが多いと考えられるので、手続について正しく理解することが一層重要と言えるでしょう。
すでに登録済みの方は こちら