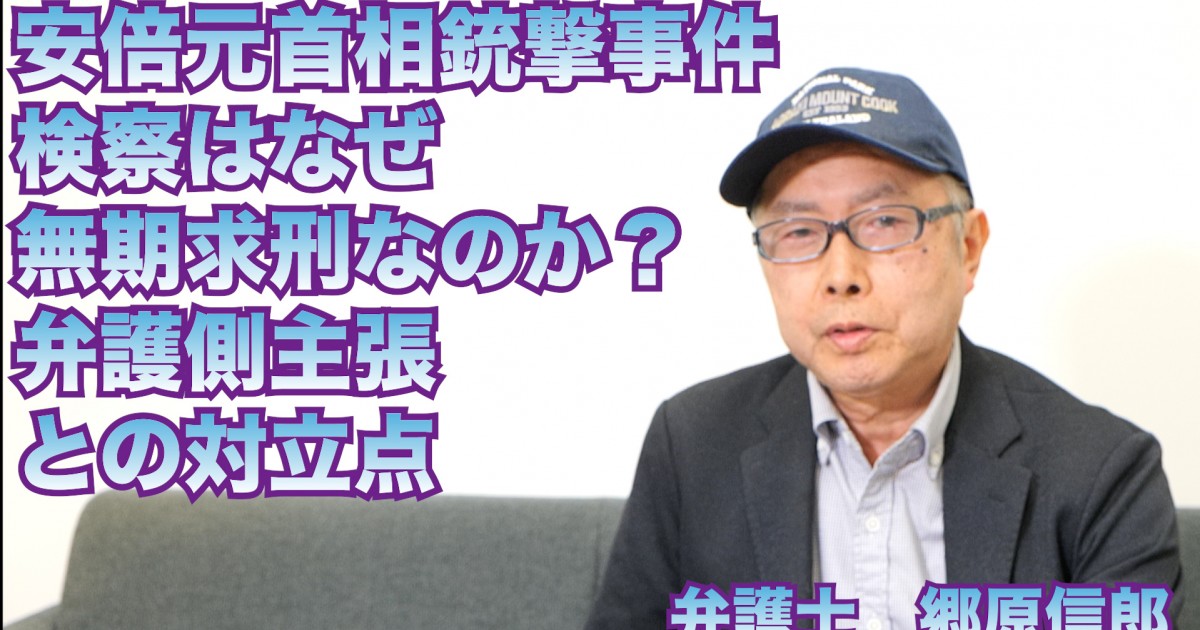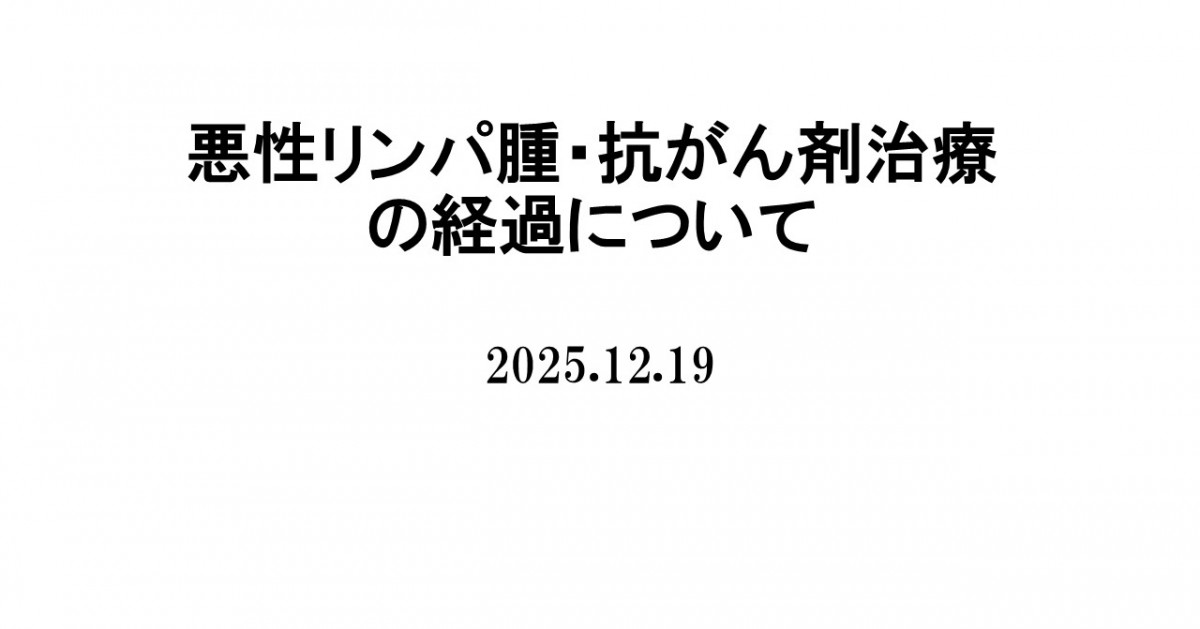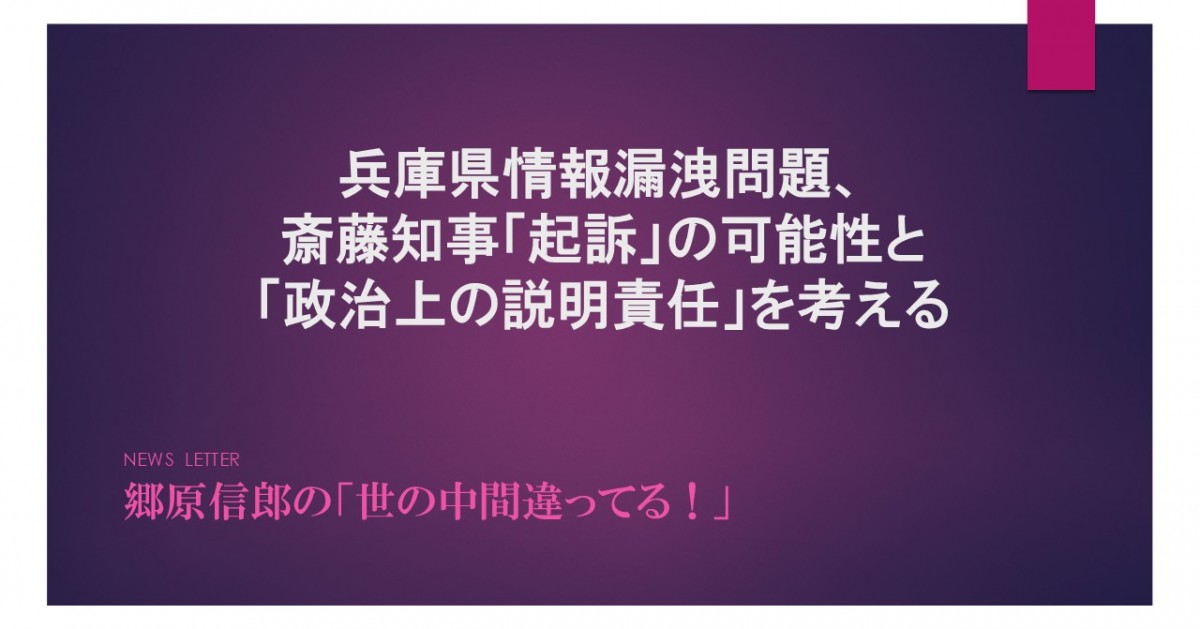世界最高額ともいわれる東電株主代表訴訟・地裁判決と、その背景を読み解く #2《無料版》
2.企業が起こした大事故、公害などに対する一般的な対応
まず、本件(東京電力福島第一原発事故)をめぐる法律問題を考える前提として、企業活動によって発生した事故・公害などをめぐる法律関係について、基本的な理解が必要になります。
被害者が求める、事故等に関する責任追及としては、「刑事責任」(刑法などの法令違反について懲役刑・禁固刑・罰金刑などに問うこと)と、「民事責任」(損害を金銭で賠償すること)の2つの方法があり、さらに、被害者の救済と直接関係はありませんが、事業によって、営業停止、許可取り消しなど、「行政責任」が問われる場合があります(【表3参照】)。また、その追及の対象も、会社などの「法人に対するもの」と、取締役や従業員などの「個人に対するもの」の2通りがあります。

刑事責任については“個人の責任”、事故や公害の発生に関わった直接の担当者や、その監督責任を負う上司、経営責任を負う取締役などが、業務上過失致死傷罪に問われるのが一般的です。
民事責任については、その企業の労働者や、サービス利用者(乗客等)などの契約上の責任を追及できるような例外的な場合を除き、一般的には、“会社(法人)”や、取締役や従業員などの“個人”に対する不法行為責任(民法709条など)の追及が行われます。
また、事故や公害を起こした企業の監督官庁について、国が監督官庁の権限(規制権限)を行使して大事故・公害などを防ぐべきであったのに、適切な権限行使が行われていなかったといえる場合には、その「規制権限の不行使」が違法となり、“国や自治体”に対して国家賠償法上の国家賠償責任を追及していくことになります。
なお、後に詳細な検討をし、理由をお話しますが、本件でなされているような、事故で会社が被った損害について株主代表訴訟を提起するという対応は、過去にはあまり例がなく、かなりイレギュラーな対応ということになります。
3.本件理解の前提として ~「過失」について~
(1)「過失」の有無が重要となる理由(過失責任の原則)
A.過失責任の原則
上記の対応にあるような、不法行為責任の追及、国家賠償責任の追及において、共通する最大の問題が、「過失」の有無です。
原則として、損害を賠償する責任は、事故や公害によって損害(結果)が生じた、ということのみで負うもの(結果責任)ではありません。故意(わざと)、もしくは過失(不注意)によってその結果を生じさせてしまったときに、はじめて賠償責任を負うことになります。これを「過失責任の原則」と言います。
例えば、民法709条は、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」
と規定して、損害賠償請求に「過失」が必要であることを明記しています。また、公務員の不法行為によって国民が損害を受けた場合に、国又は地方公共団体に損害賠償請求するための法律である国家賠償法1条も、
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
として、損害賠償請求に「過失」を要求しています。
この「過失責任の原則」が採用されている理由は、“結果責任が原則”の社会を想像するとわかりやすいです。仮に、他人に損害を生じさせた以上は、すべて無条件に責任を負って賠償しなければならないとすると、車の運転やビジネスなど、多少のリスクを伴う活動を多くの人が躊躇するようになり、社会経済活動は円滑に動かなくなります。ましてや高度医療など、有用性も高いがリスクも高い手術をやる医師など、どこにも存在しなくなるでしょう。
しかし、「過失責任の原則」の下では、注意深く運転し、投資し、手術をしていれば、仮に損害が生じる結果となったとしても、賠償責任を負わないこととなり、人はこうした活動を安心して行うことができるようになります。個人の自由な活動を裏面から支えるものとして、「過失責任の原則」は現代社会において必須のものといえるのです。
B.立証責任と過失責任の原則の修正
なお、不法行為責任の追及や国家賠償責任の追及において、相手方に「過失」があることの証明は、損害賠償請求をする側が立証しなければなりません(立証責任と言います)。条文の文言や構造がそのようになっていることや、基本的に請求する側が証明することが公平である、といった考え方が背景にあります。
これによって、突然、Aさんが見ず知らずの人(Bさん)からぶつかられ「怪我をした、弁償しろ」などと言いがかりをつけられても、反論として「自分(Aさん)に過失がないこと」を証明する必要はなく、そのBさんが「相手(Aさん)に過失があること」を証明できなければAさんは賠償責任を負わないということになります。そういう意味では妥当な結論のように思われますが、実際に大きな損害を被った被害者にとって、加害者の落ち度を立証することは容易ではなく、立証できなければ損害賠償請求ができない、というのでは不公平な場合があり得ます。
そのため、過失責任の原則は修正されることがあり、後述の「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)に代表されるように、立法によって「無過失責任」としたり、「自動車損害賠償保障法」における自動車による人身事故の賠償(3条)のように、加害者が、自分には落ち度がなかったことを立証しなければ賠償責任を免れられないとして、賠償請求をされる側に「過失の立証責任を転換」したりして、被害者の救済が図られています。
(2)「過失」の立証とは(①予見可能性と②結果回避可能性)
では、「過失」というのは、どのようなものなのでしょうか。それは、どのように立証すればよいのでしょうか。
日本語を素直に解釈すれば、「過失」とは“不注意”であり、緊張を欠いた心理の状態のことを意味するのですが、他人の内心、主観を立証するのは困難です。
現在の一般的な考え方によれば、「過失」とは、客観的な“注意義務違反”を意味すると考えられています。そして、その“注意義務違反”は、「予見可能性を前提に行為者に課される結果回避義務の違反がある場合」であるとか、「予見可能性を前提とした予見義務違反及び結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反がある場合」に認められる、と説明されています。
ここで重要になるのは、①予見可能性(危険な事象や被害(結果)が発生する可能性があることを事前に認識できたかどうか)と、②結果回避可能性(予測した危険に対して、それを回避するための適切な措置が講じたとすれば、危険な事象や被害(結果)が発生しなかったかどうか)です。加害者に責任を問う大前提として、他人へ損害を生じさせる等の「結果を予見できない」のであれば、その結果発生を避けるべきであるとはいえませんし、仮に結果を回避しようと努力したとしても、「結果を回避できる可能性がない」のであれば、やはり責任を問うことはできないためです。
①、②の両方が充たされる場合、つまり、行為者にとって、結果が予見可能で、回避することもできたのに、行ってはならないことを行った(作為)、或いは、行うべきことを行わなかった(不作為)、と言える場合に、「過失」があるということになります。そして、そのような「過失」と結果(事故等)との因果関係が認められる場合、つまり、行うべきではなかった行為を行わなかったら、或いは、行わなければいけない行為を行っていたら、事故が発生しなかったと言える場合に、損害賠償責任が認められることになります。
このような①予見可能性と②結果回避可能性、どちらか一方でも否定されれば、責任を問うべきとはいえず、「過失」は否定されます。通常の裁判実務において、「過失」の有無が争われる場合、①予見可能性と、②結果回避可能性の有無が、主要な争点となります。
なお、刑事責任として業務上過失致死傷罪に問う場合にも「過失」が問題となり、民事と刑事では若干考え方が異なる点もあり得るのですが、①予見可能性と、②結果回避可能性が主要な争点となることについては変わりませんので、本件の理解に関しては、基本的には同様に考えることとします。
4.本件理解の前提として ~「原賠法」について~
(1)原賠法による損害賠償責任の基本的な枠組み
また、本件を理解する前提として、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)の基本的な理解も必要となりますので、簡単に説明します。

A.無過失責任
まず、原賠法の特徴のひとつは、さきほど「3.(1)A.過失責任の原則」で述べた通り、「無過失責任」であるということです。
原子力事業は現代科学技術の最先端を行く事業であるため、原子力事故による損害について、過失責任の原則という一般原則通りに、被害者が原子力事業者の過失を立証することは極めて困難です。
また、原子力事業は高度で、かつ、完全には制御することができない危険なものであり、注意深く管理監督をしていたとしても、事故による被害の発生の可能性をゼロにすることはできません。事業者側は、そもそもそのような危険な施設を設置し、事業を行うことで巨額の利益を得ているわけですから、危険なものを管理する者は、過失がないとしても、そこから生じた損害に対して責任を負うべきだ、として無過失責任を負わせることを正当化する根拠もあります(このような考え方を「危険責任」といいます)。
したがって、被害者からの賠償請求を容易にするという被害者保護の観点から、原賠法は、被害者が加害者に故意又は過失があったことを立証する義務を不要としています(3条)。
なお、原子力発電所を持つ諸外国においても、無過失責任は一般的に採用されており、世界的にみて、無過失責任が原賠法制度の基本的な原則の一つと理解されています。
B.無過失責任の免責(原賠法3条1項ただし書き)
ところで、原賠法3条1項は
「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」
として、「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」による場合には賠償責任を負わない規定となっています。そのため、未曽有とされた東日本大震災が、この「異常に巨大な天災地変」に該当し、原発事故の加害者となった東電は、賠償責任を負わないのではないか、ということが当初問題となりました。
東電の勝俣恒久元会長の当時のインタビュー発言(SankeiBiz「東電・勝俣恒久会長インタビュー詳報」2012年6月26日(現在、元記事は削除されて見れない))や、当時の東電の動きに関するメディアによる事後的な検証報道(朝日新聞「東電「国有化」の実像 原発事故から10年(第2回)」2021年1月6日)などにより、東電は当初、この免責を主張するつもりであったことが明らかになっています。
しかし、東電は日本中を放射能汚染の恐怖に陥れた事故の当事者であり、当時の世論や社会情勢からして、東電を免責するという選択肢は、政府や、原賠法を所管する文科省にはまったくなかったとされています。
また法的にみても、「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」との文言からして、単なる不可抗力は想定しておらず、戦争などに比べても「想像を絶するような事態」「超不可抗力」だと解釈できます。そして、実際に、世界では、東日本大震災を上回るようなアラスカ地震(1964年)やスマトラ沖地震(2004年)も過去に発生しており、震災として「異常に巨大」とまではいえないのではないか、とも考えられています。
現在では、“東日本大震災クラスの震災”では原賠法3条1項ただし書きによる免責は認められないとの理解が一般的と思われます。また東電は、原賠法3条1項の無過失責任を負うことを前提として、国からの多額な「必要な援助」(16条)を受けているので、今になって東電が無過失責任の免責を主張することはあり得ません。
しかし、勝俣元会長が、SankeiBizのインタビューで
「今でも、(免責を)申請していたらどうだったんだろうという思いはあります」
と語り、朝日新聞の検証報道でも
「あの条文を読めば、誰だって免責が適用されると考える」。東電の関係者は今でも口々にそう語る。
などと述べているように、東電社内において、東京電力福島第一原発事故について、本来は免責されるべき賠償責任であり、「法令を超えた対応を押し付けられている」という認識があるのではないか、とも考えられます。
C.無限責任
原賠法3条には、とくに原子力事業者の責任制限、金額の上限等についての規定がないことから、他の一般的な法律同様、原子力事業者は無限に責任を負うものと理解されています(無限責任)。
原発事故について、このような無限責任制を採用する国は、他にドイツやスイスなど極めて少数であり、アメリカをはじめ、他の多くの国の原賠法制度については、原子力事業者の賠償責任に一定の限度を設けていて、世界的には、有限責任が原賠法制度の基本的な原則の一つと理解されています。
原賠法は古く1961年に制定された法律ですが、事業者が有限責任しか負わないとなると、国として残りの賠償責任を引き受け、巨額の財政負担を負わなければならないことを、当時の財政状況下で大蔵省が懸念したことや、広島、長崎への原爆投下から15年ほどしか経過しておらず、事業者の責任を制限することについて、当時の世論への配慮もあった、といったことが、無限責任を採用した理由とされています。
D.原子力事業者への責任集中及び求償権の制限
原賠法4条1項は、賠償責任を負う原子力事業者以外の者は一切の責任を負わないとする原子力事業者への責任集中について規定しています。
そして、その責任集中の趣旨をさらに徹底するため、原子力損害については製造物責任法等を適用除外とすることとし(同条3項)、賠償責任を負った原子力事業者は、他に自然人(法人ではない人、個人)の故意により損害が発生した場合にのみ求償権(他人に代わって支払いをした場合に、他人に対してその返還を求めること)を有することとして(5条1項)、メーカーや工事会社等の原発関連事業者は、よほどのことがない限り、原子力損害についての損害賠償責任を負わない仕組みとなっています。
仮に、製造物責任法が適用される場合には、原発メーカーは、「欠陥」のある原発プラントを設置した際、「無過失責任」を負うはずでした(製造物責任法3条)。製造物一般について、メーカーはそれで儲けているのだから、製造物に「欠陥」があれば、過失の有無を問わず責任を負うべきとする考え方(これを「報償責任」といいます)などによるものです。
メーカー等のこうした重い責任を免除し、原子力事業者にのみ責任が集中する仕組みを採用した根拠は、①被害者が賠償請求の相手方を容易に特定できること、②メーカーや工事会社等の原発関連事業者を被害者の賠償責任との関係で免責することにより、民間企業が巨額の賠償責任を負うことを恐れて参入しなくなる事態を避け、原子力産業を健全に育成し、原発資材供給等の取引を容易にすること 、③メーカー等も責任を負う可能性があれば、それに対して保険加入を求めるようになるが、そうなると保険業界として各事業主体に十分な保険を用意できなくなるおそれがあるので、原子力事業者のみに責任を負わせ、重複なく保険による賠償措置を講じることができるようにして、原子力事業者のために提供される保険の引受能力を最大化するため、などと説明されています。
しかし、本来は、「欠陥」のある原発プラントを設置した場合に「無過失責任」を負うはずの原発メーカーが製造物責任法の適用対象から除外され免責された経緯には、米国のGE(ゼネラル・エレクトリック)、東芝等の原発メーカーが関わっていました。その点については、「4(2)D」で後述します。
★ 続きは有料配信でお届けします。お読みになりたい方は、この「登録する」ボタンから「有料プラン」を選択し、登録画面にお進みください。
すでに登録済みの方は こちら